お正月に飾るしめ縄。
最近はモダンなデザインのものも増えてきて、クリスマスが終わると、リースを外してしめ縄を飾るご家庭も多いですよね。
でも飾る時はよいのですが、外す時期はいつ頃が正しいのでしょうか?
また外した後の捨て方は?ゴミの日に出すのは気が引けるし・・・。
などなど、実は分からないことが多くて、しめ縄を飾ることを躊躇してしまいますよね。
そこで今回は、お正月のしめ縄の作法について調べてみました。
[quads id=1]
しめ縄を外す時期はいつごろ?

お正月の飾りと言えば、しめ縄以外にも、鏡餅や門松などがあります。
鏡餅を下げる日は、1月11日の「鏡開き」の日にお雑煮として食べることが有名ですので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
一方、しめ縄や門松は、「松の内」まで飾ると言われています。
「松の内」とは、元旦にお迎えした歳神様(としがみさま:新年の幸福をもたらすために高い山から降りてくる神様)やご先祖様が家にいらっしゃる期間とされています。
お正月飾りには、お迎えした歳神様たちをおもてなしする意味が込められているのです。
その歳神様がお帰りになるのが6日の晩。
よって7日までを「松の内」として、お正月飾りのしめ縄も「1月7日」に外すところが多い(特に関東地方)と言われています。
[quads id=2]
◯地域によって松の内の時期が違うの?
ただし、関西地方ではこの「松の内」を「1月15日」として、15日に外すところが多かったり、地域によって実に様々なのです。
例として、以下にしめ縄を外す日を調べてみました。
◆しめ縄を外す日
- 1月4日 (3が日が終わったら外す説)
- 1月7日 関東地方・中国地方
- 1月8日 四国地方
- 1月10日 北関東地方・福岡
- 1月15日 関西地方・四国地方
- 2月19日 沖縄
また例えば同じ関東地方でも、7日ではなく別の日に外す、というところもあるそうです。
外す時期については、地域によって異なるため、お住まいの地域であらかじめ確認しておくとよいでしょう。
しめ縄の処分の仕方は?
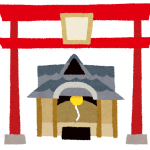
上述のように、しめ縄などお正月飾りは、歳神様をおもてなしする為のものです。
古いものを使い回したりせず、毎年新しいものを用意します。
では、外した後のしめ縄はどうやって処分すればいいのでしょうか。
◯どんど焼きでお焚きあげする
「松の内」を過ぎて外したしめ縄などは、神社やお寺で行われる「どんど焼き」で焚き上げてもらうのが一般的です。
※「どんど焼き」は、「どんと焼き」や「左義長」、「お焚き上げ」と言われることもあります。
この「どんど焼き」は、小正月の1月15日に行うところが多いようです。
また神社やお寺によっては、行事の当日でなくても、しめ縄などを預かって別途焚き上げてくれる場合もあります。
持参する時は、しめ縄のビニール系の飾りやプラスチック、針金などはあらかじめ外して、焼いてもらうようにしましょう。
◯個人でゴミの日に出す

また最近は、環境問題などを考慮して、焚き上げをしないところも増えているそうです。
近くにお焚き上げをしている神社がない、当日に持って行けないなどの事情がある場合には、個人で処分することになります。
個人(家庭)で処分する場合には、不燃物と可燃物に分別した上で、該当のゴミの日に出すようにとされています。
◯個人でゴミ出しする時の注意点
ただ、そもそも「どんど焼き」は、新年のしめ縄やお正月飾りを「神様にお返しし、祈祷する」という意味を込めて焚き上げてくれています。
やむを得ず、自分で処分しなくてはならない場合には、お清めをしてから、処分するようにしましょう。
お清めは、感謝の気持ちを込めながら「左、右、中央」と塩やお酒を振ります。
お清めが済んだら、紙に包んで、地域のゴミ分別の仕方に沿って出しましょう。
この時、できれば生活ゴミとは別の袋に入れて出すようにするといいですね。
[quads id=3]
まとめ
いかがでしたでしょうか?
しめ縄の風習には、今でも地域によって様々な特色があり、とても興味深いですね。
この機会に、お住まいの地域の慣習や風習を調べてみましょう。
またしめ縄には、おもてなしと新年の幸福を祈る意味が込められています。
地域の風習を大事にしながら、祈祷と感謝の気持ちを忘れずに、扱うようにしましょう。
[quads id=5]
[quads id=6]



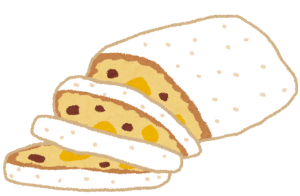
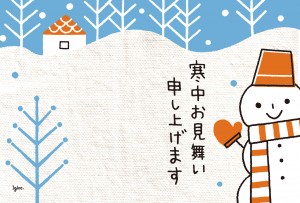

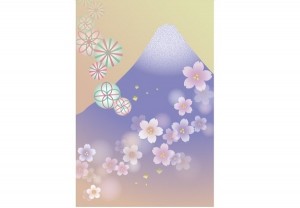


コメント