女の子がいる家庭では、桃の節句は雛人形が飾られ、ごちそうが並んで、華やかになりますね。
初節句を迎える女の子がいる家族にとっては、雛人形の準備など、忙しいけれど楽しみな日々が待っています。
でも、自分の母親が飾ってくれていた雛人形、今度は自分が娘のために飾り付けをしてお祝いするとなると、いろいろな疑問がわいてきますよね。
飾る時期に決まりはいるのか、飾り方に注意しなければいけないことはあるのか、何歳まで飾り続けるものなのか、と気になることをまとめてみました。
[quads id=1]
雛人形を飾る時期
雛人形を飾る時期は、できるだけ早く飾りたいという場合は、2月3日の節分が終わってから飾ると良いでしょう。
また場所もとるので、ゆっくりでいいという場合は、2月19日頃を目安として、遅くても節句の一週間前までには飾るようにしたいですね。
なぜ2月19日なのかと言いますと、この日は「雨水の日」と呼ばれ、氷が水に変わり、本格的な春がいよいよ始まるという時期なのです。
この日に雛人形を飾ると、良い伴侶に巡りあうとも言われています。
雛人形を飾る位置は特に決まりはなく、どの方角でなくてはいけないということもありません。
直射日光が当たらない場所で、飾り付けがしやすい場所を選んで飾りましょう。
[quads id=2]
雛人形の飾り方
お内裏様とお雛様は左右どちらにすればいいのか迷いますが、一般的には結婚式の新郎新婦の並びと同じと考えます。
右側にお雛様、左にお内裏様というのが一番多い飾り方です。
子どもが赤ちゃんのときは無理ですが、ある程度大きくなってきたら、雛人形をお母さんと子どもが一緒に飾るという風景も、とても微笑ましいものです。
◯雛人形は何歳まで飾るものなの?
子どもが小さいときは、毎年桃の節句には雛人形を飾ってお祝いをしていても、ある程度成長してからはいつの間にか雛人形も飾らなくなっていた、という家庭も決して少なくありません。
現在の住宅事情を考えると、それも仕方のないことなのかもしれません。
雛人形は何歳まで飾るものなのかという疑問は、誰もが持つものなのですが、それはいつの間にか飾らなくなってしまったから出てくる疑問なのでしょう。
雛人形は何歳になるまで飾らなくてはならないとか、何歳になるとやめなければならないという決まりがあるわけではありません。
住宅事情にもよりますが、一年のうちのイベントの一つとして、大きくなってからも飾り続けるのもいいのではないでしょうか?
◯雛人形を娘に受け継いでもいいの?
お嫁入り道具として持っていくという人もいますが、お母さんが飾っていた雛人形を、その娘さんに受け継ぐのは避けた方がよさそうです。
なぜかというと雛人形は本来、女の子の厄除けの意味もあり、身代わりとなってくれる意味があるからです。
だから雛人形は、その持ち主の女の子だけに用意してあげたいものですね。
2月生まれの場合の初節句
1月に生まれた女の子なら、同じ年の3月3日が初節句になります。
迷うのは2月に生まれた場合ですね。
2月に予定日だと言われたけれど、予定日ぴったりに生まれることは稀です。
いてもたってもいられずに、人形だけでも見ておきたいと、人形店に雛人形を見にいくおじいちゃん、おばあちゃんも多くいます。
正式なルールというわけではありませんが、節句前3週間以内に生まれた子どもの初節句は翌年にすることが多いようです。
つまり、雛祭りの場合は2月10日以前に生まれた女の子が、その年に初節句となります。
初節句のお祝いは、親戚や友人などをできるだけたくさん招いて、できるだけ賑やかに楽しく過ごすようにすれば、思い出に残る初節句となることでしょう。
ちらし寿司や蛤のお吸い物、桜餅、白酒など、桃の節句につきもののごちそうと、たくさん記念写真を撮ることも忘れないようにしましょう。
[quads id=3]
まとめ
たくさんの人の思いがこもって贈られた雛人形ですので、大きくなったからと言って飾らなくなるのはもったいないですね。
何歳になっても一年に一度、雛人形を飾り付けして、健康と幸福を願ってお祝いしたいものです。
初節句の時にはそこまで先のことは考えないと思いますが、ぜひ毎年気持ちを込めてお祝いしてあげてください。
お祝いの気持ちがやっぱりうれしいですし、家族の思い出は多い方が絶対に楽しいですよ^^
雛人形の飾り方や飾る時期についても、もう一度確認しておいてくださいね。
料理も前もって準備を進めていきましょう。
簡単レシピで普段と違う料理に挑戦してみるのもオススメ
お祝いをする意味はこちら
せっかくのひな祭りですから、子供のためにもお祝いしてくれる親戚のためにも、楽しくお祝いしたいですね。
[quads id=5]
[quads id=6]



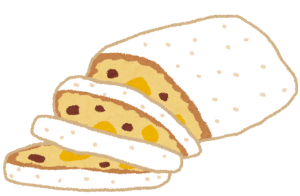

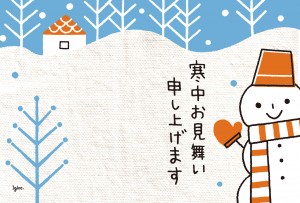

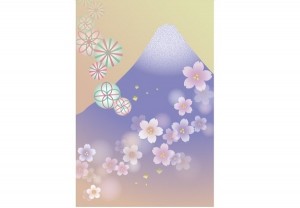

コメント