保育園(2歳から)に通っていなければ、幼稚園が子供が初めての社会生活を送る場になります。
突然、親と離れて、他の子供と集団で数時間過ごしますから、親御さんにとっては、いろいろと不安も多いことでしょう。
ですから入園式までに、幼稚園に少しでも早く適応できるように手伝ってあげることが大切です。
幼稚園ごとに様々な特色がありますので、事前の準備も異なりますが、どのような幼稚園であっても共通する項目をピックアップしていきます。
幼稚園前のお子さんがいるお母さんにシェアしてほしいと思います。また、あなたの子供が幼稚園の入園前であれば、はてなブックマークなどで保存しておくことをオススメします。
ぜひ折に触れて見返して頂きたい28項目になりますので、順番に確認していきましょう。
[quads id=1]
幼稚園生活をスムーズにする28のしつけ
1)自分の苗字と名前を言える
これは、何においても、とても大切なことです。
名前は、赤ちゃんの時から呼ばれているので、身についていますが、苗字は改めて親が教えなければなりません。
例えば、迷子になった時などは、フルネームで言えるほうが、何かといいのです。
2)電話番号が言える
これも名前と同じで、迷子等になった時に有効です。
親と離れている時間を持った子供には、暗記させるようにしましょう。
3)規則正しい生活をする
幼稚園前は、好きな時間に起きて、食べてという生活をしていた子供は、学校生活が始まると、その時間帯に合わせるのに、最初は大変苦労するでしょう。
早寝早起きを心がけ、朝食、昼食、夕食、おやつの時間など、時間を決めて、その時間に合わせて与えるようにします。
このようにすると、子供の中でスケジュールに沿って行動することが身につきますので、学校の規則正しさに息苦しさを感じません。
4)積み木やブロックで遊べる
積み木やブロックで遊ぶスキルはとても大切です。
何かを創造するだけに留まらず、手の動きや考える力など、さまざまな刺激を脳に与えます。
もし、子供のおもちゃのアイテムにこれがなければ、今すぐ取り入れてください。
幼稚園の試験があるところは、これで遊ぶ様子を観察することを取り入れている場合もあります。
5)少なくとも10まで数えられる
幼稚園に入園したばかりでは、10まで数えられない子供がいたり、逆にすでにもっと大きな数をすんなり数えられてしまう子とさまざまです。
しかし、幼稚園に入ると、小学校の準備として、基本的な数について少しずつ学習してゆきますので、今から少しでも、数になれるようにしてゆきましょう。
最初は10までを目標にして、それがクリアできたら、20、30と増やしてゆきます。
お風呂で一緒に数える練習をするのもいいでしょう。
カレンダーを使って、その日にあたる数にシールを貼っていったり、いろいろやり方を工夫して下さい。
6)あいさつが出来る
「こんにちわ」「さようなら」「ありがとう」など、基本的な挨拶を教えましょう。
集団の中にいると、特にこういった基本的な挨拶ができることがとても大切になります。
近所の人に会ったら、「こんにちわ」。公園から帰る時、友達に「さよなら」など、チャンスがあれば、親が促しながら、どの状況で言うのかを教えてください。
どの時代でも、挨拶が出来る子供はとても印象がいいものです。それには、親が率先して教えてあげましょう。
7)基本の色や形を覚えておくと便利
色なら、赤、青、黄色、白、黒など。形なら、丸、三角、四角など、基本的な色や形を教えておきましょう。
2歳の子供でも、おもちゃなどを使って、以外に簡単に覚えられます。
覚えてしまうと、子供は大変得意になりますので、生活の中で、時計や机などを使って、「形は何?」「色は?」と聞きながら、ゲームのようにやってみましょう。
幼稚園に入ってからも覚えられますが、その前に覚えておけば、子供に余裕ができます。
8)トイレに行ける
トイレトレーニングは、すでに出来ているのが望ましいでしょう。
また、トイレを使った後は、おろした下着やパンツなどをちゃんと元のように戻すことができるようにします。
トイレトレーニングが完了していることが条件のところもあれば、そうでない幼稚園もあるようです。
しかし、基本的には幼稚園に行く前に出来ていることが望ましく、子供も他のことに集中できます。
9)洋服の着脱ができる
冬などは、ジャケットを着たりしていますが、それを自分で脱いだり、着たり。
ジャケットなどを着た時に、ボタンやジッパーが閉められるか、子供にとって難関はありますが、何度もやっていると、ある時突然自分で出来るようになりますので、親が着せるのではなく、自分で出来るように見守りましょう。
10)靴がひとりで履ける
子供は、2歳くらいでも、靴を自分で履けるように指導すれば、すぐに履けるようになります。
最初は、右左逆に履いていたり、かかとの部分がなかなか入らない等ありますが、忍耐強く指導していると短期間で履けるようになります。
コツとして、簡単に履けそうな靴を選んであげるべきです。
いろいろなデコレーションがついていると、履きにくい靴もあります。
自分で履けたら、「よくできました」と言って、ほめてあげましょう。
11)指を使って10まで数えられる
数える際に、指を使って数え、それと数があっている練習をします。
毎日繰り返しましょう。 やり方は、イチと言って、人差し指を立てて、これを二つの手の指を使って、10まで数えてゆきます。
12)前、後ろ、側面、右、左
これはまだ出来ない子供もたくさんいると思いますが、幼稚園に入る前、入ってからも、少しずつやってみましょう。
これを絵本などを使ってやってみるといいでしょう。
絵本の前の表紙を指差して、ここは「前」、そして、ここは「後ろ」などといいながら、場所を認識できるようにします。
慣れてきたら、体全体を使って、右見て、左見て、などとゲーム感覚で試してみます。
[quads id=2]
13)困ったことがある時に説明ができる
例えば、「転んでしまったので、ひざが痛む」とか、「モノがなくなった」等、何か困ったことが起きた時に、先生にお話ができることは大切なことです。
学校にいる時に、何も言わないで、家に行ってから親が気がついて心配することがあります。
まだうまく説明できない場合もありますが、短く簡単に説明ができるように、コミュニケーション能力も養っておきましょう。
自分の子供を守る上でも大切なことです。
最初は、大人から質問をして、子供がイエス、ノーで答える形式で構いません。
「おなかすいた?」「どこが痛い?」「何がほしい? これ? あれ?」など、質問してゆきましょう。
それから、少しずつ子供が説明するチャンスを与えて、幼稚園前に、ある程度説明できるようにしてみましょう。
14)他の子供から嫌なことをされた時に「やめて」と言える
これもとても大切なことです。
幼稚園と言っても、さまざまな子供が集まってきています。
中には、どうしてもウマが合わない子供もいるかもしれません。
誰かに不愉快なことを言われたり、されたりした時に、はっきりと意思表示が出来ることは、たとえ幼稚園児であっても必要なスキルです。
そのスキルを身につけるには、まず家でママと練習をしてみましょう。
手のひらを相手にむけて、はっきりと「やめて」を言いましょう。
その場になると、最初のうちはうまく言えないかもしれませんが、少しずつスキルアップしてきます。
15)トイレに行った後に、自発的に手を洗うことが出来る
トイレ後に自動的に、手を洗うことが出来るようにならなければなりません。
この習慣があれば、さまざまなウイルスなどを少しでも防ぐこともできますので、とても重要な習慣です。
今のうちに、“トイレ後、必ず手を洗う”を強調しておきましょう。
16)箸やフォーク、スプーンが使える
幼稚園では、皆で集まって、テーブルの上で皆と食事を楽しむ時間があるでしょう。
もし、家でまだママが食べるのを手伝っているのでしたら、さっそく子供が自分でスプーンや箸を使って、食べられるように練習させましょう。
最初はテーブルの上が散らかってしまうこともありますが、気にせずに、食事ごとにさせます。
子供の好きな箸やスプーンなどを一緒に買いに行って、それらを使わせると効果的です。
17)5~10分間は座っていることが出来る
子供がじっとしている時間は長くありません。
よく言われているのが、子供の年齢と集中力の時間が比例するといわれていますが、幼稚園児(5歳児くらい)であれば、5分がせいぜいでしょう。しかし、訓練によって、もう少し長くすることもできます。
入園前に、家庭で「ストーリータイム」等を設けて、この状況に慣れるようにしましょう。
本を読みながら、子供にも参加させて、いろいろな質問をしながら読むと、子供も飽きないでいられるのと、さらに、さまざまな分野の能力も一緒についてきます。
18)お片づけが出来る
幼稚園でも、クラスの後に、例えば、クレヨンやおもちゃなどが出しっ放しになっていたら、片づけるように言われます。先生がすることではなく、生徒がするように仕向けられますので、後片付けの習慣も身に着けておくといいでしょう。
また、後片付けが出来る子供は、仕事の処理能力が高いのではないかと思います。
なぜなら、後片付けがよく出来る子はモノ覚えも早い傾向にあると感じているからです。
お片づけの歌を決めて、それを歌いながら、片付けるのもいいでしょう。
ぜひとも積極的にやってほしいと思います。
19)他の子供と道具やおもちゃなどを共有できる能力
2,3歳の子供ですと、どうしても自分のおもちゃなどに関して、テリトリーの意識が高く、貸すなどトンデモナイ!という行動を取ります。
幼稚園になってくると、一緒に他の子供たちとも遊べるようになっていますので、同じおもちゃで一緒に遊んだり、道具を共有したりできるようになってきます。
しかし、一人っ子だったり、その子の日々の経験によって、個人差もありますので、公園など、他の子供がいる場所に行って、一緒に遊ばせるようにして、幼稚園に備えましょう。
20)幼稚園に気分よく行けるように
毎朝ぐずったりして、機嫌が悪くなる子供もいます。
その場合、睡眠や食事と言った、生活でも基本的なことを一度振り返ってみてください。
特に、睡眠は、子供の1日を大きく左右します。3歳から5歳の学童期は、11~13時間の睡眠が必要とされています。
親と一緒に、遅くまで起きて、毎日十分睡眠を取れない子供は、十分な睡眠を取れるように取り計らってあげましょう。
眠りは、軽視できないほど大切で、学力や健康に大きな影響を及ぼします。
21)親と離れて、過ごすことができる
幼稚園にいる時間は、それほど長くありませんが、親と離れて過ごすのが初めての子供がほとんどです。
それに慣れるためには、時々友達の家に1時間くらいでも、預かってもらったり、習い事をさせて、その間だけ親がいない時間を作ったりして、慣れるように工夫してください。
そして、置いていく時に、「じゃあね。すぐ戻ってくるから。楽しんで」等、いつも明るく振舞いってから、その場を去りましょう。
22)先生の指示に従うことが出来る
幼稚園と言っても、そこには小学校に上がるために必要なことを教えてくれる先生がいて、数や書き方など、さまざまな学習をします。
教室では、先生の指示に従って、座ったり、移動したり、さまざまなことを行います。
その指示を聞いて、指示通りに行動することが出来る能力があることが望ましいのです。
幼稚園に上がる前に、これについてお話しておきましょう。
23)絵を見せて答える
幼稚園の中では、面接時に子供に絵を見せて、質問に答えさせることを行う学校があります。
例えば、絵を見せて、「うさぎさんは、どこにいるの?」「椅子に座っているのは、だーれ?」など、いくつか質問をしてきます。
普段から、こういった質問に答える能力を養ったおくと、面接のある幼稚園の試験に対応できます。
単純な絵を見せて、色、形、動物やモノなど、いろいろな角度から質問して、練習しましょう。
24)運動能力を養っておく
家の中では、なかなか運動能力はつきにくいですが、毎日のように公園などに出向き、ジャングルジムやブランコ、メリーゴーランド等、さまざまなツールを使って、子供の運動能力を高めましょう。
また、ボール遊びも大変よく、コーディネーション力を養います。
これらが身につくには、ママが積極的に子供に教えて、させることが大切です。
例えば、ジャングルジムですと、今日は一段昇って、すぐ降りたとしても、「やったね」と褒めてあげて、次の日は2段目とどんどん高く上らせるように、少しずつ、忍耐強く努力してください。
大切なのは、恐怖心を覚えさせるように無理をさせてはいけません。
25)ぬり絵をさせる
3歳くらいの年齢の子供は、まだぬる絵の対象にむけて、色を塗ることはできません。
どちらかと言えば、ぐちゃぐちゃに色をぬってしまうでしょう。
しかし、4、5歳になってくると、もう少し理解できてきて、少しずつ形になってきます。
ぬり絵は、色彩感覚を養ったり、脳を刺激しますので、最初はわけがわからない感じで色を塗っていても、少しずつ出来上がってきますので、普段から、雨の日に家にいたり、あるいはレストランにいる時など、ぬり絵ノートを持って行って、練習するようにしましょう。
26)歌いながら、手も使う
保育園や幼稚園では、手も使いながら、歌を歌って、何かを覚える方法がよく使われています。
今から、この方法にも慣れさせておきましょう。
小さな子供の脳に働きかけて、何かを覚えさせるために、大変有効な方法です。
「むすんで、ひらいて」「きらきら星」など、いろいろな歌がありますが、これは家庭でもできますので、ネットからいくつかピックアップして、今からでも始めてみてください。
子供は歌が大好きですので、無理のない学習方法にも適用できます。
歌を交えると、楽しく、簡単に覚えられますので、いろいろなものに活用してみて下さい。
27)ちゃんと話を聞く
大人は、何かをやりながらでも、耳を傾けることができますが、小さな子供は、ひとつしかできません。
もし、ママが子供に何か話しかけている時に、子供がおもちゃで遊んでいたら、話は聞いていません。
入園したら、先生の話をだまって聞く機会が増えます。また、幼稚園以降、この先、学校から社会人になっても、結婚しても、「聞く」という行為はとても重要なキーを秘めているのです。
話を聞かせる習慣をつけるには、本を読んであげるストーリータイムが有効です。
また、話をする際に、「聞いてくれる?」とひとコト言って、自分に注意を向けるように促すようにするのもいいでしょう。
28)ごみ箱にゴミを入れる
ティッシュを使って、鼻をかんだり、口を拭いたりした後、ゴミ箱に必ずいれるように教えてください。
決して、ママに渡して、それをママが処理することをしないようにします。
ゴミ→ゴミ箱、この流れをしっかりと頭に叩き込んでください。
幼稚園に行ったら、ゴミは自分で捨てるようにしましょう。
[quads id=3]
ママと少し練習するだけで、ひと味違う幼稚園ライフに!
ほとんどの子供は、幼稚園が最初の外の世界の入り口になります。
遊びや友達は、とても楽しみですが、学校ですから、ママやパパ以外の大人がいて、規則もありますので、子供ながらに、結構気力、体力を消耗します。
子供が少しでも、ラクに、楽しく過ごせるには、その前にいくつか家庭で出来ることもあります。
この中のすべてをマスターするのは大変かもしれませんが、いくつかでもやっておけば、入園前に、不安も少しなくなるでしょう。
入園前に準備したいこと
まとめ
幼稚園は、アカデミックなことの比重よりも、社会的なスキルを伸ばすことに重きを置く場合がほとんどです。
これから小学校、中学校、高校、大学、そして社会人という段階を順調に踏んでいくために、とても大切なひとコマですから、学校だけでなく、親からのサポートの、両方で連携を組んで出来るのが望ましいと思います。
幼稚園前のお子さんがいるお友達や親戚にもぜひシェアしてあげてください。またあなたもはてなブックマークなどで保存して、子供のためのチェック項目としてぜひご活用ください。
慣れてしまえばなんてことないことですから、一つずつ楽しみながら確実にクリアしていきましょう。
そして、一つ達成する度に、ちゃんと褒めてあげてくださいね!
FBアプリでしつけレベルを簡単に診断
褒め方についてはこちら
→間違えたら大変!子供の正しい褒め方15のコツ【完全保存版】
正しい褒め方をすることで褒められ上手の子供に育てるコツをまとめたので、できてるかどうか確認してみて下さい。
[quads id=5]
[quads id=6]

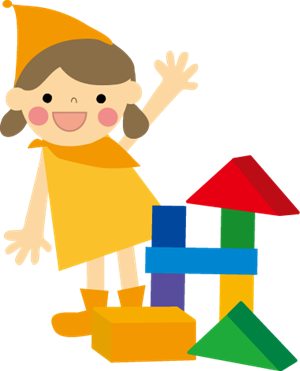


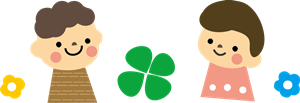




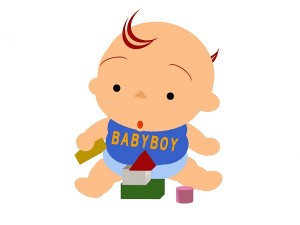




コメント
コメント一覧 (2件)
[…] →入園式前に教えたい、子供の幼稚園ライフが充実する28のしつけ【永久保存版】 […]
[…] →入園式前に教えたい、子供の幼稚園ライフが充実する28のしつけ【永久保存版】 […]