ひな祭りを彩るお祝いメニューと聞いてあなたは何を思い浮かべますか?
ひなあられ、ひしもち、甘酒。
はまぐりのお吸い物、チラシ寿司。
ん?チラシ寿司?
チラシ寿司を作りながらふと思ったことありませんか?
早春を感じさせる3月上旬、桃の節句をお祝いするためのメニューになぜ、チラシ寿司を食べるようになったのだろう?
その謎に迫るためにまず、ひな祭りの由来から触れていきましょう。
[quads id=1]
ひな祭りの由来
ひな祭りは女の子の成長の無事を祈りお祝いする節句ですが、元々を辿っていくと中国で行われていた「上巳節」に行き着きます。
「上巳節」とは、3月3日に川の水で自分の身を浄めることで、厄災や穢れを払うという中国の風習でした。
その風習が遣唐使によって日本に伝えられたのがひな祭りの由来と言われています。
そして、平安の世の貴族の子女の遊びだった人形遊びが「上巳節」と合わさり、現代の世まで伝えられているのがひな祭りです。
チラシ寿司の意味と由来は?
ひな祭りの定番メニューであるチラシ寿司。
寿司とはそもそも「寿を司る」という意味を持ち、お祝いの席で食べられる縁喜がいいものとされています。
平安時代に人形遊びが流行している頃、時を同じくして日本にお寿司の起源と言われている「なれ寿司」が食べられるようになりました。
このなれ寿司をお祝いの時に食べ始めたことが、現在のチラシ寿司に変わっていったと言われています。
チラシ寿司の具として挙げられる主な具材
- 海老…腰が曲がっている海老は長生きの象徴である
- れんこん…穴が開いているれんこんは先を見通せる
- 豆…いつまでも健康で、まめに働ける
と、やはり縁喜を担いだものが組み合わされています。
たくさんの具が混ざりあって作られるということにも意味があり、将来食べ物に困らないようにという願いも込められているのです。
そう考えるとお正月に食べるおせち料理も同じ縁喜を担いだものですよね。
節目、節目に縁喜を担ぐ。
日本人の細やかな気配りを垣間見た気がします。
我が子がいつまでも健康で幸せに暮らせるように、という切なる願いが、ひな祭りのお祝いにチラシ寿司を食べる習慣を根付かせたようです。
[quads id=2]
「はまぐり」や「ひしもち」はどんな意味?
チラシ寿司にも意味があるということは、他の食材にも何か意味がありそうですよね。
はまぐり
二枚貝になっているはまぐりは貝がぴったりと合わさることから、仲の良い夫婦の象徴として、一生、一人の人と添い遂げられますようにと願いが込められています。
ひしもち
ひしもちの色にもそれぞれ意味があります。
「緑」…長寿、健康を祈る、新緑
「白」…清浄、雪解け
「ピンク」…魔除け、桃の花
雪が溶け、新緑が芽吹く頃、桃の花が咲く。
春の訪れを喜ぶ風情が感じられます。
[quads id=3]
まとめ
きちんとひな祭りの由来を知り、お祝いの席で食べるものが持つ本来の意味を知ることで、ひな祭りがまた違ったものに見えてきますね。
こどもの成長を願い、ひな祭りをより身近に楽しむためにも、後世にひな祭りの意味をしっかり伝えていきたいものですね。
こどもを育てることで派生する親の役割は、先人の知恵を伝えるということも大きな役割だと思います。
[quads id=5]
[quads id=6]



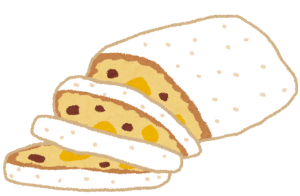

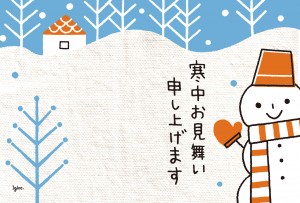

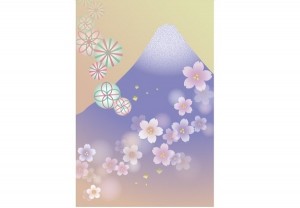

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] お祝いをする意味はこちらを参考にしてください。⇒ひな祭りの由来!チラシ寿司やはまぐりはなぜ食べるの? […]