雛人形を飾って女の子の健康と幸せをお祈りする雛祭りが終わったら、今度はお人形を片付けなければなりません。
雛人形を片付ける際にはどんなことに注意しなければならないのでしょうか。
片付けの時期や知っておくべき注意ポイントについて紹介していきます。
[quads id=1]
雛人形を片付ける時期
「雛人形を片付けるのが遅れると、お嫁に行けない」とよく言われたものです。
これは単に迷信なのですが、しっかりと片付けができないようでは、いいお嫁さんにはなれないという戒めがこめられています。
さて、その片付けの時期ですが、昔から「啓蟄の日」が最適であると言われています。
具体的な日付は3月6日頃のことをさします。
気温が上がってきて大地で冬眠していた虫たちが穴から出始める頃を言います。
3月6日頃の晴天の日に雛人形の片付けをするのがベストですね。
天気も気にしよう
雛人形を片付ける日は晴天の日を選ぶようにしましょう。
なぜ晴れているときが良いのかというと、湿気が少ないからです。
雨天のときはどうしても湿度が高くなり、じめじめとしてしまいます。
この湿度は雛人形には大敵であり、人形や人形の着物に湿気を残したまま片付けてしまうと、シミやカビの原因になってしまいますので、注意しなければいけません。
[quads id=2]
片付ける時の注意点
箱に仕舞うときには、人形用の防虫剤を使い、虫がつかないようにすることも大切です。
保管場所についても気をつけなくてはいけないことがあります。
雛人形は湿気を嫌いますので、お風呂や台所の近くに保管しておくことは避けましょう。
また乾燥のしすぎも、人形にひびが入ってしまうこともあり、注意しなければいけません。
直射日光が当たるなど、高熱になってしまうような場所も避けましょう。
雛人形を片付ける前にはお供えをする?
以前は、雛人形を片付ける前に、おそばを供えてから仕舞う風習がありました。
「雛そば」とか「節句そば」と呼ばれていました。
なぜそばなのかと言うと、そばは少しの粉で細く長く伸びるので、家の繁栄も細く長く続くようにとの意味を込めていたのですね。
江戸時代に、雛人形とお別れするための儀式として行なわれていた風習ですが、今では知っている人も少なくなってきました。
雛人形を飾っている間は、ひなあられや白酒、桜餅などをお供えしている家庭も多いことでしょう。
しかし、1ヶ月弱の間お世話になった雛人形、また一年間お別れする前の儀式として、おそばをお供えして、いっしょにいただいた後に片付けるというのは、なかなか素敵な風習ですね。
[quads id=3]
まとめ
いかがだったでしょうか。
ただ片付けるだけではなく、注意点や風習を知って片付けるとより人形への愛着も湧いてきますね。
雛人形を片付けるときには、また一年後にお会いしましょうという願いをこめて、いつまでも綺麗な状態を保つことが出来るように、注意しながら片付けたいものです。
[quads id=5]
[quads id=6]



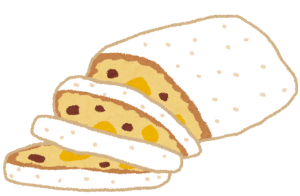

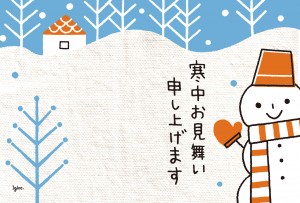

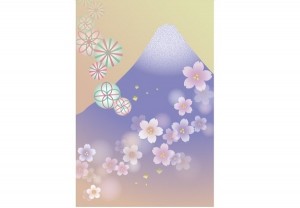

コメント