四十九日の後に初めて迎える盆供養、新盆に招かれた時に、恥をかかない挨拶のマナーがあります。
故人が亡くなってから慌ただしく通夜、葬式、四十九日と法要が続きますが、いざ招かれた時の挨拶って何て言ったらいいのか迷いますよね。
「おはようございます」「こんにちは」だけってわけにもいかないだろうし、「お悔やみ申し上げます」じゃお葬式…?
訪問した時の挨拶マナーと、のし袋と表書きについても、一緒に確認していきましょう。
[quads id=1]
新盆見舞いにふさわしい挨拶のマナーは?

四十九日が終わって仏様になった故人が初めて家に帰ってくるのが新盆です。
挨拶は湿っぽくなる必要はありません。故人と親交があった場合は、思い出話をたくさん話したり、聞くことがマナーのようなものです。
とはいえ、第一声の挨拶は、なんて声をかけるのがふさわしいのか悩むところです。
参加する立場別に、挨拶を紹介しますね。
新盆に招かれた場合(挨拶をする側)
持参した香典を施主に渡す時が、最初に挨拶をするシチュエーションです。
最初の挨拶のポイントは、招待して頂いたことへの感謝です。香典をパートナーが渡した場合などにも感謝の挨拶から入るとスムーズですね。
「本日はお招きいただきありがとうございます。」というのは、万能の挨拶言葉なんですね。施主の家族の方に挨拶する時も何回も使えます。
[quads id=2]
施主に近い親族として招かれた場合
施主に近い親族として参加する場合は、施主(嫁ぎ先の両親など)にお手伝いを申し出るとよいですね。
施主の家族も慣れない対応でバタバタしているでしょうから、このような気遣いは心から感謝されるはずです。
新盆施主の直系親族だった場合(挨拶を受ける側)
例えば、ご実家の祖父母や両親、嫁ぎ先の両親が施主になった場合は、招かれた親戚やご近所、仕事関係の方から挨拶を受ける立場になります。
そうなった場合も気の利いた挨拶を返したいですよね。
受ける側の挨拶も感謝から入ると印象がよいですね。足を運んで頂いたことへの感謝を言葉に出して伝えましょう。
規模が大きい盆供養祭をする場合は受付を頼まれることもありますから、スマートに挨拶したいですね。
[quads id=3]
まとめ
20代中盤以降になると、新盆見舞いなどの法要に、きちんと大人として参加する機会が誰しも出てきますね。
結婚したパートナーの家の法事だと粗相しないように…と緊張しがちですが、夫婦のイベントの一つだと思ってみるのもいいですね。
相手の親戚のことや育った環境のことを知るいい機会でもあります。
そんな時に、「お招きいただきありがとうございます」「何かお手伝いすることがあればおっしゃって下さい」が口からサッと出てくれば、緊張する法事もスムーズに乗り切れますよ。
頭で理解するだけでなく、口に出して何度か練習していくと、自然な感じで挨拶できます。
今回ご紹介した、万能の挨拶言葉を、ぜひ声に出して覚えてしまいましょう!
表書きの書き方のルールもチェック!
のし袋の表書きで恥をかかないために、一般的なルールを押さえておきたいですね。事前に目を通しておくだけで恥をかかずに済みますよ!
[quads id=5]
[quads id=6]



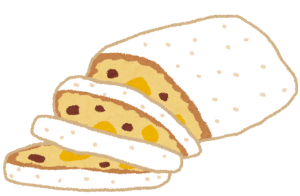

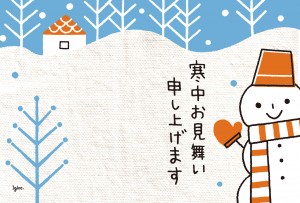

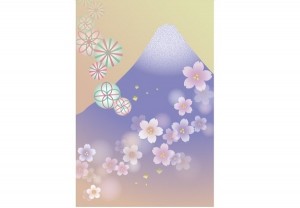

コメント