年賀状をどこまで出すべきか、喪中の場合は悩みますよね?
それに喪中の期間は、お父さんとおじいちゃんとでは違うなど、ややこしく感じられる方が多いです。
でも、年賀状を出すときに必要な、喪中のルールだけ確認すればOKですよ。
忙しい時期ですから、年賀状の準備は手際よく進めていきましょうね!
[quads id=1]
年賀状の準備の前に、喪中の範囲がどこまでかチェック!

一般的には、本人からみた2親等までは喪中の範囲で、3親等からは同居していなければ喪中としないケースが多いです。
《参考までに》
・0親等 夫・妻
・1親等 父母・配偶者の父母・子ども
・2親等 (自分の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母、孫
(配偶者の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母
・3親等 (自分の)曾祖父母、伯叔父母、伯叔父母の配偶者、甥、姪
(配偶者の)曾祖父母、伯叔父母、伯叔父母の配偶者
ただし、あくまでも一般的な範囲ですので、宗教やそれぞれの状況で判断しましょう。
また、近年は核家族が増えていることもあり、離れて暮らしている場合はそこまでこだわらないケースもあります。
○喪中の期間は、父と祖父で違うの?
喪中に関する取り決めには、明治時代に定められた太政官布告があります。
これは昭和22年に撤廃されていますが、現在の喪中の基準になっています。
《参考までに》
・父母、義父母 12~13ヶ月
・子ども 3ヶ月~12ヶ月
・祖父母 3ヶ月~6ヶ月
・兄弟姉妹 30日~6ヶ月
・曾祖父母 伯叔父母 喪中としない
このように亡くなった方との関係によって、喪中の期間は異なります。
ここも、期間に幅があるのはそれぞれの状況、故人との関係で判断するからです。
服喪期間中に新年を迎える場合は、喪中欠礼の挨拶状を出しましょう。
○喪中はがきを出す範囲は?
毎年、年賀状のやり取りをしている人(友人、同僚、上司、先生など)が喪中はがきを送る範囲です。
喪主の場合には、故人が年賀状をやりとりしていた、友人、葬儀に参列してくださった相手(仕事・ビジネス上の取引の方も含む)となります。
[quads id=2]
喪中はがきを出す時期

喪中はがきは送る時期は、早ければ早い方がいいというわけではありません。
12月上旬~中旬に届くのが、ちょうどいい時期と覚えておきましょう。
12月上旬は、「年賀状をそろそろ書かなきゃ」と、年賀状を意識する季節ですからね。
でも、早すぎると相手も忙しくて忘れてしまうかもしれません。
なので、遅くても12月上旬~中旬がベストの時期になります。
○喪中に年賀状が届いたら?
松が明けたら(一般的に1月7日過ぎ)、寒中見舞いや挨拶状として、普通のはがきに切手で送ります。
その際、年賀状に対するお礼と、故人を明らかにしたうえで喪中であったことを記載しましょう。
日付は投函日を入れ、「賀」などのめでたい文字の使用は避けた方が安心です。
○故人宛てに年賀状が届いたら?

この時も同様で、松が明けたら寒中見舞いや挨拶状として送りましょう。
そんな時は、以下のような内容を案内状のはがきに書いておくと安心です。
《参考までに》
・季節の挨拶
・年賀状のお礼
・本人が亡くなっていること
・知らせできなかったお詫び
・お付き合いのお礼
・遺族(差出人)の名前
[quads id=3]
まとめ
家族が亡くなった時は、気持ちが落ち込むだけでなく、普段と違うことが多いので一層くたびれますよね。
また、あなたやパートナー(夫・嫁)の親戚に不幸があった場合も、どうすればいいのか判断に迷うことが多いでしょう。
ですが、亡くなった方が、あなたやパートナーにとってどういう関係だったのか、そこから整理して考えていけば、することは意外とシンプルですよね。
年末が近づいてくるにつれて忙しくなってきますので、早めに整理していきましょうね!
Q.喪中の範囲は?
一般的には、本人からみた2親等までは喪中の範囲で、3親等からは同居していなければ喪中としないケースが多い。
Q.喪中の期間は?
亡くなった方との関係によって、喪中の期間は異なります。
・父母、義父母(12~13ヶ月)・子ども(3ヶ月~12ヶ月)・祖父母(3ヶ月~6ヶ月)
・兄弟姉妹(30日~6ヶ月)・曾祖父母 伯叔父母(喪中としない)
Q.喪中はがきを出す時期は?
一般的には送る時期は早ければ早い方が良いのではなく、12月中旬までに届くように手配し、誰が亡くなったのかを明記しましょう。
Q.喪中はがきを出す範囲は?
毎年、年賀状のやり取りをしている人(友人、同僚、上司、先生など)が喪中範囲です。
Q.もし、喪中に年賀状が届いたら?どう返す?
松が明けたら(一般的に1月7日過ぎ)、寒中見舞いや挨拶状として、普通のはがきに切手で送ります。
[quads id=5]
[quads id=6]



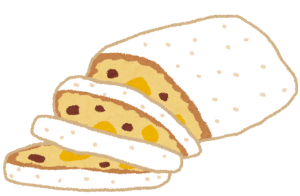

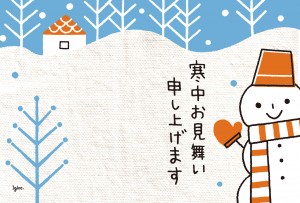

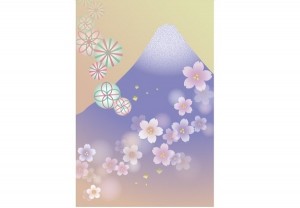

コメント