子供が幼稚園や小学校に通い出すと、親としての心配はつきないですよね。
だからといって、過保護になってしまっては、子供にとっても決してプラスではありませんよ。
過保護な親の特徴や過保護な親が子供に与える影響をご紹介しますので、自分でチェックしてみて下さい。
また、過保護を回避する方法もぜひ参考にして頂きたいと思います。
[quads id=1]
過保護な親の5つの特徴とは?
過保護な親には、行動の特徴が5つあります。
・子供を人一倍、心配する
・子供がやるべきことも率先して手伝ってしまう
・子供が望むものは全て買い与える
・子供の交友関係に口出しをする
・子供に自由を与えない
子供を持つ親なら、ついついしてしまいがちな行動もありますよね。
特に私も親として、よく反省しているのが「◯◯やったら?」という口癖です。
「宿題やったら?」
「片付けやったら?」
親からすると子供のことを心配しての一言ですが、子供の自主性は育ちにくくなってしまいます。
つまり、なぜ○○をした方が良いのか、子ども自身に考える力を身につけさせないと自立心が養われないのです。
○親子の関係が変化している

ところで、30年前と比べると、困ったときにお母さんに相談する小中学生が、激増しています。
お母さんに相談する小中学生の割合
・30年前・・・20%
・現在・・・・38%
さらに、反抗期がない子どもが激増しているというデータもあります。
親子の関係がよくなっているとも言えますが、子供の自立が遅れているという見方もできるのです。
過保護とは、子供に対する愛情があふれているがゆえの行動ですが、親からの一方的な愛情になっていないかを考える必要もあります。
子どもの健全な成長を妨げてしまうのでは、本末転倒ですからね。
過干渉になっていないかをチェック!
過保護よりもさらに問題なのは、過干渉です。
・過保護…子供が望むことに応えすぎてしまうこと
・過干渉…子供が望んでいないのにやりすぎてしまうこと
子供への愛情が親の思い込みになってしまうと、過干渉になってしまいます。
子供だって一人の人間ですから、親が望むように育つわけではありません。
日頃から親子のコミュニケーションを大事にして、子供の気持ちを確認しておくことが大切です。
「子供のためだから」と思っての行動が、それが子供にとってマイナスになるなんてことになったら、ショックですからね。
◯過干渉な親に育てられた子供はどうなる?

過干渉な親に育てられた子供にも、特徴があるので見ていきましょう。
・積極性がない
・なかなか自分自身に自信が持てない
・我慢ができない
・自分で解決する力が育たない
自分で何かを見たり、聞いたりしても自分自身が感じたことをうまく表現できなかったり、親が良いと思うもの=良いものと思い込んだりします。
また、誰かと違うことに違和感を感じたり、不安を覚えたり、自分らしく生きることにストレスを感じる場合もあります。
つまり、精神的に自立することができなくなってしまうのですね。
○こんな子どもに育っていいの?
私が小学生だった頃、かなり過保護なお母さんを持つ同級生が居ました。
朝、着る洋服や髪を結わえるゴムの色まで、なんでもお母さんの言う通りでした。
そして、その子の口癖は
「お母さんに聞いてみないとわからない」
「自分では決められない」
でした。
このように、自分で何かを決めることにすら不安を覚える子供に育ってほしい、と思う親はきっといないと思います。
その同級生の親だって、決してそんな思いで育てたわけではないはずです。
[quads id=2]
では、子供にすべきこととは?
子供がしてもらって嬉しいこととは一体なんなのか、を知る必要があります。
親が知らず知らずの内に、過保護になってしまい、子供の気持ちが見えなくなってしまった実話を紹介しますね。
これはある小学校での話です。
子供同士で喧嘩をした時に、お母さんが自分の子供にこのように言いました。
「あなたは悪くないんだから謝らなくていいのよ。」
これを聞いた時、その子はとっても悲しい気持ちになったそうです。
理由は、「お母さんは、自分の子供だからという理由だけで、悪くないと思い込んでいて、自分という人間を見てもらえてないと感じたからだ」と言っていました。
親の思い込みの愛情は、目を曇らせてしまうので、本当に怖いですよね。
子供は親に、自分という人間を認めて欲しいんです。
○人間と人間のコミュニケーションが大切
子供が思うこと、感じていることをしっかり受け止めながら、コミュニケーションをとることを心がけましょう。
正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると毅然とした態度でいることも大切です。
血がつながった親子であっても、別の感情を持った別の人間ですから、1つ1つ信頼関係を築いていくことが大切です。
過保護を回避するための心がけ

大事な子どもだからこそ、痛い思いはして欲しくないと思いがちですよね。でも、そんな思いが過保護につながることも多いのです。
経験から学ぶことが、一番の成長の糧になると捉えることが大切です。
そして、失敗から立ち上がるときに必要なサポートをしてあげるのがいいですね。
○小学校3,4年生は、自我が芽生える時期と知る
成長に合わせて教育方針を切り替えていく必要があります。
一つの大事なきっかけは、小学校3,4年生の自我が芽生える時期です。つまり、反抗期の始まりの時期になります。
この時期は、子ども自立していくので、あなたから離れていく寂しさもあるかもしれません。
でも、親が子離れできないことが原因で、子どもの自立心を奪ってしまっては、子どもにとって決してプラスにはならないと思います。
[quads id=3]
まとめ
子育てには万人向けの正解がないから難しいですよね。
ですから、ちょっと違うかもしれないなと思った時は、振り返ることが大切です。そして、自分の素直な気持ちや子供の気持ちを確認するようにしましょう。
「自分は間違ってない!」と思い込んでしまうと、間違いを認めることすらできなくなってしまいますよ。
もし、過ちに気付いた時には「ごめんね。」と言えば済むのが、親子です。
もちろん、「過保護かもしれないな?」と気にした時点で、そんな思い込みはないわけですから、そんなあなたは深刻に考える必要はないでしょう。
これからも、素直な気持ちで子供とコミュニケーションを取り、子供が少しずつ自分で考える力を身につけられるよう、心強いサポートをしてあげてくださいね。
正しい褒め方、できてますか?
かわいい子供を褒める時のルールを知っていますか?間違った褒め方をしてしまうと逆効果ということもありますよ。
しつけ方にもコツがある!
→入園式前に教えたい、子供の幼稚園ライフが充実する28のしつけ
子供と遊んでコミュニケーションを取ろう!
→子供の集中力に親が与える影響とは!幼児期に大切なことって何?
子供の集中力を高めてあげるには、子供といっしょに●●をすればいいんです。
お金教育もコミュニケーションがポイント
お金の教育を上手にできている家庭は、意外と少ないようです。お金を通して子供に考える力を付けさせることがポイントです。
[quads id=5]
[quads id=6]




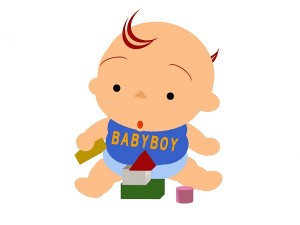




コメント