子育て中は、子供の成長は嬉しい反面不安もいっぱい、自我が芽生え、性格が表れてくると、手を焼きます。
「もしかして多動症かも・・・」
と心配に思ったりすることもあるかもしれません。
他の赤ちゃんとつい比べたくなりますが、まずは自分に赤ちゃんの様子をきちんと見てみることから始めてみましょう。
また、多動症には、まだまだ知られていないことや、誤解されていることが多いようです。
今回は、多動症を正しく理解するために、その特徴についてまとめました。
[quads id=1]
多動症の赤ちゃんの3つの特徴

脳は、周りの刺激によって働き方は変わるので、環境が変わると、多動症の症状にも違いが出てきます。
多動症の特徴は
- 不注意
- 多動性
- 衝動性
の3つに分けられます。
それぞれどんな行動をとってしまうのか見ていきましょう。
[quads id=2]
1)不注意性
不注意性の行動パターンは注意力がなく、長く集中できないことです。
物音がしたら、すぐにそちらに意識が行ってしまいます。
また、指示に従えず、物事が完成しなかったり、努力が必要な課題を避ける傾向があります。
物をすぐに無くしたり、順序よく行動するのも苦手です。
2)多動性
多動性の特徴は、とにかくじっとして留まることができません。
寝ている間中、体を動かしたり、足や手をいつもバタバタさせたりします。
また、順番を待ったり、じっと座って話を聞いたりすることもできません。
3)衝動性
衝動性では、突発的に行動したり、感情のコントロールが出来ないという特徴があります。
自分の好きなものがあると、すぐにそちらに興味を持ち、欲しがるのは、赤ちゃんの全般に言えることです。
ですが、多動症の赤ちゃんは、それが手に入らないと、奇声を発したり、すぐに手を出したりしてしまいます。
また、少し大きくなって順番が待てず行動してしまったり(割り込むなど)、刺激にすぐ反応する傾向があります。
行動のチェックポイント

多動症の特徴を見ていると、赤ちゃんにありがちな行動が多いと思いませんか?
特徴だけで、判断するのは意外と難しいので、次のような行動が無いかチェックすると、分かりやすいですよ。
- 母乳やミルクをあげているときも視線が合わない
- 抱っこを嫌がる、抱っこすると反り返る
- 指さしをしない
- 寝つきが悪く、2〜3時間ですぐ目を覚ます
- 癇癪が異常にひどい
- クレーン現象がある
これらの行動は、3か月未満の赤ちゃんでは判断はできません。
生後10か月以上たった赤ちゃんでもこのような行動がある場合は、多動症かもしれません。
また、クレーン現象というのは、赤ちゃんが他人の手を使ってものを取ってもらったり、要求を満たそうとする行動のことです。
1歳を超えると、指さしをする赤ちゃんが増えますが、2歳になっても指さしをせず、クレーン現象が見られるなら、多動症の疑いがあります。
子育て支援センターや保健センターなどで相談できるので、一度利用してみてくださいね。
[quads id=3]
そもそも多動症の原因は?

多動症は、正式名称を「注意欠陥多動性障害(ADHD)」という子供に見られる発達障害の一つです。
赤ちゃんの頃に見られる多動症は、成長するにつれ、軽くなっていきます。
昔から、多動症の人はいましたが、障害として認知されず、「変わっている」「落ち着きがない」として、誤解されていました。
海外では90年代ごろに認知され始めましたが、日本ではまだまだ知られていません。
知られていないのに関わらず、発症率は100人に3〜7人もいて、1クラスに1人は多動症である計算になります。
◯脳の先天性異常が原因
よく「親のしつけ、教育が悪いから落ち着きがないんだ」という人がいますが、そんなことを言われると、お母さんは気に病みますよね。
多動症の原因は親のしつけではありません。
原因ははっきりと解明されていませんが、
- 脳の前頭葉
- 大脳基底核が小さい
- 前頭葉の動きが悪い
- ドーパミンの働きが偏る
と多動症の症状が出ることが分かっています。
また、遺伝も関係することがあるため、親が多動症の傾向があると、赤ちゃんも多動症になる可能性があります。
多動症の赤ちゃんとどう付き合うか

自分の赤ちゃんが多動症だと分かったら、どう付き合うか困惑してしまいますよね。
多動症の対処法としては、薬による治療、環境への対処、行動への対処などがあります。
まだ、小さいうちは薬による治療が困難な場合もあります。
親ができることは、まず、行動自体を理解してあげることです。
特別なことをする必要はありません。
ポイントは2つ
- ルールが守ることができた、きちんと行動できたらしっかり褒める
- 間違っても無駄に叱らない
この2つを心がけて接すると、自分が認められることで心が安定していき、成長するにつれて症状が治まるケースが多くあります。
願うように行動してくれないので、イライラすることもきっとありますよね。
でも、赤ちゃんも自分をコントロールできない状態なので、理解してあげてくださいね。
まとめ

多動症に対する理解は昔に比べて、ずいぶん増えました。
しかし、今でも誤解や偏見から「変わった子」と思われることもあり、親や赤ちゃんも傷つくことが少なくありません。
多動症の赤ちゃんを育てていくには、親の理解と周囲の理解が必要です。
赤ちゃんには、それぞれ個性や、能力があり、それは多動症あっても同じです。
まずは、できないところも個性として接することで、隠れた才能が開花するのではないでしょうか。
○クレーン現象についてもっと詳しく
→クレーン現象は健常児でも見られる?1歳~2歳なら心配ない?
クレーン現象についても、正しい知識を持っていないと、ついつい不安になりがちです。
健常児と自閉症の子供の違いについて、しっかりと理解してください。
[quads id=5]
[quads id=6]



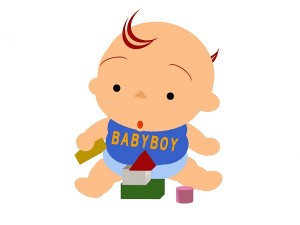





コメント