暑中見舞いに比べるとちょっとマイナーですが、冬には寒中見舞いという季節の便り・挨拶があります。
年賀状と重なるので、「時期はいつなのか」「特別なマナーはあるのか」などが気になりますよね。
年賀状で挨拶を済ませる人がほとんどなので、書かないことも多いですしね。
今回は、寒中見舞いを出す時に気をつけたい、時期や書き方のマナーを紹介していきます。
[quads id=1]
寒中見舞いを出す時期はいつ!?

1月8日から2月4日頃までに、相手に届く季節の挨拶のことを寒中見舞いといいます。
松の内が明けてから立春(2月4日頃)までの期間ということです。
相手に届く期間を考えれば1月6日、7日以降に出せばよさそうですね。
年賀状の返信が遅れてしまった時など、1月7日より後になってしまいそうなら年賀状ではなく、寒中見舞いとして出すのが正式なマナーです。
ちなみに立春の後になってしまったら「余寒見舞い」となります。
この辺は暑中見舞いと残暑見舞いと同じ感覚ですね。
寒中見舞いを書くときのマナー
・期限を守る
・年賀ハガキを使わない
・頭語と結語は不要
・相手の状況(喪中など)を考慮した言葉を選ぶ
寒中見舞いを書くときは先に紹介した時期を外さないように気をつけましょうね。
また、例え年賀の挨拶だとしても年賀状の使用は避けましょう。
仲の良いお友達などならご愛敬~となりますが、寒中見舞い用にハガキを新しく用意するのが正式なマナーです。
○避けたい言葉もある?
寒中見舞いは相手が喪中の場合にも使います。
喪中の相手の場合は、忌み言葉やおめでたいとされる言葉は使わないようにします。
・重ね言葉(忌み言葉)
「くれぐれ」「返す返す」「たびたび」「いよいよ」「重ねる」など
・おめでたい言葉
「あけましておめでとうございます」「謹賀新年」「謹んで初春のお慶びを申し上げます」など
寒中見舞いを書くのはどんな時?
こんな時には寒中見舞いの出番です。
・年末にいただいたお歳暮のお礼状をまだ出していない時(お礼状)
・年賀状の返信が遅れた時(年賀状の代わり)
・自分や相手が喪中の場合(年賀状の代わり)
・喪中の相手に年賀状を送ってしまった時(お詫び)
紹介したマナーを守って、季節の挨拶をして親交を温めましょう(^-^)
◯寒中見舞いに家族写真はあり!?
寒中見舞いのプリントで検索すると、写真付きプリントの広告がでてくるんです!
個人的にはちょっとびっくりしたのですが、こういう考え方ならマナーに反することもないのではないかなぁという基準を紹介します。
◯喪中が関係ない場合は写真付きもOK!
相手も自分も喪中ではなく、単に年賀状を出しそびれてしまった場合は家族写真付きでも問題ないでしょう。
相手や自分が喪中の場合は、写真を避けるのが無難です。
子どもが小さかったり、赤ちゃんが生まれたり、写真で子どもの成長を知らせたい場合も、喪中であることを考慮して我慢しましょう。
仲の良い友達にだけは、写真シールを貼って出したという人もいるみたいです。
個別に対応すれば非常識と思われることは避けられそうですね。
寒中見舞いの書き方

寒中見舞いはこの順番で書くとスムーズにつなげていけます。
段落ごとに1文字下げて書くようにしましょう。
① 「寒中お見舞い申し上げます」
冒頭に少し大きめに書く
② 時候の挨拶
ハガキでスペース節約したい場合は省略もできます
③ 本題
年賀状やお歳暮のお礼、喪中欠礼した年始挨拶などなど
④ 近況報告
省略もできます。
⑤ 時候の挨拶(結び)
相手の体調を気遣う言葉を使うといいです。
⑥ 日付
平成○年△月□日または平成○年△月
印刷で用意する場合は△月までの日付が使いやすいですね。
年賀状などと同じく、印刷の場合はそれぞれ相手に向けた直筆の一言を添えるといいですよ。
[quads id=3]
まとめ
喪中に関連して出す機会が多いのが、寒中見舞いになります。
暑中見舞いと違って、年賀状の時期と重なるので、出す機会が少なくないですよね。
年賀状と同じく、相手の状況(喪中かどうか)でふさわしくない言葉もありますので注意が必要です。
寒中見舞いはいつからいつまでの時期に出すべきなのか、守るべきマナーはどんなものがあるか、おさらいしてくださいね。
1月中旬の時候の挨拶
→1月中旬の時候の挨拶に使いたい言葉は?寒中見舞いに使える例文も!
1月下旬の時候の挨拶
→時候の挨拶を1月下旬に使うには?まずは季節の言葉をチェック!
書き出しや締めのあいさつでは、季節感を表すことで親しみがこもる寒中見舞いになります。
あなたらしい時候の挨拶の書き方を、参考にしてくださいね。
[quads id=5]
[quads id=6]



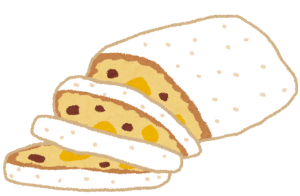


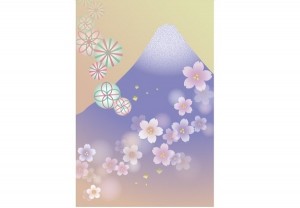


コメント
コメント一覧 (2件)
[…] →寒中見舞いの時期はいつ?マナーを大切にしたいですね! […]
[…] →寒中見舞いの時期はいつ?マナーを大切にしたいですね! […]