日本では、子供にお金の教育をしっかりできている親は、意外と少ないものです。
でもお金は生きていくうえでとても大事なものですから、自分の子供には正しいお金の価値観を学ばせたい、と思いますよね。
日常生活の中で自然な形で金銭感覚を身につけるには、タイミングを見ながら教育するのがコツです。
今回は年代別に分けて学びたいポイントやできることをご紹介します。
また、お金とは何かの根本を見失わないように、まずは親から正しい認識を持つようにしましょう。
[quads id=1]
子供のお金教育は、人生観を左右する
現代の日本ではあらゆる面で「自己責任」を問われますよね。それは何も仕事だけでなく、金銭、つまりお金の面でも同じですが、学習する場がないのが現状です。
お金は将来設計をするときに必要不可欠ですし、お金についての考え方は人生観に大きく影響します。
先々に困ることがないように小さな内からお金の教育を行い、金銭感覚を身につけさせる方が、子供の人生にとってはメリットが大きいです。
ぜひ子供のためにお金のことを正しく教育するようにしましょうね。
年代別のお金教育のポイント
4~6歳
買い物ごっこなどを通してお金の役割を学びます。
【この時期に学びたいこと】
・お金で物が買える
・お金は貯めることができる
・お金で物の価値を測ることができる
【学びのアドバイス】
・お金は使えばなくなる。
・我慢してお金を貯めることで欲しいものが手に入る
4歳ぐらいじゃまだ早い!と思われる方もいるでしょうが、お金で物が買えることを認識したら、自分用の財布に少額のお金を入れて持たせることも始めてみましょう。
お金教育は4歳からと言われているのもお金を認識することで欲しいと言えば買ってもらえると思わないようにするためです。
値段を口に出す
そして、実際に買い物に行く時でもお母さんが買いたいものをカゴに入れるだけでなく、値段を口にしてみましょう。
「このお豆腐は88円だけど、こっちは198円だね。」「イチゴはとちおとめが398円で、あまおうは598円だね」
など数字を口にすることでどういうものがいくらぐらいするか、同じ商品でもいくつかの値段があることなどが分かりますね。
買えるものと買えないものを理解させる
自分の財布の中のお金で買えるもの、買えないものがあることを知るチャンスを沢山作ってみましょう。
また、家で買い物ごっこをする時も「ジュースください」「250円です」「今日はバナナジュースだけ150円ですよー」などとやりとりすることもお金教育の1つです。
コミュニケーションを取りながら正しい価値観を持たせることを、徐々に生活に取り入れましょう!
小学1~2年生
字を書くこと、計算することに慣れてくる小学低学年の頃には、お金で買える物を選ぶということを学びます。
【この時期に学びたいこと】
・おこづかい帳をつける。
・労働をして対価を貰うということを伝える、体感させる。
【学びのアドバイス】
・実際におこづかいを渡す。
・おこづかい帳をつけてみる。
・お父さんやお母さんが仕事をすることで報酬をもらうことを教える。
例えば小学1年生には、毎月300円のおこづかいを渡してみましょう。
その中からやりくりさせるのですが、渡し方にもポイントがあります。
小銭を渡す
100円玉を3枚渡すのではなく、なるべく細かく渡すということが大切です。
全て1円玉で…というわけではなく、300円でも100円玉1枚、50円玉2枚、10円玉8枚、5円玉2枚、1円玉10枚など、なるべく多くの小銭を渡すことが大切です。
たくさんの小銭を渡すことで本人がお金を持っているという満足感を得ることだけでなく、それぞれのお金を使う意味、そして買い物をする時の細かな計算をすることにも役立ちます。
おこづかい帳を付けさせる
自分が何に何円使ったかということをおこづかい帳に記入していきます。
月初にお金を使いきってしまうと、月末には何も買えなくなるということを学ぶと、計画性を持つきっかけにもなります。
労働をして対価を貰うということを伝える、体感させる
お金が無尽蔵にあるわけではないということを子供に実感してもらいます。お金は労働をした対価としてもらうことができるということを、覚えさせます。
お手伝いをしたらいくらと設定して、お金についての価値を感じてもらうようにするとよいですね。
[quads id=2]
小学3~4年生
おこづかい制やおこづかい帳に慣れた小学中学年の時期は、次なる段階のお金の仕組みを学ぶチャンスです。
【この時期に学びたいこと】
・貯金の仕組みを知る
・おこづかいを計画的に使うことを学ぶ
【学びのアドバイス】
・親が子供用に持っている口座とは別に子供名義の口座を開き、自分のおこづかいの中から貯金を始めて見る。
・欲しい物を買うための計画をたてる。
例えば3年生には500円のおこづかいを渡してみましょう。
500円の中から200円ずつ貯める、もしくは300円ずつ貯めるなどの計画を立てて、欲しいゲームソフトや本を買う喜びを知ることを体験させましょう。
また、500円のおこづかいの中で月末に余ったお金を貯金することも勧めてみましょう。そうすることで貯金の喜びを知り、体感することができます。
お金は使えばなくなる、貯めると賢く買い物ができるなどお金の使い方が身につくことでしっかりとした計画性も身に付けられます。
小学5~6年生
お金を使う、貯めるが身についた小学高学年では、更なる計画性を持つことを学びます。
【この時期に学びたいこと】
・リサイクルでの売買
・ほしい物の優先順位を付け、計画的にお金を貯める
【学びのアドバイス】
・欲しいものリストを作る
・いらなくなった古本やおもちゃをリサイクルショップに売ってみる
年齢を重ねると欲しい物も増えてきます。友達との付き合いや欲しいものが高額になるなど、計画が長期に渡ることもあります。
そんな時に欲しいものリストを作ることで物の優先順位を決めて、決められたおこづかいの額の中でやりくりしていくことを実践していきます。
また、いらなくなったものを捨てるのではなく、読まなくなった本は中古品としてリサイクルさせる、使わなくなったおもちゃなども綺麗に保管しておけば高く売れるなどを体験する機会を設けましょう。
金銭感覚を養うだけでなく、物に対する大切さも変わって来るはずです。
お金教育の根本を見失わないように!
お金についての感覚を身につけるのは、子供にとっても大事なことです。ですが、損得勘定に偏った意識になってしまうのは考え物ですよね。
ですから、子供のころはお金については教育しなくてもいいと言われてきたのだと思います。
その偏りを防ぐためには、お金の使い方や貯め方を教えるときに、お金の正しい考え方をセットにして教えてあげましょう。
お金はなんのために使うのかといえば、人生を豊かにし、自分も周囲も幸せにするために使うものですよね。
何かやりたい目的があって、そのために必要なのがお金ですから、どんな夢を持つのかということが根本にあるはずです。
そのことを見失ってしまうと、お金を正しく使うことができるはずがありませんよね。
目先の娯楽のためにお金の教育をするだけではなく、その根本の考え方もしっかりと教えてあげるようにしましょう。
[quads id=3]
まとめ
まだ早い、まだ幼い、親はそう思いがちですが、子供が「あれ買って」と言い始めたらお金教育を始めるいい時期です。
子供が「買って」と言いだした時に、親や大人が無条件に買ってあげると、お金のことを学ぶ貴重な機会を失ってしまいます。
日頃からお金についての正しい感覚が身につくように、ぜひ教えてあげて下さいね。
また、正しく使えばお金は人生を豊かにしてくれますし、使い方を間違えば身を滅ぼすことにもなるのがお金です。
ぜひ、それぞれの時期に合わせたお金の教育を、子供にしてあげてくださいね。
そして、それ以上に、人を思いやる気持ちを養うことや、お金を使う目的を見失うことがないように、言葉を足して伝えてあげたいですね。
[quads id=5]
[quads id=6]








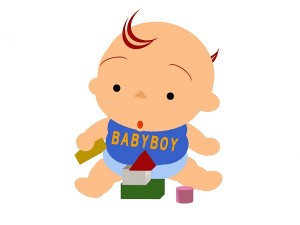




コメント
コメント一覧 (1件)
[…] →子供のお金教育にはコツがある!考える力を付けるには? […]