世界的にも長寿の国として知られる日本。
その秘訣の一つとして、魚を中心とした健康的な食生活があると言われていますが、食べ過ぎには注意が必要だと知っていましたか?
肉食よりも魚食の方がヘルシーで、美容にも健康にも良いイメージがありますよね。
ところが「魚だったらいくら食べてもOK」ということではないのです。
今回は、魚の食べ過ぎが原因になる症状や病気について、まとめました。
[quads id=1]
魚も食べ過ぎれば病気になる?

“お魚博士”の異名を持つ、タレントで東京海洋大学客員准教授の「さかなクン」。
2012年末に、彼が「尿管結石」で入院した際、この病気になった原因の一つとして魚の食べ過ぎが指摘され、大きな話題になりました。
当時さかなクンは、千葉県の房総地域に住んでおり、毎日魚づくしの食生活を送っていたそうです。
地元の漁師さんの漁船に乗せてもらい、獲れたての新鮮なイワシやアジを楽しむこともしばしば。
一見、健康そうな食生活に思えますが、もし魚だけを食べ続け、野菜やタンパク質など他の栄養素をあまり摂っていなかったとしたら・・・。
その偏った食生活が、病気を引き起こしてしまった可能性は充分考えられます。
では、尿管結石とはどんな病気なのでしょうか?
〇尿管結石とは?
尿管結石は、腎臓でできた結石が尿管へ流れ、その時に激痛が走る病気です。
結石は、カルシウムやミネラル物質が結晶化し、固まってできるものです。
男女問わず発症する可能性があり、その症状は、
- 下腹部への激しい痛み
- 血尿
などが挙げられます。
〇尿管結石の原因
尿管結石や痛風の原因となるのは「プリン体」です。
アジやイワシ、カツオなどにはプリン体が多く含まれているため、これらの魚を過剰摂取は注意が必要です。
尿酸が溜まって結石ができやすい、つまり尿管結石になりやすくなると言われています。
やはり、いくら良い栄養素が豊富に含まれているとは言え、食べ過ぎは病気の元となる、ということですね。
また魚の内臓や魚卵(タラコ、数の子など)にもプリン体やコレステロールが多く含まれていますので、食べ過ぎには注意しましょう。
[quads id=2]
イクラや塩鮭を食べ過ぎると、胃がんリスクが増える?
国立がん研究センターによれば、日本人に特有の塩分濃度の高い食品や塩蔵加工品の摂取回数が増えると、胃がんリスクも高まるという研究結果が示されています。
塩分濃度の高い食品とは、
- イクラやタラコなどの塩蔵魚卵
- 塩鮭やメザシなどの塩蔵魚
- 塩辛、練りウニなどの塩蔵魚介類
などです。
何か特定の魚が胃がんリスクを高めるのではありませんが、塩漬けされた味の濃い塩蔵(加工)食品を毎日食べ続けていると、胃がんのリスクを高めてしまう恐れがあるようです。
塩鮭などは、塩抜きしてから食べたり、これらの食品を食べるのは週に1~2回程度にする、など工夫が必要ですね。
妊婦さんが食べ過ぎてはいけない魚
妊娠中には、摂取を控えるようにと言われる食べ物がいくつかあります。
魚介類では、
- マグロ類
- 金目鯛
が挙げられます。
これらの魚には、食物連鎖によってメチル水銀が蓄積されている可能性が高く、またメチル水銀(有機水銀)は中枢神経に障害を起こすことで知られています。
またメチル水銀は、胎盤を通して胎児に移行しやすい点も指摘されています。
妊婦さんがこれらの魚を通じてメチル水銀を摂取すると、胎児の発達への影響が懸念されるのです。
なお、妊婦さんでも絶対に食べてはいけないということではなく、これらの魚は週に2回以内(合計で100~200g以下)とすることが推奨されています。
[quads id=3]
カロリーが高い魚もある?
お魚は全て低カロリーかと言えば、そうではありません。
調理法や個体差にもよりますが、一般的に以下の魚(魚料理)はカロリーが高いと言われています。
<100gあたりのカロリーランキング>
- アンコウの肝
- マグロのトロ
- フカヒレ
- さんま
- うなぎ蒲焼
- ツナ缶
- ぶり
- ハマチ
- イワシ
- 鯖
なお、これらの魚は200kcal以上あり、トップのアンコウの肝になると445kcal程度になります。
魚の脂質は不飽和脂肪酸なので、体脂肪になりにくいと言われています。
しかし、もちろん食べ過ぎれば太ってしまいますので、注意したいですね。
まとめ
以上、魚と病気の可能性について見てきました。
魚が肉類と比較してプリン体も少なく、低カロリーで、EPAやDHA、IPA、タウリンといった健康に良い成分が豊富に含まれていることには違いありません。
また、うつ病などの予防にも、魚の栄養素が有効であるとも言われています。
しかし、ヘルシーだからと言って食べ過ぎてしまったり、魚ばかりの偏った食生活を続けていては、結果、健康を害することになり本末転倒ですね。
あくまで色々な食材をバランスよく摂取することを心掛けて、心も体も健康的に過ごしましょう。
[quads id=5]
[quads id=6]






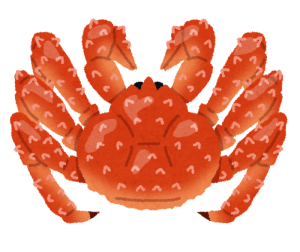
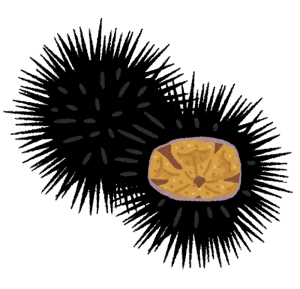

コメント