5月5日の「子供の日」に向けてこいのぼりをもらったものの、いつからいつまで上げればいいのか、疑問が頭をよぎることもあるのではないでしょうか。
ふと、こいのぼりを上げている家庭に気づいて、なんとなく合わせて上げたりしていますよね。
そんな時は、一般的な時期を確認しておくと安心です。
また、こいのぼりの意味を確認して、子供のお祝いの気持ちもしっかりと込めて上げるようにしたいですね。
[quads id=1]
こいのぼりはいつから上げるべきか
だいたい、ご近所の様子を見計らって、飾りだすことが多いかもしれませんが、ある意味ではそれで正解です。
というのも、こいのぼりを上げる期間は、4月上旬くらいから上げることが多いですが、実際は3月20日の春分の日を過ぎてから上げてもOKという少しあいまいなものだからです。
はっきり「いつからいつまで」と、決められているわけではないんですね。
ですが、こいのぼりを上げる日、そして片付けをする日は、大安の日を目安に行うのが一般的です。
男の子の成長をお祝いするめでたい日ですから、やはり縁起をかついで大安の日がいいですね。
こいのぼりはいつまで上げておくべき
こいのぼりを片付ける日は、一般的には、5月5日後すぐに片付けるのが一般的です。
ただし、その考えも地域によって、異なることがあるので、地域の風習に従うことが大切です。生まれ育った場所ではない場合は、ご近所さんに聞いてみるといいと思いますよ。
例えば、子供の日が過ぎても、そのまま5月末まで飾っておくこともあったり、旧暦でお祝いにする地域もあります。
旧暦でお祝いをする場合は、6月の中旬あたりまで出しているようです。
[quads id=2]
なぜ5月5日が端午の節句?
端午の節句は、奈良時代から行われてきた行事です。「端午」の「端」は月の初めの意味で、「午」は文字通り午の日のことですから、月の初めの午の日がもともと端午の節句でした。
それが、午は五の意味があるため、5月5日を端午の節句と呼ぶようになっていきました。
こいのぼりの意味
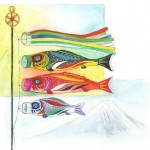
こいのぼりを飾るのは、もともと男の子が将来出世できるように祈願する意味合いがあります。
もともと江戸時代に武士の家に男の子が授かると、家紋の入った幟(のぼり)や旗などを上げる習慣がありました。
男の子が生まれると、一族みんなで喜び、それはそれは大事にされたんですね。
そして、武士に対抗する形で一般庶民の間で、鯉の絵を描いて飾るようになったのが、こいのぼりの由来です。
家門が繁栄してほしいという願いは、武士も一般庶民ももちろん同じだったのです。
中国の故事に由来している!?
では、なぜ「こい」を縁起物として考えたのかというと、中国に次のような故事があるからです。
「黄河に竜門と言う急流の滝がありましたが、さまざまな魚がその急流をめざし登ろうとしますが失敗に終わります。しかし、鯉だけが登りきり、後に竜もなりました。」
つまり、「こい」のように逆境に負けず、強くたくましく生き残れる子供に育ってほしいという願いが、こいのぼりに反映されているのです。
こいのぼりの意味や由来を知ると、昔の人の思いが今の時代になっても変わらず受け継がれていることがよく分かります。
時代や地域が違ったとしても、子供を大切にする親ごころは当然同じですね。
こいのぼりは、祖父母から贈られることが多い
男の子が誕生して、初めて迎える端午の節句は、両親だけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんにとっても、特別の行事となりますね。
こいのぼりは、祖父母から贈られるケースが多いですが、父方と母方の両方からダブって送られても困りますよね^^;l
最近のスタイルでは、両家でお金を出し合って購入するケースが一般化されつつありますので、もし祖父母からこいのぼりの相談があったら、両家の気持ちを受け取るのがよいでしょう。
[quads id=3]
初節句は皆でお祝い!
こいのぼりも大安に飾り始めて、鯉が風に乗って、すがすがしく泳いでいる姿を見ると、中国の故事で語られているストーリーが、ふつふつと蘇ってきますね。
こいのエネルギーにあやかって、ぜひ毎年男の子のお祝いをしてあげましょう。
そして、もし初節句であれば、いっそう特別なお祝いをしましょう。
おじいちゃんやおばあちゃんも招待して、端午の節句にちなんだ「ちまきや柏餅」などを作り、一緒に食事をする席を設けたいですね。
また、こいのぼりをいつからいつまであげるか、大安の日もチェックしておいてください。
子供の日に向けて、今からでも少しずつプランを立てて、楽しい思い出となるようにしてくださいね。
[quads id=5]
[quads id=6]



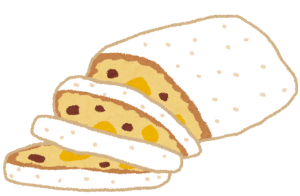

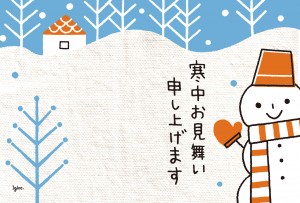

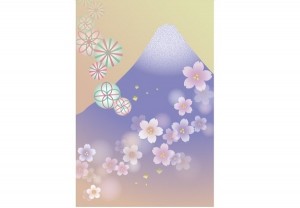

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] →こいのぼり、いつからいつまで上げるべき?意味や由来も! […]