子供の教育において、「褒めること」はとても重要であると、多くの親は聞かされています。
「褒める」と言う行為は、子供の成長期に“良い”影響を与えるのは、間違いありません。しかしながら、ナンデモカンデモ褒めてしまうのも、ちょっと考えものです。
成長過程にある子供には、ただ単に褒めるだけでは、逆効果になることがあるからです。
それほど褒めることでなくても、「よくやった」「すごい」等、言い続けていると、何やら、ちょっと困った方向に行ってしまうこともありますので、気をつけなければなりません。
いくつかのことに注意しながら、言い方を工夫しながら話すことで、「褒める」こと自体が、子供にもっと意味を与えます。
[quads id=1]
幼稚園児~小学生までの正しい褒め方15のコツ
1)「頭がいい」を連発しない
幼いうちから、文字を読んだり、3桁の数をかぞえたりする子供がいますが、そういう子供は、しょっちゅう、周りの大人からも「頭がいい」なんて言われていたりします。
頭がいいなどと、連発していると、確かに子供は自分はとても頭が良いと思い込むのですが、実は、頭がいいと言われているため失敗はできないと思い込み、失敗を恐れる子供になる可能性が高いと言われています。
そのため、自分で出来そうもないと感じたものへのチャレンジ精神がなくなるので、その先伸び悩みになるそうです。
これは、アメリカのスタンフォード大学の心理学の教授が子供のグループで実験をして、その結果で実証されています。
2)「上手」と言うだけでは不十分
確かに「上手」と褒めてあげると、子供はとても喜びます。しかし、何もわからない、ぐちゃぐちゃ描いた絵に対して、「上手」とは言いがたいものです。
とは言え、「ひどい絵」とも、まさか言えないことは確かです。
それでは、どう言ったら、いいかと言えば、「これは何かな?」とまず尋ねてください。
子供は、「これがママで、そしてこれが自分」など言うかもしれません。
その時は、「なるほど。ありがとう。がんばったね。じゃあ、パパも描いてみる?」なんて、何か絵にサジェスチョンを入れてみましょう。ただ単に、何も考えずに「上手」というより、ヒントを与えてあげます。
また、自分を描いてもらったことに対しても感謝を述べることを忘れずに。
これで、子供はまた描いてみようかと言う気持ちが起きてきます。さらに、一緒に描いてあげると、子供は喜んで自分も参加しますので、絵を楽しく学べるようになりますよ。
3)やったことについて、具体的に褒める
例えば、ボタンがうまく閉めることができなかったとします。しかし、ある日突然できるようになりました。
ママはさっそく、「よくできたね」と言うでしょう。
もちろん、それだけでも子供はうれしく思いますが、もうひとこと付け加えると、自分はどんなことで褒められたのかはっきり認識します。
「“ボタンがちゃんとはめられるようになった”のは、すごいよ。」と褒めてあげます。
これで、子供は、ボタンのように何か達成すると褒めてもらえるというパターンが身につきます。
4)小さなことでも、気がついてほめる
親は普段から、子供の成長については気に留めていますが、子供の成長も早いので、以前できなったことが出来るようになったこと等、小さなことはあまり気に留めずに、素通りしてしまうことがあります。
そこで、小さいことでも、「あれ!」と思ったことがあれば、忘れずに、「○○ができるようになったんだ。やったね!」と、さりげなく褒めてあげましょう。
私の息子が2,3歳の時に、ハサミがなかなかうまく使えなくて悪戦苦闘していましたが、それほど大きな問題にもしていませんでした。
ある日、ハサミを使って、好きな絵を切っているところを見て、すぐに前述した言葉を言ってみたら、得意になって、どんどんハサミを使うようになりました。
私が息子に言ってあげることで、きっと、「あ、そーか、あれだけ難しかったハサミが、今使えるようになったんだ」と気がついたのでしょうか?
小さな子供は、自分がいつの間にか出来るようになったことに気がつかないことがあります。
5)努力した過程をほめる
何かの目標を達成するには、やはり努力が必要です。
モノによっては、すんなり出来るものもあれば、ちょっと困難が伴うものもあります。子供にとっては、多くのものがちょっと努力をしないとそこに行き着きません。
実際に、努力しても、失敗することがあります。
しかし、大切なのは、その失敗の過程に経験したことこそが、これから将来のすべての成功につながってゆくのです。
小さな子供にそんなことを今説明しても、まったく理解できないですが、普段から、達成前の努力の段階を褒めるようにしておけば、これも大切なことなのだと体で理解するようになります。
描いた絵を見て、「ずいぶん一生懸命やったのがわかるよ。うまく描けたね。」とひとこと言ってあげましょう。
6)他の子供と比較して褒めない
「○○ちゃんよりも上手にできたね。すごい!」なんて言ってはいけません。子供は、誰とも比較して話さないようにしましょう。
それぞれの子供の進歩は皆異なります。また、それぞれの得意分野も異なりますので、どれから早く芽が出るかは、わからないのです。
そんな風に子供を褒めていると、子供も他の子供を見下したり、へんに競争意識を持ったりする可能性が出てきますので、注意しましょう。
[quads id=2]
7)褒めることを覚えておいて、忘れないうちに伝える
子供に褒めたいことが見つかった時に、忙しさにかまけて忘れてしまうこともありますが、必ず覚えておいて、タイミングを見てひとコト言ってあげてください。
忙しいと忘れてしまうことがありますのが、褒める点があれば子供に教えてあげることが重要で、子供も自分が得意なことがはっきりわかってきます。
これが、将来自分がどんな仕事がしたいのかの考えに導いてゆく助けとなります。
忘れそうなら、紙にでもメモしておくといいでしょう。
8)褒める際のコメントは短く
褒める時に、同時に何かコメントをしてあげるといいのですが、子供に長いコメントをするのはよくありません。
第一、あまり長くコメントしても途中から聞かなくなります。
例えば、子供が得意そうに絵を見せて、とてもうまく描けていたら、「ママはこの絵がとてもきれいだと思う。」とか、「すごく色がいいと思う」など、短くてわかりやすいコメントをしてあげます。
ママの言っていることがはっきりと理解し始める小学生になっても、複雑なことを長く言われると、子供はあまり理解しません。
それは、最後まで聞いていないからです。
どんなことでも、子供に伝えることは、短く、クリアであることがベストなのです。
9)褒めながら、けなしてはいけない
「よく出来たけど、ここをこうしたら、もっとよくなるのに」なんて言ってないですよね?
言った大人は、アドバイスのつもりで言っているかもしれませんが、アドバイスどころか、子供は内心がっかりします。
ある友人は、子供の頃にとても絵が好きだったければ、ある日とても嫌いになったそうです。
それは、子供の頃に、父親が「○○の絵は上手だけど、もっとうまく描けるはずだ」と言ったそうです。
その時点で、子供ながらに何だか描きたいという気持ちを失ったそうです。
10)何かの出来具合ばかりでなく、言動についても褒める
絵がうまく描けた、ブロックがうまく積めた等で褒めるのもいいですが、その子供の言動にもよく注意して褒めてみましょう。
例えば、何か間違ったことをしてしまった子供が、大人に「ごめんなさい」と言ったとします。
「ありがとう」はよく言えても、「ごめんなさい」はなかなか言えないことが多いものです。
しかし、子供ながらに一生懸命言ったのを見たら、「言ってくれてありがとう」とひとコト言いましょう。
あるいは、兄弟姉妹で、弟がおもちゃが壊れて泣いていたら、お兄ちゃんが自分のを弟に貸してあげたとします。
子供なのに、なかなか出来ることではありません。その時も、「あなたの弟にやさしくしてくれてありがとうね。ママはとても誇りに思う」と言って褒めてください。
こう言った感情面でも褒めてあげることは、子供の情緒面に大きく影響してきます。
11)本当に「よくやった!」と思ったら
例えば、2,3歳のトイレトレーニングは、子供たちにとって、難関のひとつです。
実際には、そこにたどりつくまで、何度もアクシデントを繰り返す子供は多いものです。
また、アクシデントごとに処理する母親も、正直言ってラクではありません。
時々イライラもしますが、これは母親と子供の二人三脚でやる大仕事と言っても過言ではないでしょう。
こういった大きな難関を突破できた時は、子供に褒めるのは、もちろん、ご褒美をあげてもいいと思います。
初めて自分でトイレに行けたら、アイスクリームサンデーを一緒に食べてお祝いするとか、大きなことには、がんばった結果、達成できたことを印象づけてあげましょう。
これで子供も、苦しかったけれど一生懸命やるとこんなにいいことがあるのか、と感じるようになります。
12)しかし褒めすぎるとプレッシャーになることも
自分の子供の得意なことを、他の人に自慢する親がいます。
「○○は、もうABCが言えるんだよ。ほら、今皆の前で言ってみせなよ」等言って、子供にそれをやらせようとします。
私は、何度かその現場に居合わせたことがあるのですが、そういう感じでプッシュすると、子供はやらない場合が多いのです。
子供が得意なことを知って、他の人にも披露したいのはわかりますが、「褒める」目的は、人に見せるためのものではなく、将来の子供の才能を育てることがメインですので、変にプレッシャーを与えるのも考えものだと思います。
13)どんなことでも褒められるという流れを作らない
「褒める」ことが子供を喜ばせるからと言って、いい加減な作業をしたら、褒めることは控えましょう。
褒めれば、次はもっとよくやってくれるかと言えば、そうではありません。
子供の思考はとても単純で、どんなことでも簡単に褒めていれば、「あー、こんないい加減になっても、褒めてくれるなら、チョロいものだ」と子供心に感じ取ってしまいます。
その結果、次もいい加減なものを出してくるでしょう。
大人もそうですが、子供も作業は、苦労がつきまとうより、そりゃ、簡単なほうがもちろんいいに決まっています。
でも、世の中そうは行きませんよね。
努力しただけのものが、そのままついてくるのです。
ですから、ナンデモ褒める流れを作ってはいけません。
14)「惜しい! もう少しがんばろう」
アメリカの保育園の話なのですが、子供たちが何かよく出来た時は、英語でGood Job!またはNice Job!と言って褒めますが、ちょっと失敗してしまったら、Nice try「惜しかったね。でも、がんばろう」と言います。
例えば、ボールを子供用のネットに入れたいけれど、なかなか入らない! その場合は、Good job ではなくて、 Nice tryですね。
しかし、失敗しても、それほど違和感のない言葉だと思いませんか?
日本語でも同じで、本当によくやったら、「よくやったね」と言ってほめてください。
しかし、失敗した時は、暖かく「惜しかったね。でも、もう一度やってみようか?」とやさしく言ってみましょう。
これで、失敗した時に、すぐに褒められないけれど、失敗しても大丈夫、またトライしたらいいんだからと言うパターンが身につきます。
15)得意顔を見逃さない
時々、子供がはりきって、親を呼んで、自分が作ったものや絵など、見せることはありませんか?
そんな時は、子供の顔を見てください。得意顔をしているのを見逃してはいけません。
この顔を見せたら、無条件で褒めるサインです。
子供は、この時、大人に褒められるだけの大仕事をこなしたと言っている顔なのです。
その顔を見た時の作品は、その子供にしては、結構すごいものだったりして、褒められるのを期待しています。
まあ、その子供にとって、大人へのサプライズですね。その時は、むずかしいこと抜きにして、「わーすごい。よくやったね」と心から褒めてあげてください。
ちょっと細かいことが聞けそうなら、例えば、子供がママの絵を描いていたら、「この帽子、ママが持っているのだね。同じ色も使ってる」など、さらに一緒に話の花を咲かせてみましょう。
褒められ上手の子供に育てよう
単に「褒める」のではなく、もう少し工夫しながら褒めることで、もっと子供の成長に有益な効果を及ぼすことをお話しました。
これは、言うなれば「褒め上手」になることだと思います。
それに大人が褒め上手になれば、自然と子供も「褒められ上手」になります。
[quads id=3]
まとめ
正しい褒め方をすることは、子供の成長にとってものすごく重要な意味を持ちます。いろいろなシチュエーションで褒められたことを元にすばらしく成長してゆくことでしょう。
褒め上手とは、適切な時に、適切な方法で、心地よく褒めてあげること。
そして、褒められ上手とは、褒められたひとつひとつのことから、自分の本当の強みを見出し、さらに成長してゆくことでしょうか。
親子で本物の実力を見出せるように、一生懸命、一歩一歩進んでゆきましょう。
ぜひ子育てに一生懸命なママ友がいたら、フェイスブックやツイッターでシェアしてあげてください。また、ご自身でもはてなブックマークなどで保存しておくことをオススメします。
折にふれて確認することで、子供といい関係を築いていくための手助けになるはずですから。
[quads id=5]
[quads id=6]




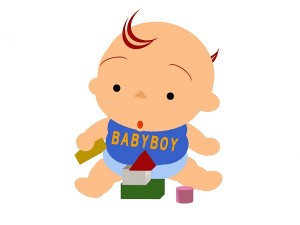




コメント
コメント一覧 (6件)
[…] →間違えたら大変!子供の正しい褒め方15のコツ【完全保存版】 […]
[…] →間違えたら大変!子供の正しい褒め方15のコツを覚えておこう! […]
[…] →間違えたら大変なことに!子供の正しい褒め方15のコツ […]
[…] →間違えたら大変なことに!子供の正しい褒め方15のコツ […]
[…] →勘違い続出!子供の正しい褒め方15のコツ […]
[…] →間違えたら大変!子供の正しい褒め方15のコツ【完全保存版】 […]