上の子供が2歳になる頃、下の子供が生まれるケースは多いですよね。
そんな時の悩みとしてありがちなのが、2歳になった上の子供の赤ちゃん返りです。
2人目が生まれると、余計に忙しくなるのに、上の子供まで赤ちゃん返りされるとママの負担は倍増してしまいますよね。
愛情を正しく伝えることが、赤ちゃん返りの対応に必要なことですが、果たしてできているでしょうか。
2歳児はただでさえ、イヤイヤ期にも突入しますので、本人もママも繊細な時期です。
対応のチェックポイントを5つにまとめてみたので、確認しておきましょう。
[quads id=1]
2歳児の赤ちゃん返りの対応 5つのヒント
ママが下の子供の妊娠中には、「お兄ちゃん(お姉ちゃん)になるの楽しみだね^^」なんて一緒に話していた上の子供が、いざ下の子供が生まれた後、突然赤ちゃん返りが始まるということはよくあります。
今までは、すべての大人の目が自分に向いていたのに弟(妹)が生まれてからは、関心がすべてそちらに向くことで、それを何とか取り戻したいと感じて、上の子供が起こす行為です。
また、2歳児ですから、まだまだ幼く、ママの十分な注目が必要です。
今その最中であるのでしたら、まず「あまり心配する必要はない、逆に赤ちゃん返りがある方が安心!」と言い聞かせてから、次の対応別の事項を参考にしてみてください。
1)下の子供を抱っこしている間、寄ってきたら抱っこをする

ママ以外の大人がいれば、そちらに赤ちゃんを頼んで、すぐにママが上の子供を抱っこしてあげましょう。
またはママだけであれば、赤ちゃんをひとまず安定したところに寝かせ、上の子供を抱っこしましょう。
2)ママのおっぱいを欲しがる時、他のものに気をそらす
2歳児なら、もうすでにママからのおっぱいは卒業していますよね。
でも、下の子がママのおっぱいを飲んでいるのを見ると自分も赤ちゃんのようになりたい、また赤ちゃんと同じようにママに優しくされたいと思ってしまいます。
おっぱいをあげる代わりに…
1歳ぐらいで、ほとんどの断乳の段階に入っていますので、2歳児におっぱいを再開するのは問題です。
この年齢の子供は、ママのおっぱいでお腹をいっぱいにするのではなく、もうすでにある程度大人が食べるものも試しながら、食事をさせる時期に入っています。
そこで、ママが赤ちゃんにおっぱいをあげているのを見て、2歳児がおっぱいを求めてきたら何か他のものに注意を引かせるように努力しましょう。
こんなアイデアも!
例えば、上の子供が好きなキャラクターがついたカップを一緒に買ってきましょう。
それにミルクを入れて、飲ませるなどするのもいいかもしれません。
「ほら、こっちのほうが格好いいでしょう?」と言うようにカップで飲むことを勧めましょう。
また、そのカップで飲む時は、ママが一緒についてあげるようにしてください。
決して、与えてすぐに上の子供を1人にして赤ちゃんに意識を向けることはしないようにということがポイントです。
3)なかなか言うことを聞かなくても怒らない

2歳児は特に、イヤイヤ期の真っ最中でもありますよね。赤ちゃん返りの行動が続いて、言うことを聞かず挙句の果てに大泣きすることもあるでしょう。
しかし、そんな時に「怒らないように気をつける」ことはとても大切です。
ママのほうも、上の子供が言うことを聞かないことで、精神的に限界になってしまうこともあるでしょう。
怒らないために有効な方法とは?
怒ることのデメリットを認識し、まずは深呼吸してみましょう。
赤ちゃん返りの子供を怒ると、もっとエスカレートすることがあることを、親が知ることから始まります。
もちろん上の子自身は、自分が赤ちゃん返りしていることは、分かっていません。自然と出てくる防衛本能であることを知っておいてください。
そう思うと、ちょっとだけママも感情をコントロールできるかもしれませんね。
4)2歳児がママに何かを頼んできたら、いつやってあげるか示す

例えば、赤ちゃんのおむつを換えている時に上の子供から「本を読んでほしい」「お腹が空いた」など、ママの関心を引くために、何か頼んでくることがありますよね。
そんな時は、「わかった。待っててね。おむつを換えたらするから」と言って、しっかり応えるようにしましょう。
いつやるのかを示すことがポイント
「今忙しいから」「あっちに行ってなさい」「今できるかわからない」などの曖昧な返事は、2歳児の心をもっと不安にさせます。
はっきりと「いついつやるから待っていて」と返事をするようにします。
また、その時、ママは上の子供のほうに顔を向けて、しっかりと応えてあげるようにしましょう。
そうすることで「ママは自分のほうを見ている」との自覚を持ち、上の子供も随分気持ちが楽になるようです。
5)「お兄ちゃん(お姉ちゃん)だから」はやめる
下の子供ができた当初は、上の子供もまだまだ幼く、その存在を受け入れる体制が出来ていません。
いくら、生まれる前に、「お兄ちゃん(お姉ちゃん)になるの楽しみだ」と言っても、2歳児にとってはそう簡単に、新しい存在に対してのキャパシティが広がるわけはありません。
ものの道理を立てて、説明しようともまったく理解できていません。
そんな時に赤ちゃんとの年の差を例にあげて、「大きいんだから、○○はもうしちゃだめだよ」「お兄ちゃん(お姉ちゃん)だから、○○にあげようね」などと話をしないようにしましょう。
自然と上下関係を理解するのが理想
実際は、何でも平等になるように、兄弟を育てて行くのが理想です。
そのうち、上の子供が「僕はお兄ちゃん(お姉ちゃん)なんだ」と理解し、自覚できるようになってきます。
事実、年がもっと離れていると、もっと早く、より簡単に年齢の上下関係が理解できるようです。
[quads id=2]
上の子供はこうやって下の子供を受け入れていく!
上の子供の気持ちが落ち着くまでは、常に「ママもパパも、あなたを下の子供と同じように愛している」ことを示してください。
下の子供を抱っこした後は、上の子供も抱っこしてあげたり、出来るだけ時間を取って、上の子供の遊びに付き合いましょう。
そのうちに、上の子供は、下の子供に対する不安も少しずつ解消して行き、その存在を受け入れられる体制が整っていきます。
個人差がありますので、どのくらいかかるのかはそれぞれ異なりますが、赤ちゃん返りの対応で一番大切なのは、子供に“わかるように”愛情を注ぎ、常に目をかけることです。
そうすればママの愛情で上の子供が落ち着き、より早く問題が打開されることも大いにありえます。
「愛情」を理解するキーワード

どの子供も望むことは、親に「甘える」ことです。「甘やかす」という言葉がありますが、“精神的”に甘やかすことはなんら間違いではありません。
これに対して、子供が欲しがる物をどんどん買い与える、物質的な甘やかしがありますが、それとは異なります。
そうではなく、心と心の対話が出来るような「甘え」なら、大人にだって必要なことですから、それが2歳児なら、なおさら必要なのです。
親子の愛情を確かなものに!
その段階を踏んで、ママとの結びつき=絆が安定すると、今度は自分の弟や妹を受け入れられる気持ちが生まれてくるのです。
それをベースに育つと、ママのために、そして可愛い弟や妹の面倒を率先してみたり、お手伝いをしてくれる頼もしい子供に育って行きます。
[quads id=3]
まとめ
それでは最後にテストです。
Q:上の子供が靴下を履かせてと訴えている時に下の子供も泣いています!まずあなたがすることは?
・
・
・
・
・
・
A:それは、上の子供を優先することです。
これが下の子供を優先すると、上の子供の赤ちゃん返りを増長させる引き金になります。
ポイントの3つ目でもお話したように、「あなたはもう大きいから、下の子の用事が済むまで我慢しなさい」のような発言や行動はあまりおすすめできません。
そのような発言や行動を続けていると、「自分は下の子供より価値がない」「ママは下の子供の方が好きなんだ」と感じるようになるのです。
そして、下の子供と同じように赤ちゃんになり、ママや大人が注目するという結果にたどり着いてしまうのです。
つまり、赤ちゃん返りを改善する方法で、まず考えることは、上の子供を優先して、「愛情を注ぐこと」「欲求を満たしてあげること」を念頭に置きながら行動することが大切なのです。
食事も楽しいコミュニケーション
食事を通して、楽しく子供と気持ちのキャッチボールをしましょう。
習い事の探し方のヒント!
子供が好きなことを一緒に探してあげるのがコツです。
親子の絆を確認しよう
赤ちゃん返りの2歳児の相手は大変だと思いますが、親子の絆を知るとそんなことは吹っ飛んでしまいますよ。
[quads id=5]
[quads id=6]




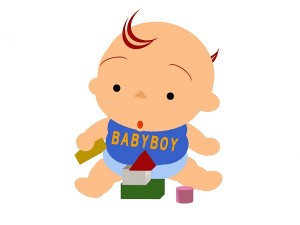




コメント
コメント一覧 (2件)
[…] →2歳児の赤ちゃん返りはなぜ?対応のヒント5つ! […]
[…] →2歳児の赤ちゃん返りはなぜ?対応のヒント5つ! […]