いろいろな知育玩具が2、3歳の幼児向けに使えますが、粘土もその一つです。
粘土はさまざまな形を作ることだけでなく、色も一緒に学ぶことができる知育玩具です。
幼児の創造力を高める効果がありますし、子供とのコミュニケーションにも有効なので、遊びの中に積極的に取り入れることをオススメします。
それでは、粘土遊びの手順や、粘土を小麦粉で手作りする方法を紹介していきましょう。
[quads id=1]
粘土遊びは2、3歳の幼児から!
粘土が適する年代は2歳くらいからです。
あまり早くからスタートしても、粘土を口にいれてしまったり、手や指の成長がまだ未発達なため、うまく使いこなすことができません。
2歳の幼児でも、たまに口に入れてしまったりしますので、粘土で遊ぶ時は、常に大人が側で気をつけておく必要があります。
1)粘土遊びで形を覚える
はじめは手を使うことを覚えながら、カンタンな形からチャレンジしていくとよいですね。
◯ボールを作ろう
たとえば、まずはボールを作るように教えてあげましょう。
ボールは、少しの粘土を手の平にもって、両手でくるくるしている内に丸くなっていきます。はじめは完全な丸にはなりませんが、特に気にせずに一緒に作ってみましょう。
そして、ふたつできたら「雪だるま」ができますので、くっつけて見ることでまた幼児の創造の世界が広がります。
◯ヘビを作ろう
次は「へび」です。へびも少しの粘土を机に置いて、片方の手の平で机の上の粘土を転がします。これでへびができます。
(※へびとボールは、勿論、どちらを先に作ってもOKですよ^^)
◯アルファベットや数字を作ろう
粘土のさまざまな型が一緒に売られていますが、簡単な形の型を用意して、アルファベット、数や形を遊びながら覚えることができます。
三角形、円、四角等、またはいくつかの数字、アルファベット等の粘土用の型に粘土をはめて、幼児と一緒に作ってみましょう。
◯注意点
ただし、粘土遊びの途中で勉強をするように「形は何?」「このアルファベットは何?」としつこく聞きすぎないようにします。
あくまでも粘土遊びを楽しみながら、自然に頭に入れていく方法で十分です。
例えば、幼児に「そこの三角形の型を取ってくれる?」みたいに自然と誘導し、形を記憶させるのがオススメですよ!
2)粘土遊びで色を学ぶ
小麦粉粘土を作る際に、食用色素でいろいろな色の粘土を作ることができます。
粘土の色で、「赤いボール」「靴の色と一緒の緑」など、色を覚えさせるきっかけができるでしょう。
◯色の組み合わせ
粘度で遊んでいく中で2つの色を混ぜると違う色になることを説明する時に便利です。
例えば、「赤と黄色を混ぜるとオレンジ色」「青と赤を混ぜると紫色」などの色遊びも楽しみながらできてしまいます♪
◯季節の色

シーズンごとに季節をイメージする色ってありますよね。
例えば、春の色なら薄い黄色、ピンク色、緑色。夏は青色。秋は茶色、黄色。冬は白色など。
または、ハロウイーンの時期ならオレンジ色。クリスマスなら、赤色、緑色など、季節に合わせた色を用意することも季節感を養う機会になります。
3)粘土遊びで香りを楽しむ
粘土にシナモンやバニラなどの匂いを含ませて作るのもいいでしょう。ちょっとしたいい香りを幼児に教えてあげることで、嗅覚を養うこともできます。
家庭にある、クッキー用のエッセンスなどを利用すればOKです。
幼児が「何だかいい匂い」と言えば、「これはシナモンだよ」などと会話する内に自然と覚えて行きます。
4)粘土遊びで幼児とコミュニケーションを取ろう!

幼児が少しずつ粘土で何か作ることに慣れてくると、親の手を借りずに自分で何かを作りたいと思うこともあります。
その時、「何を作っているの?」「何ができるかな?」と声をかけてみましょう。
例えば、少し前に一緒に作っていたへびや雪だるまを自分ひとりで作ろうとしていることもあります。
少し前に一緒に作ったものを思い返しながら、幼児なりに一生懸命作っています。出来上がりが違ったものになったとしてもママはあまり手を出さずに、黙って見守ってあげましょう。
粘度が完成したら「よくできたねー」「上手に作れたね」としっかり笑顔で褒めてあげましょう。また、そのままとっておいて「パパにも見せようね」と言って、後でパパにも見せてあげましょう。
自信がも付きますし、楽しみながら遊ぶことで想像力を育てることができますよ♪
[quads id=2]
粘土は小麦粉で作れる!
粘土は、自宅で簡単に手作りすることができます。
小麦粉で作れますので、幼児にも安心して触らせることができます。
ここでは、自宅での粘土の作り方をご紹介します。更に知育効果を意識するなら、自家製粘土を作る際も幼児と一緒に作ってみましょう。
材料:小麦粉 500g、サラダ油 少々、水 適量、塩 ひとつまみ、食用色素 好きな色
作り方:小麦粉とサラダ油を入れます。水は小麦粉を混ぜながら、少しずつ入れていきましょう。
※あまり水っぽくならないように気をつけます。粘土としての硬さであれば、それに食用色素を入れて、よく混ぜて完成です。
小麦、サラダ油、塩をあらかじめ、カップにいれておきましょう。幼児に材料をボウルに入れてもらうなどのお手伝いをさせるのもいいですね^^
また、食用色素の色を選ばせるのもいいでしょう。
作る時も、遊ぶ時もビニールシートが便利

粘土遊びでも、特に食用色素の色を使ったり、自家製の粘土だと、小麦粉の粉があちこちに散らばって汚れてしまいます。
幼児と粘土を作る際や遊んでいる最中も散らかってしまいますので、作る前からあらかじめビニールシートを敷き、その上で粘土作りをすると後はそのままゴミ箱にシートについた汚れを落とすだけですから、後がラクですよ。
片付けが大変になると次回の粘土遊びが億劫になりますから、ママの負担が最小限に収まることが大切です。
手作り粘土の保管期限
小麦粉ですからそれほど長くは持ちません。
3日程度ですが、タッパーのような密封容器にいれて、冷蔵庫で保管しましょう。
小麦粉ですからあまり長持ちはしませんが、塩を少し多めに入れておくと、1、2日はより長く持ちします。変な臭いがした時はすぐに捨てるようにしてくださいね。
粘土にあまり興味を示さない幼児も…
粘土遊びは、ほとんどの幼児が好きですが、中には、それほど興味を示さない場合もあります。
別に焦る必要はありませんが、興味を示さないからといってすぐに諦める必要もありませんよ。
その場合は粘土を作る時に形を作るのではなく、一緒にコネコネしたり、色をつけたりするだけでも楽しめるものです。
幼児の頃は、ぐちゃぐちゃしたものを触るのが大好きですからね。
その内に粘土作りに興味を抱くこともあるでしょう。
また、ママがその粘土を使って、何か面白そうなものを作って見せてあげるのも興味を持つきかっけになるでしょう。
いずれにしても楽しみながら遊ぶことが大切なことです。
[quads id=3]
まとめ
粘土遊びを通して「色」と「形」を遊びながら学ぶ方法を紹介してきました。
工夫次第で香りや季節感まで学べるのが粘土遊びの魅力です。
2、3歳の幼児は吸収力がすごくどんどん成長していきます。私たち大人が考えている以上にすごい能力がありますから、いろんな刺激を与えてあげたいものです。
粘土は、昔からある幼児のおもちゃのひとつですが、粘度が秘めている可能性は大きく、幼児の創造力、想像力共に育むきっかけとしてとても効果的です。
粘土は購入しても、自宅で作っても、それほどコストがかからないところも嬉しいですね。
後はママの工夫の腕のみせどころ!効果的な知育を遊びで取り入れることができますから、ぜひ参考になさってくださいね!
2,3歳の子供の気持ちを理解するコツとは?
→【イヤイヤ期】2歳~3歳児の、気持ちに寄り添う20のコツと対処法
下の子が生まれたら注意!
2,3歳の幼児は、イヤイヤ期に突入する時期ですが、飛躍的に成長する時期でもあります。
正しいコミュニケーションを取っていきたいですね^^
[quads id=5]
[quads id=6]




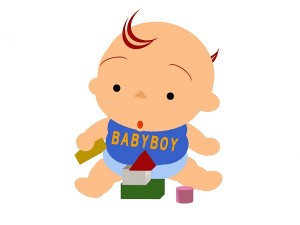




コメント
コメント一覧 (3件)
[…] →粘土遊びは2、3歳の幼児にどんな効果?実は小麦粉で作れます! […]
[…] →粘土遊びは2、3歳の幼児にどんな効果?実は小麦粉で作れます! […]
[…] →粘土遊びは2、3歳の幼児に効果がある?お手製粘土を小麦粉で作ろう! […]