4~5ヶ月頃の赤ちゃんが突如、キャーとかキーとか大声で奇声を出し始めることがありますよね。
その奇声の大きさにびっくりしたり、戸惑ったりするお母さんも多いことでしょう。
こんな大声で奇声をあげたら近所迷惑になるのでは?虐待をしていると疑われるのでは?まさかうちの子、発達障害……?
お母さんの不安は赤ちゃんがあげる奇声を聞く度に大きくなるかもしれません。
でも、赤ちゃんがあげる奇声には実は赤ちゃんなりの理由があるんです。今回はそんな赤ちゃんの奇声に関してのチェックポイントや対処法をご紹介します。
[quads id=1]
赤ちゃんが奇声をあげる理由とは?
赤ちゃんが奇声をあげる時の様子はどんな感じでしょうか。
ニコニコしながらご機嫌で奇声をあげてはいませんか?
手足をバタバタばたつかせて、お母さんの顔を見るとニコニコして喜びますか?
こんな感じでごきげんな様子で奇声をあげているなら、なんの問題もありません。
赤ちゃんはまだ言葉が話せません。だから、感情表現の一つとして奇声をあげることを自分で選んでいるのです。
そして、その声を聞いて更にご機嫌になっているなら、ちゃんと耳が聞こえている証拠でもあります。
ご機嫌だからこそ出る奇声を「今日も絶好調だね!」ぐらいの気持ちで受け止めましょう。
奇声の対処法は、このコミュニケーションで!

ご機嫌な時の奇声は、対処法で悩むことはないと思います。
でも、気分がいい時に奇声をあげるとは限りません。たとえば、このような時にも奇声をあげることがあります。
・思い通りに行かずイライラしている時
・誰かに注目して欲しい時
・不安でどうしようもない時
このような気持ちのときには、お母さんに甘えたいんですね。赤ちゃんは奇声をあげれば、大好きなお母さんが「どうしたの?」と抱っこをしてくれることを知っています。
その時は、抱っこできる時は抱っこしてあげて、どうしても手が離せない時は、言葉でコミュケーションをはかりましょう。
「今はお皿を洗っているからもう少し待っていてね。」
「今はスーパーにいるから騒いだら迷惑になるからいけないよ」
そして、待たせた後は、必ず褒めてあげましょう。
「上手に待ててえらかったね。」
大きな声での奇声を止めさせたければ、その時もただ叱るのではなく、言葉で伝えましょう。
「大きな声を出すとママの耳が痛くなっちゃうよ。」
「今は静かにする時間だよ。」
「もう寝んねの時間だから静かにしようね。」
そして、静かにできたらたっぷりと褒めてあげましょう。
「静かにできたね、えらいね。」
成長していくうちに赤ちゃんの口から言葉が出てくるようになり、大人の言葉を少しずつ理解し始めます。
頭ごなしに「うるさい!」「静かに!」と叱るのではなく、ちゃんと理由を伝えてあげると、赤ちゃんも理解してくれますよ。
[quads id=2]
発達障害かどうかの見分け方

ところで、一般的に発達障害としっかりとした診断ができるのは、3歳以降と言われています。
ですが、3歳を過ぎても、以下のような反応が見られるようでしたら、少し注意が必要です。
・寝返りができない
・おすわりが出来ない
・歩けない内から高い所に登りたがる
・物を口に運んで自分から食べようとしない
・異様にこだわりの強さを見せることがある
・視線が合わない
・呼びかけに反応しない
・言葉が遅い
そして、「赤ちゃんの奇声が成長によるものではないかもしれない」と不安に思った時は、1人で悩まずに、近くの医療機関に相談してみましょう。
[quads id=3]
赤ちゃんの脳に必要な栄養は3歳までが勝負です

子供の脳は3歳までにほぼ100完成すると言われています。
つまり、3歳までに食べさせたもので、基本的な脳の性能が決まってしまうということです。
赤ちゃんが便秘で苦しんでいませんか?
赤ちゃんが便秘で苦しんでいる場合には、適切な対処をする必要があります。
ぜひこちらの記事も参考にしてください。
ガマンしても何も良いことはありませんよ。
→赤ちゃんのお腹が苦しそう!オリゴ糖はほんとに効果があるの?
まとめ
赤ちゃんが突然、奇声をあげるとびっくりしますよね。
わが家でも長女が5ヶ月ぐらいの時に、突然お風呂あがりにニコニコしながら、
「キャーーーーーーーーーーーー」と奇声をあげたことがありました。
いきなり始まったので「え???なんで?なに?」と戸惑ったのを覚えています。
でも、自分の声を聞いてますますご機嫌になり、イルカの出す鳴き声に近い奇声をあげる長女に「イルカちゃん」とアダ名をつけて過ごしているうちに、いつの間にか奇声をあげることはなくなりました。
赤ちゃんが奇声を上げたときは、まず赤ちゃんの様子をよく見てあげてください。
「うるさいよ、静かに!」と叱ることで終わらせるのではなく、ご紹介したような言葉を使って、しっかり赤ちゃんと向き合ってコミュニケーションをはかりましょう。
赤ちゃんの昼寝の注意点
赤ちゃんの昼寝についても、正しい知識を身につけておきたいですね。
赤ちゃんの鼻づまりの対処法6つ
赤ちゃんが鼻づまりになったときは、この解消法を実践すれば大丈夫です。
気の合うママ友も作っておこう!
近くにママ友がいると、何かと相談もできるし安心ですよね。こちらの記事を参考にしてみてください!
[quads id=5]
[quads id=6]




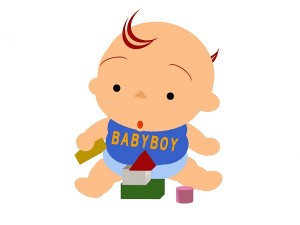




コメント