もやしと枝豆、どちらも私たちの食生活の中で重宝する食材ですよね。
もやしは、一年を通して安価で家計に優しい食材です。
枝豆は、ビールのおつまみにも欠かせない一品で夏野菜の代表とも言えますが、冷凍食品の種類も豊富ですよね。
そんな、もやしと枝豆ですが、実は同じものということを知っていましたか?
どちらも大豆の成長と関わりがあり、収穫時期が違うだけなのです。
今回は、もやしと枝豆について、栄養素やカロリーの違い、もやしの栽培方法などについて紹介していきたいと思います。
[quads id=1]
もやしと枝豆、どちらも大豆の成長に関係アリ

もやしと枝豆は、収穫時期が異なるだけで実は同じものです。
大豆が育つ過程で、緑色の未熟な大豆を枝も一緒に収穫したものが「枝豆」です。
枝豆を収穫せずにそのまま成長させると大豆になります。
また、大豆を暗い場所で人工的に発芽させると「もやし」になります。
○もやしの本来の意味は?
もやしを「萌やし」と表記することもあり、本来は新芽の作物を意味します。
日本ではもやしというと緑豆もやしが多く普及していますが、中華料理などで炒め物に多用される大豆もやしも有名です。
今回は、もやしの種類の中でも大豆もやしのことを取り上げています。
[quads id=2]
もやしと枝豆、栄養面で違いはあるの?
大豆を発芽させた「もやし」と、未熟な大豆を枝ごと収穫した「枝豆」。
栄養面で違いがあるの?
大豆として食べるよりも利点があるの?
と疑問が沸きますよね。
もやしは、低カロリーなうえに一度にたくさん摂取することができるという長所があります。
そのため満腹感が得られやすく、ヘルシーな食材でおすすめです。
○カロリーと栄養素の違い
ちなみに、大豆もやしのカロリーは100gあたり37kcalなのに対し、枝豆は135kcal、大豆は433kcalです。
枝豆は、大豆には少ないビタミンAやビタミンCが豊富に含まれています。
枝豆100gと大豆100gの中に含まれる量は、以下の通りです。
- ビタミンA・・・枝豆が110mg、大豆は12mg
- ビタミンC・・・枝豆が30mg、大豆が0mg
このように、枝豆には夏に不足しがちなミネラルが豊富に含まれているため、夏バテ予防に欠かせない食材です。
[quads id=3]
自家製大豆もやしの作り方を紹介!
大豆を人工的に発芽させるともやしになるということを紹介しました。
ここからは、自宅で大豆もやしを作る方法を具体的に説明していきます。
1)大豆を洗い、たっぷりの水に一晩以上つける
大豆がふっくらするまで水につけることが大切です。
これが不十分だと発芽率が下がってしまいます。
水が少ないと大豆が充分に吸水できないので、水は多めに用意しましょう。
2)大豆の吸水が済んだら水を捨てる
水切り付きタッパー容器に入れ、湿度を調節するため、蓋を少しずらした状態にします。
暗所で栽培するため段ボール箱などを利用して日光が当たらないようにしましょう。
腐るのを防ぐため、一日2回ほどは大豆を洗ってぬめりを取りましょう。
◯大豆もやしを作る時の2つのコツ
大豆は発芽するまでに時間がかかるため、
- できるだけ新しい豆を使って豆がふっくらするまで充分に水につけること
- 一日数回は必ず水洗いすること
が成功の秘訣です。
大豆以外にも、小豆などでも発芽可能ですが、季節によって発芽までの日数にはバラつきがあります。
大豆もやしは、もやしと枝豆を一緒に食べているような感覚で絶品です。
興味がある人はぜひ試してみてはいかがでしょうか。
まとめ

もやしと枝豆は収穫時期が異なるだけで、実は同じものです。
成長過程で名前が違うという出世魚の植物バージョンと言ってもいいかもしれません。
- 大豆を発芽させたものが「もやし」
- 大豆が出来る前の未熟な大豆をさやごと収穫したのが「枝豆」
どちらもそれぞれに長所があります。
もやし
低カロリー低価格で一年を通して家庭料理に利用しやすい食材です。
枝豆
大豆よりもビタミンが豊富で夏バテ予防にピッタリです。
それぞれの良さを知ったうえで料理したり栽培したりすると、食べ物に対する考え方がさらに広がるかもしれませんね。
[quads id=5]
[quads id=6]






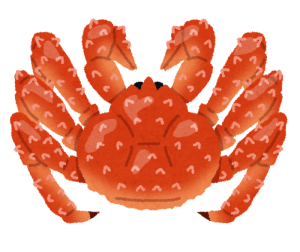
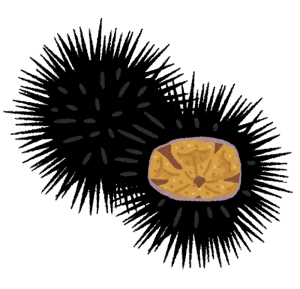

コメント