初盆に招かれて香典の準備をする時に、表書きにどう書こうか手が止まる方も多いと思います。
初盆だけに失礼がないようにしたいですし、一般常識を疑われたくはないですよね。
ただ、昔ながらの風習は、基本的なルールさえ押さえてしまったら、逆に不安要素はなくなります。
表書きの書き方だけでなく、香典袋の選び方、知っておきたい法事のマナーなどを、この機会に確認してみましょう。
[quads id=1]
初盆の香典の表書きのルール

準備でほぼ必須といえるのが、香典の用意や、お供え物の用意ですね。
初盆の香典の表書きは、金封であれば「御佛前」「御供物料」と書きます。
品物であれば「御供」「お供物」と書くのが一般的です。
筆で書くのが正式ですが、筆ペンでもかまいません。下段はフルネームで書き入れてください。
字が上手でなくても、丁寧に書いた字と分かれば大丈夫ですよ。斜めに歪んだりしないようにだけ注意しましょう。
○香典の相場
初盆の香典の相場は、1人で行く場合は5,000円~10,000円、2人の場合は20,000~30,000円ぐらいになります。
僧侶の読経の後に食事がふるまわれる場合は、気持ち多めに包むようにします。
また金額は、漢数字を使用するとしっかりした印象にもなりますし、書き換えられることもなくなります。
二 → 弐
三 → 参
中袋に金額を書く時は、このような漢数字を用いるようにしましょう。
[quads id=2]
不祝儀袋や水引の種類

法事などのお悔やみで使われるお金を入れる袋は、「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」と呼ばれます。
不祝儀袋の帯の水引が、結び切りという固く結んでほどけない形のものを選んでください。これは、1度きりであってほしい行事の際に使います。
逆に、祝儀袋の水引は蝶結びです。ほどいて結びなおせることから、何度あっても喜ばしい場合にのみ使われます。
意味を理解しておくと、覚えやすいですね!
初盆の場合は、水引の色が白×黒、白×銀、銀×銀などのタイプを使用します。
○不祝儀袋のグレード
中に入れる金額と袋のグレードを合わせるようにしてください。
文房具店などで購入する際に、金額の目安なども書いてありますから、参考にすれば大丈夫です。
渡す時の作法
当日持参する場合は、紫色のふくさに入れて持っていくのが正式です。
直接仏壇にお供えするのでなく、施主様に「御仏前にお供えください。」と差し出します。
ふくさから出し、自分の名前が先方に読めるように持ち替えて両手で持つか、下に置いて両手で軽く押し出すようにして渡します。
[quads id=3]
まとめ
初盆は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆なので、念入りに供養されます。
故人のご家族に気持ちよく初盆を過ごして頂きたいですね。
また、香典の表書きなどのルールはそんなに難しいものではありません。ですが、金額だけでなく、文字を丁寧に書くなど細かいことに気を遣いたいものです。
法事のマナーは、人間関係を円滑にする先人の知恵ですから、基本を押さえておきましょう。
新盆は何と読むか知ってる?
お盆の過ごし方や、常識とされる考え方は、地域によっても違いがあります。少し知識があるだけで、あわてずに済みますよ!
[quads id=5]
[quads id=6]



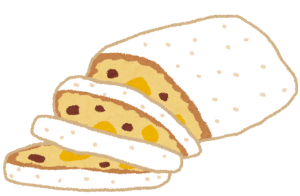

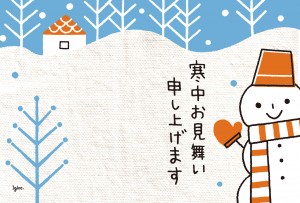

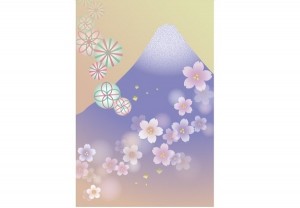

コメント
コメント一覧 (3件)
[…] →初盆に招かれた…!香典の表書きはどう書くの? […]
[…] →初盆に準備する、香典の表書きの書き方は? […]
[…] →初盆に準備する、香典の表書きはどう書くの? […]