テレビなどのメディアで、有名人の方が脳梗塞で入院したというニュースを聞くと、脳梗塞って身近な病気なのかなぁと心配になりますよね。
それが高齢の人の場合もあれば、そうではない若い人の場合もあります。
元気な健康的なイメージで、しかもまだ若いのにどうして?と思ってしまいます。
今回は、脳梗塞の原因と予防について、年代別の違いにもふれながら紹介していきたいと思います。
[quads id=1]
脳梗塞の原因(危険因子)とは?

脳梗塞になる原因としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心臓病などの病気が挙げられます。
また、喫煙、肥満、ストレス、飲酒など生活習慣も原因になります。
高齢者になるほど脳梗塞のリスクが高まるので、日常生活で改善できるものを早めに見直すことが予防になります。
少しでもリスクを減らすために、治療すべき生活習慣病についても、かかりつけ医に相談して治療を進めましょう。
◯そして、普段の生活習慣を見直す
血液をサラサラに保つためには、バランスの摂れた食事や、適度な運動と充分な睡眠をとることです。
また、脱水や急な温度変化も、発作を起こす原因になります。
水分補給や温度にも気を配りましょう。
[quads id=2]
若年性脳梗塞の原因と予防
高齢者に多い病気というイメージもありますが、20代、30代で発症することもあり、さらには10代でも発症する例もあります。
45歳までに発症する場合、若年性脳梗塞と言います。
若年性脳梗塞の主な原因は、高齢者にみられる脳梗塞とは違い、
- 抗リン脂質抗体症候群
- 奇異性脳塞栓症
- もやもや病
など、特異な疾患によるものが多いと言われています。
それぞれどんな病気なのか、順番にご説明していきますね。

○抗リン脂質抗体症候群
抗リン脂質抗体という自己抗体が血液中に出来てしまい、血液が固まりやすくなることで血栓ができてしまう病気です。
とくに血栓ができやすい場所は、足の深部静脈です。
足の一部分に痛みや腫れを感じることがあります。
その血栓が脳に移動すると、激しい頭痛や一過性脳虚血発作を起こします。
- 血栓が心臓に移動した場合は心筋梗塞
- 肺に移動した場合は呼吸不全
など、いずれの場合も命に関わる重篤な病気を引き起こしてしまいます。
○奇異性脳塞栓症
足の静脈などにできた血栓が、卵円孔という心臓の右房と左房の間にある穴を通って、脳の血管に移動して脳梗塞を発症する病気です。
心臓にある卵円孔という穴は、胎児の名残りで成長とともに閉じられます。
しかし、成人の20%ほどの人には残っていると言われているのです。
血液が正常に流れている間は問題ないのですが、
- 重い荷物を持ち上げたり
- 激しい運動をしたり
など、負荷がかかると血栓が卵円孔を通って移動してしまうことがあります。
力を入れた時に一過性脳虚血発作がみられた場合は、早めに受診しましょう。
最近では、心臓内や卵円孔の血栓の有無が分かる検査として、食道を通して行うエコー検査(経食道心エコー)や胸の外側から行うエコー検査(経胸壁心エコー)があります。
○もやもや病
脳の動脈が狭まったり閉塞したりすると、周囲の毛細血管が血流を確保するために拡張します。
血管造影検査ではその様子が網の目のように広がり、もやもやした煙のように見えるため、もやもや病という病名が付けられています。
毛細血管は、細くて弱いので、詰まったり破裂しやすいため、脳梗塞のリスクが高まります。
もやもや病から脳梗塞を発症する場合、その前触れとみられる症状として、
- 笛を強く吹いたり
- ラーメンを冷ますために息を吹いたり
などすると、意識障害や手足の脱力感が一時的に起こることがあります。
これは毛細血管が狭まって脳梗塞に近い状態が起こっている状態です。
○早めに対処すること!
これらの気になる症状がみられた場合は、早めに医療機関で診察を受けることをおすすめします。
血栓を予防するためにもバランスのとれた食生活を送ることがなによりの予防になります。
若いから大丈夫だろうと油断せず、定期的に健康診断を受け、血液検査などを受けるようにしましょう。
まぁいいやという油断が、ちょっとした前触れを見逃してしまう場合もあります。
[quads id=3]
高齢者にみられる脳梗塞
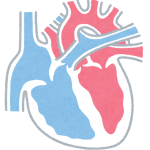
脳梗塞は、脳卒中の種類のひとつです。
日本人の死亡原因第3位が脳卒中で、発症する人は一年で25万人以上と言われています。
細胞に充分な酸素や栄養が行き渡らず、脳細胞が壊死してしまう病気の総称が脳卒中です。
○脳卒中は大きく分けて2つ
脳梗塞
その中でも脳の動脈に血の固まり(血栓)が詰まったり、動脈が狭くなったりする状態
脳内出血
血管が破れて出血した状態
脳卒中の約60%が脳梗塞と言われています。
高齢者にみられる脳梗塞の主な原因は、血管の動脈硬化や心房細動に起因するものが多いと言われています。
糖尿病や高血圧、心疾患や喫煙など長年の生活習慣によって、徐々に脳の血管の動脈硬化が進行した結果、発症してしまいます。
脳卒中をもっと詳しく分類

治療の面や予防的な立場から、次のように分類される場合が多いです。
○アテローム血栓性脳梗塞
頸部から脳にかけての比較的太い動脈が、50%以上狭窄したり完全に詰まってしまう状態です。
食生活の欧米化や加齢、高血圧、脂質異常症などにより、血管に脂肪性物質が付着するアテローム硬化が原因で起こります。
○心原性脳塞栓症
心房細動や心筋梗塞、心臓弁膜症などが原因で心臓に血栓ができ、その血栓が脳に流れて脳動脈を塞ぐことによって発症します。
○ラクナ梗塞
直径が15以下の小さな脳梗塞が該当し、脳の中心部分にある細い血管がつまることによって起こります。
最近は、アテローム血栓性脳梗塞や心原性脳塞栓症が増加傾向であるのに対し、ラクナ梗塞は減少傾向にあります。
[quads id=6]
気をつけたい脳梗塞の6つの症状
脳梗塞の症状は、徐々に進行するものや突発的に発症するものなど様々です。
1)半身麻痺、運動障害、感覚障害
片方の手と足が麻痺して動かなくなったり、片方の手あるいは足だけ動かなくなる単麻痺の場合もあります。
両手両足に麻痺がみられる場合は四肢麻痺と呼びます。
ダメージを受けた場所が右側の脳の場合、左側に麻痺が生じ、左側の脳がダメージを受ければ右側が麻痺します。
手足ではなく、顔の筋肉に麻痺がみられることもあり、口角が片方だけ下がりよだれが出ることもあります。
2)言語障害、失語症、健忘症
- 言葉を話そうとしたときにろれつが回らない
- 何を言っているのか分からなくなる
- 話したいことがあっても言葉が出てこなくなる
- 相手の言葉を理解できなくなる
などの症状です。
周りの人との会話で気付くことが多いです。
3)視覚障害
両目とも視野の半分が欠けて見えなくなる同名性半盲や、物体が二重に見える複視という症状が出ることがあります。
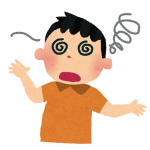
4)平衡感覚の障害
ふらつきやめまいが起こって体のバランスがとれなくなります。
ふらついて転倒したり、めまいや頭痛によって嘔吐することもあります。
5)嚥下障害
口の中の筋肉に麻痺が起こり、舌や喉の動きにも障害が出て、食べ物が普段通りに飲み込めなくなることがあります。
6)意識障害、呼吸困難
すぐに寝てしまったり、話しかけられてもぼんやりしてしまい、適切な受け答えができないことがあります。
また、急に息苦しくなることがあります。
紹介してきたように、脳梗塞の前駆症状には、めまいや頭痛、立ちくらみなど、脳梗塞とは連想しずらい症状もあります。
疲れやストレスかな、と見逃してしまいそうなものもありますが、早めに治療すれば大事に至ることを防ぐことができます。
体に気になる変化がみられたら医療機関を受診するようにしましょう。
異変に気付いたら、1分でも早く病院へ

体の異変に気付き、脳梗塞が疑われる場合は、一刻も早く救急車を呼び正しい診断と治療を開始することが大切です。
発症後3時間以内であれば、血管を詰まらせている血栓を溶かすための薬を使うことができます。
時間が経てば経つほど梗塞部分は拡大して脳のダメージも大きくなります。
脳細胞が壊死する前に、血流を再開させることが何よりも重要です。
まとめ
脳梗塞は、高齢者だけでなく若い世代にも発症するリスクのある病気です。
- 長年の不健康な生活習慣が危険因子になる場合
- 特異な疾患が原因の場合
など、原因は様々です。
さらに症状の現れ方としても
- 突発的に麻痺などの症状が現れる場合
- 無症状の場合
- めまいや頭痛など他の病気と勘違いするような場合
など、見逃してしまうような症状もありますので注意してください。
ただ、脳梗塞が疑われる場合は、一刻も早く治療を開始すれば大事に至らない場合も多いです。
異変に気付いたら迅速に対応できるよう、普段から周りの人と話題にしておくことも大切ですね。
[quads id=5]
[quads id=6]


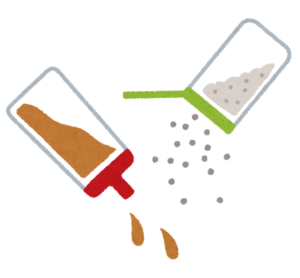
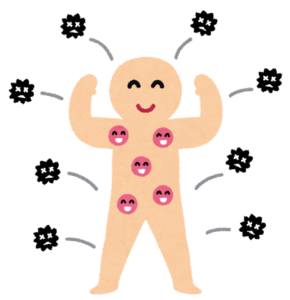





コメント