食中毒による嘔吐や下痢は、年間を通してある日突然、家族を襲います。
食中毒は夏に活発な原因菌もいれば、冬に多い原因菌もいて年間を通して注意が必要なのです。
家族を食中毒から守るために、主婦・ママができる最低限の予防対策を知っておきましょう。
有名な食中毒の原因菌も併せて紹介しますので、参考にしてくださいね。
[quads id=1]
食中毒の原因菌の種類は?

食中毒と一言にいっても、その原因は大きく4つに分けられます。
- 細菌類
- ウイルス類
- 自然毒
- 化学性
自然毒は毒キノコなどの、いわゆる「食べてはいけないもの」を食べたことによって起こる食中毒です。
そして家庭で起こることがほぼないので、馴染みが薄いですが化学物質が原因の食中毒というのもあると頭の片隅にでも置いておいてください。
家庭で気をつけたいのは、細菌性食中毒とウイルス性食中毒です。
この2種類にはとっても有名な菌やウイルスもあるので、名前を知っておくと病院を受診する時やママ友とのおしゃべりなんかでも案外役に立ちますよ。
◯食中毒を引き起こすウイルスの種類は?
有名なものが多いのはウイルス性の食中毒です。
ウイルス性の場合は胃腸炎と言われることの方が多いですね。
ウイルスも数が多いですが、食中毒と同じ嘔吐・下痢の胃腸炎症状を引き起こして症状が重いことで有名なウイルスが以下です。
- ノロウイルス
- ロタウイルス
- アデノウイルス
- アストロウイルス
特にノロウイルスとロタウイルスの嘔吐下痢症状は学校などで流行してあっという間に拡大してしまうこともあるので、流行っている噂を聞きつけたら気をつけたいです。
名前を知らなければママ友たちの会話に出てきても注意できないので、頭の片隅にでも覚えておいて、家族を守るアンテナを張っておきたいですね。
[quads id=2]
◯食中毒を引き起こす細菌の種類は?
食中毒を引き起こす細菌はとっても沢山います。
はっきりいって全部は覚えられません。
食中毒は大抵2〜3日で症状が治まるので、菌を特定するための検査をしている間に治ってしまうことがほとんどです。
そのためほとんどの場合、原因菌を特定することまではしないので病院で細菌の名前を診断されることも稀です。
実際子供が突然嘔吐・下痢をして病院に駆け込んだとしても「なにかの細菌かウイルスに感染したかなぁ」くらいの反応をされることが多いです。
念のため、主な食中毒の原因菌の種類についても知っておきましょう。
◯食中毒の原因になる細菌
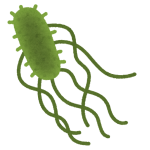
家庭で感染して食中毒を引き起こす可能性が高い細菌は
- サルモネラ菌
- カンピロバクター
- 黄色ブドウ球菌
あたりです。
<サルモネラ菌>
サルモネラ菌は卵なんかに付着している可能性が高い細菌です。
他にもカメなどの爬虫類系のペットから感染する場合も多いみたいです。
細菌の中で比較的症状が重くなるので細菌の名前も有名になってきてますね。
<カンピロバクター>
あと、最近のアウトドアブームの影響で有名になってきた細菌がカンピロバクターです。
肉や井戸水などから感染するため、潜伏期間の1日〜7日以内にBBQなどを行っていたら疑われます。
<黄色ブドウ球菌>
黄色ブドウ球菌は皮膚の常在菌の一つです。
ただ、傷口などで繁殖してしまうので手指の消毒が不完全な状態でおにぎりを作ったりすると菌が増殖して毒素を出し食中毒に繋がります。
黄色ブドウ球菌の場合、1日でケロっと治ってしまうことが多いです。
この3つの細菌は食中毒症状が比較的症状が重くなる原因菌なので、名前が有名になっていますが、名前も知らないような細菌に感染している場合も多いです。
食中毒症状が重く出たら「こいつらが原因かな?」くらいの感覚で受け流しておきましょう。
◯本気でヤバい細菌も
家庭で感染する細菌による食中毒は特別な治療をしなくても治ります。
ただ、嘔吐や下痢といった食中毒症状だけに留まらない、重症化すると本当にヤバい細菌も世の中にはいます。
感染したら保健所が乗り出してきて、集団感染したらニュースで取り上げられるような危ない細菌なので名前だけでも覚えておきましょう。
それぞれ特徴的な症状が出るので、思い当たることがあったら必ず病院へ行きましょう。
- 腸管出血性大腸菌O157
- 腸炎ビブリオ
- 赤痢菌
- コレラ菌
[quads id=3]
食中毒を予防する対策は?

食中毒予防の3原則は
「食品に菌をつけない」
「増やさない」
「殺菌する」
です。
順番に説明していきますね。
◯食品に菌をつけないためには?
まずは食品に菌をつけないために具体的にはこんなことに気をつけましょう。
- 生モノを触ったら必ず手洗い
- 加熱前の食材に使う調理器具(包丁、まな板、菜箸など)を使い回さない
特に調理器具の使い回しは、慌ただしく料理をする中で大変ですが細菌が増える夏場は特に気をつけましょう。
◯家庭内で菌を増やさないためには?
細菌が喜んで繁殖してしまう環境をなくしましょう。
細菌は食べ残しやシンクの水滴などでも繁殖します。
- 食べ残しはすぐに冷蔵庫へ
- 台所の水滴をきれいに掃除しておく
食材の管理も大切です。
買ってきた食材は冷蔵品はすぐに冷蔵庫へしまいましょう。
◯殺菌する
気をつけていても、生肉や台所には細菌が潜んでいます。
細菌を100%排除することはできないので、調理方法で殺菌しましょう。
細菌もウイルスも熱で殺菌することができるので、肉や魚は中心部まできちんと火を通す様にしましょう。
野菜類もできるだけ火を通したいですが、生野菜だって食べたいですよね。
生野菜は冷蔵庫で適切に保管したものを、丁寧に洗うようにしましょう。
調理後も使った調理器具や布巾を熱湯消毒すると、台所で菌が繁殖するのを防ぐことができます。
[quads id=4]
細菌性とウイルス性の食中毒は何が違うの!?
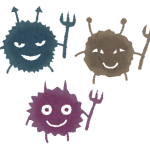
一番大きな違いは、細菌には抗生物質が効果的ですがウイルスには抗生物質が効かないことです。
抗生物質で細菌を退治すれば嘔吐や下痢の症状も治まります。
しかし、ウイルスの場合は体から排出されるのを待つしかないので、ウイルス性食中毒(胃腸炎)の方が治療が大変というイメージです。
ただ、細菌が原因の食中毒でも抗生物質が必要ない程度だったら処方はされません。
発生時期にも違いがあります。
細菌性の食中毒は主に夏場、気温が上がって細菌が繁殖しやすい環境で多く起こります。
ウイルス性は逆に冬場に流行する傾向があります。
ただ年間を通してどちらの種類も感染の危険があるので、食中毒予防は油断せずに行いないですね。
まとめ
食中毒を引き起こす細菌やウイルスの知識があれば、対策も具体的にできますね。
原因菌の対策を知っておくと、家族を食中毒から未然に防ぐことができます。
食中毒・胃腸炎を引き起こす原因の細菌やウイルスを
- 食品に付けないこと
- 家庭内で増やさないこと
- 調理方法で適切に殺菌すること
が家族を守る大切なポイントです。
目に見えない細菌やウィルスなどの原因菌を甘く見ることなく、正しい知識で家族を守っていきましょう。
[quads id=5]
[quads id=6]


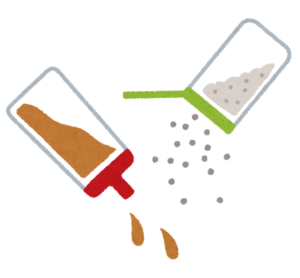
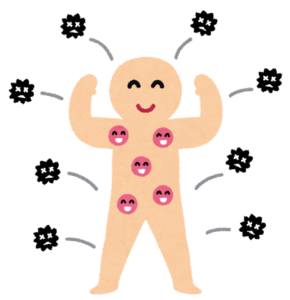





コメント