11月下旬(21日~30日)ともなると、秋と冬の移り変わりを実感する気候が続きますね。
そんな季節に、時候の挨拶に使いやすい言葉をご紹介します。
保護者会や自治会に参加していて、案内やお知らせの文書を作らないといけない時もあれば、親戚や友人への手紙を書く時もありますよね。
ケース別にふさわしい言葉と例文を紹介していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
[quads id=1]
11月下旬での時候の挨拶のポイントとは?

11月下旬では、秋の終わりだけでなく、冬の始まりを表わす言葉というのが代表的です。
11月22日頃は、二十四節気の一つ「小雪」で、雪がチラつく頃という意味の言葉があります。
その他にも「向寒」「霜寒」「初冬」のように、冬に向かっている時期を表す言葉。
そして、「落葉」「時雨」「残菊」といった、11月下旬ごろの風景や天候を表す言葉も、時候の挨拶に使いやすいですね。
[quads id=2]
公式の文書を書くときに使える、時候の挨拶の例文
文書の書き出しによく見られるのが、季節の言葉に「~の候」「~のみぎり」をつける形です。
文書に限らず、冠婚葬祭の招待状や個人宛の手紙にも使える一般的な表現なので、まずは基本として季節の言葉を抑えておくといいですね。
◯書き出しの例文
「小雪のみぎり、保護者会の皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか」
「向寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝にお過ごしのことと存じます」
「~の候」という表現以外にも、幼稚園や学校関係の文書では子供の様子や、季節の言葉を使って時候の挨拶を作ることもできます。
「小雪を迎え、いよいよ寒さが身にしみる頃となりました。皆様におかれましては益々ご壮健のことと存じ上げます」
「子供たちが落葉で遊ぶ姿が見られるようになりましたね。皆様におかれましては健やかにお過ごしのことと存じます」
言葉を足して話し言葉に近づけることで、より親しみが感じられる挨拶文に仕上がりますね。
手紙を書くときに使える時候の挨拶の例文は?
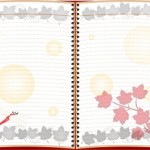
早めに届いたお歳暮のお礼状や七五三の内祝いなど、改めて手紙を出したいときなども時候の挨拶を使うと手紙の書き出しがスムーズになります。
電話をかける時も、まずは近況の挨拶をしてから本題に入りますよね。
手紙での時候の挨拶も同じです。
季節を表す挨拶と体調うかがいなどをセットにして書き始めると、本題にも入りやすくなりますよ。
◯書き出しの例文
「残菊の候、お風邪など引いていないでしょうか」
「ここ数日冷え込みが強まり、早くも初冬の気候となってまいりましたが、お元気でお過ごしでしょうか」
他にも勤労感謝の日や、旬の食べ物などを使っても時候の挨拶を作ることができます。
◯結びの例文
「これからの冬支度にお忙しいとは存じますが、お風邪など召されませぬようお気を付け下さい」
「こちらは勤労感謝とは名ばかりの忙しい連休を過ごしました。○○さんもどうぞご自愛くださいね」
[quads id=3]
まとめ
時候の挨拶というと、文書や手紙を書くときに必要な文法という、堅苦しいイメージがありますよね。
変なことを書かないようにと身構えてしまうこともあるかもしれませんが、実際はそんな難しいものではありません。
11月下旬は、冬に入る直前の季節ということを意識すればいいだけです。
また、身近な生活で感じる季節を素直に表現するだけでも時候の挨拶になります。
「ニット」「マフラー」「ストーブ」など、冬に向けての準備に登場するキーワードがたくさん見つかるはずです。
親しい間柄の人に送る手紙には、あなたらしい時候の挨拶を書いてみると、ステキな手紙になりますよ。
11月中旬の時候の挨拶
→【時候の挨拶】11月中旬の言葉と例文!秋の季節ももうすぐ終わり!
12月初旬の時候の挨拶
→【時候の挨拶】12月上旬の季節の言葉は?お歳暮の添え状の例文も!
文書の場合は季節の言葉を参考に、手紙などの場合は相手に話しかけるのと同じような感覚でオッケーです。
季節の変化を改めて味わういい機会でもありますから、ぜひ楽しみながら時候の挨拶を書いてみてくださいね。
[quads id=5]
[quads id=6]

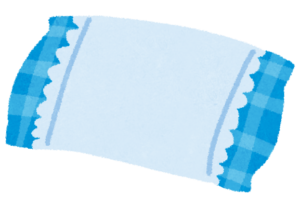







コメント
コメント一覧 (2件)
[…] →時候の挨拶で11月下旬に使える言葉は?秋から冬に変わる季節! […]
[…] →時候の挨拶で11月下旬に使える言葉は?秋から冬に変わる季節! […]