冬から春先にかけて、主に子どもたちの間で感染が流行する水疱瘡。いつからいつまでが感染力があるのかって案外知らないものです。
学校などで水疱瘡の発症が出た時の注意点や潜伏期間など、感染の可能性がどのくらいあるのかも把握しておきましょう。
感染力がある期間を知っていれば、兄弟間での二次感染の注意もしやすくなります。
[quads id=1]
水疱瘡の潜伏期間と感染期間
水疱瘡は感染してから発症(発疹がでる)まで2~3週間の潜伏期間があるといわれています。
そのため症状が出た日から遡って、2~3週間まえから感染していたことになります。
強い感染力があるのは、発疹がでる1日前~水疱がかさぶたになるまでの約7日~10日間とされています。
しかし、潜伏期間中も菌を保有しているため、人にうつす可能性はゼロではありません。
ポイントは発疹がでる1日前から強い感染力があることです。
発疹が出るまでは症状が出ないことが多く、通園・通学を通常通りしていることがほとんどです。
そのため学校などでは集団感染がよく起こります。
[quads id=2]
水疱瘡になったら出席停止
発症が分かってからかさぶたになるまでの期間(およそ7日~10日)は、学校保健法により出席停止と定められています。
出席停止の解除には医師の診断が必要です。
通園・通学していない未就園児なども、この期間中は不必要な外出を控えるようにしましょう。
他の学年やクラスで水疱瘡の生徒がでた時の注意点
生徒が休む1週間前までに、全校集会など体育館で集まる機会があったかを確認しましょう。
前日でなければそこまでの心配はいらないかもしれません。
しかし、マスクなど空気感染を予防する対策を始めるといいですね。
ただ生徒が休んだ理由を全生徒に連絡してくれる学校は少ないでしょうから、過度に敏感になる必要はないでしょう。
同じクラスの子が水疱瘡で休んだ時の注意点
席が離れていたり、接触の少ない子であればあるほど感染の可能性は下がります。
冬は特に教室を閉め切っていることが多いので、寒い時期ほど空気感染の危険が高まります。
隣の席や、よく遊ぶ子の場合は感染が濃厚になってきます。
発症するまで休む必要はありませんが、最初の子の欠席から3週間は発疹が出ないか注意しておくと良いでしょう。
家族に水疱瘡が出たら?
最初に発症に気づいた時点で、既にほかの家族も感染している可能性が非常に高いです。
発症するまで外出を控える必要はありませんが、家族の他に感染源が見当たらない場合は、特に発症から14日後以降は発症のサインを見逃さないよう注意しましょう。
また、感染から72時間以内に予防処置を行うと、ある程度の効果があるとされています。
感染が心配な兄弟等がいた場合は予防について、小児科に相談してみるのもいいでしょう。
[quads id=3]
まとめ
水疱瘡の感染で脅威なのは、発症する前1日、2日も強い感染力を持っていることです。
感染者本人も気がつかないまま、ウィルスを持ち込んでしまっているので周りで流行の兆しを感じたら早めに予防をすることが肝心です。
また、感染拡大を防ぐためにも、感染力がなくなるとされる期間までは外出をせずにいるよう注意しましょう。
水疱瘡の感染経路についても、確認しておきましょう。
→水疱瘡は空気感染する?感染経路を知って家族を守ろう!
水疱瘡の初期症状を見逃さないようにしましょう。
→水疱瘡の初期症状とは!子供の急な発熱は注意が必要?
水疱瘡についての知識は、子供を持つ親ならぜひ知っておきたいところです。普段の風邪と見極めることが、被害を最小限に抑えるコツですよ。
[quads id=5]
[quads id=6]


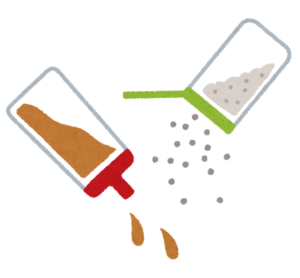
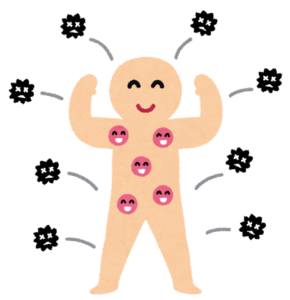





コメント