誤嚥性肺炎の症状は、一般的に言われている肺炎とは違います。
それは、誤嚥性肺炎は飲み込んだ食べ物などが誤って気道に入り、その食べ物などに付着していた細菌が肺に感染しておこる肺炎だからです。
誤嚥性肺炎は、空気感染はありませんので感染症としてはあまり危険ではありません。
しかし、気付かずに放っておくと重症化してしまい、高齢者や赤ちゃんの場合は死に至る場合もあるので注意が必要です。
早めに対処できるように、誤嚥性肺炎の症状は知っておいてくださいね。
[quads id=1]
誤嚥性肺炎の5つの症状とは?
肺炎と聞くと「高熱、咳、痰」という症状が思い浮かびますよね。
しかし、高齢者や赤ちゃんに起こる誤嚥性肺炎には、これらの症状が見られない場合があり、そのため発見が遅れます。
また、赤ちゃんは自分で症状を伝えることができませんし、高齢者は風邪の初期症状と思い込み、辛くても我慢することを選び、どちらも重症化してしまいがちです。
もし以下の5つの症状が見られる時は、誤嚥性肺炎の可能性があります。
・食欲不振
・顔色がすぐれない
・呼吸に雑音が混ざる
・痰が絡むような咳が出る
誤嚥性肺炎の怖いのは、大したことがないと思い込んでしまいがちなところにあります。
もし上記の症状がいくつか当てはまるようでしたら、早めに医者の診察を受けることをオススメします。
また、知らず知らず誤嚥を起こしやすい生活を送っている場合もありますが、そんな方は誤嚥性肺炎の可能性が高まります。
どんな方が起こりやすいのか、高齢者の誤嚥の原因と、赤ちゃんの誤嚥の原因を、それぞれしっかりと理解しておきましょう。
高齢者の誤嚥性肺炎はこんな方が注意…

平成23年には肺炎が死因の第3位になりましたが、高齢者の肺炎の多くは、普通の肺炎ではなく、誤嚥性肺炎と言われています。
70歳以上の肺炎の場合は70%以上が誤嚥性肺炎だそうです。
高齢者の中でも、この誤嚥性肺炎を起こしやすい方には特徴があります。
・咳の反射が低下している
・口腔内が清潔に保たれていない
・胃液が逆流しやすい
・泥酔して入眠した
・睡眠薬を常用している
上記のどれかに当てはまる方は特に注意が必要です。
誤嚥性肺炎を発症するプロセスとは
本来、人間は食べ物が喉を通る時に、食べ物が気管に入らないように脳が気管を塞ぐ指令を出します。
しかし、高齢者の場合は、その指令が遅れることで、気管に食べ物が入ってしまう場合があります。
そうすると、食べ物や唾液が含まれた細菌と共に気管から肺に入り、肺で炎症をおこす原因になるのです。
誤嚥を防ぐために
誤嚥を防ぐためには、食事中のちょっとした工夫でリスクを減らすことができます。
1)食事の際は前かがみの姿勢をキープする
ベッド上で食事をする場合は、特に注意が必要です。上向きだと誤って食べ物が気道に入り込みやすいです。
2)飲み込みやすいものを食べる
食べ物を細かく刻んだり、柔らかく煮るなど、食べやすく調理を工夫することで、ご縁のリスクを減らすことができます。
また、とろみを付けることで飲み込みやすくなります。
こんな時にも発症する!?

実は、寝ている時に、発症することが多いのも高齢者の誤嚥性肺炎(不顕性誤嚥)の特徴です。
唾液が気管の方に垂れてきて、いつの間にか肺の方に細菌が入り込み、肺炎を発症してしまうのです。
脳血管障害や認知症の方の場合は、嚥下障害になりやすいため、特に注意が必要です。
認知症の予防に効果的なサプリがある
健康な血液を保つことと、認知症の予防には密接な関係があります。
というのも魚に多く含まれているDHA&EPAを摂ることが、予防に効果があることが分かっています。
そのため、認知症のサプリを飲む人も増えてきていますよ。
感染リスクを減らすために!
口腔ケアが不十分でに細菌が残っている場合は、唾液の中にも細菌が混じってしまいます。
ですから気管に唾液が入り込んでも感染しないようにするには、口腔内を清潔に保つことが最大の対策と言われています。
睡眠の前には、歯ブラシでよく磨くだけでなく、ガーゼやスポンジブラシを使いながら口腔内に残る食べ物のカスや余分な水分を取り除きましょう。
[quads id=2]
赤ちゃんに起こる誤嚥性肺炎の原因は?

赤ちゃんは身体の機能が未発達なために、うまく食べ物を飲み込めず、誤って気管に入ってしまうことがあります。
気管に入った直後はゴホゴホとむせた後、すぐにケロッとしてしまうこともあるので、意外と気付くのが難しいんですね。
また、咳が直後から出るわけではないので「肺炎は咳がひどいものだ」と思い込んでいると、治療が遅れてしまうことがあります。
いつの間にか、急に咳き込んだり、咳が止まらなくなったり、いつもと違う変な咳が出る、という症状が見られたら、誤嚥性肺炎の可能性がありますよ。
どんな治療が必要?
病院では、聴診器で肺の音を確認し、胸部X線で異物を確認する検査が行われます。
もし異物があれば、内視鏡を使って取り除き、抗生剤で肺炎の治療が行われます。
対処が遅くなるほど回復にも時間がかかってしまいますので、「もしや!」と気になった時は、早めに医療機関に連れて行くようにしましょう。
誤嚥を防ぐための対策

よく見られる赤ちゃんの誤嚥の予防には、下記のような対策があります。
1)調理を工夫する
・丸呑みしてしまうサイズの食べ物は細かく切る
また、絶対ダメ!というわけではないですが、ピーナッツなどの豆類は誤嚥の原因になりやすいので、与える時は注意するようにしましょう。
2)食事の時間には赤ちゃんを観察する
・食事に集中させる
注意散漫な状態で食べ物を口に入れてしまうと、誤嚥の原因になりやすいです。
できるだけ食事はあわてて取らないようにし、赤ちゃんの食事の様子をしっかりと観察するようにしましょうね。
[quads id=3]
まとめ
機能の低下が著しい高齢者、または機能が未発達な赤ちゃんにとって、誤嚥性肺炎を起こすことは決して珍しいことではありません。
いつもと様子が違ったり、気になる症状が出ていたら、早めに医者に診てもらいましょう。
また、誤嚥性肺炎は少しの注意で未然に防ぐことが可能なものです。
今回、ご紹介した対策は今日からできることですから、ぜひ意識して頂きたいと思います。
何事も早めの対応を心がければ、予期せぬ出来事がおきても慌てずに済みますし、重症化する前に対処することができますよ。
誤嚥と誤飲の違いを説明できる?
誤飲と誤嚥は似ていますが、対処法も異なりますよ。いざという時に家族を守れるよう、一度は目を通して頂きたいと思います。
[quads id=5]
[quads id=6]


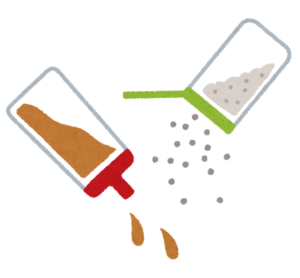
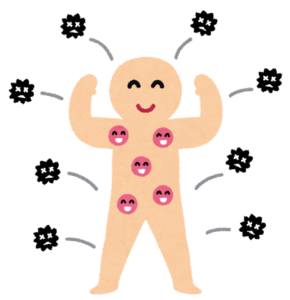





コメント
コメント一覧 (2件)
[…] →誤嚥性肺炎の症状5つ!高齢者と赤ちゃんは特に注意が必要! […]
[…] →誤嚥性肺炎の5つの症状!高齢者と赤ちゃんは要注意 […]