一般的に子供に虫歯があるかどうかの見分け方は、意外と判断しにくいかもしれません。
たまたま歯科検診を受けた時に、初めて虫歯があるのに気が付く方も少なくないでしょう。
子供の虫歯の感じ方は大人と異なるため、見落としてしまいがちなんですね。
しかし、虫歯になっているかどうかの見分け方は、いくつかのポイントがあります。
子供の歯の健康を守るために、チェックポイントを押さえておきましょう。
[quads id=1]
子供の虫歯を見分ける4つの方法

子供の虫歯を見分けるには、次のような特徴を理解しておくと、早く発見することができます。
1)痛みがそれほど感じられない
幼児は、まだ身体の機能が未発達なため、感覚として痛みを感じにくい場合があります。
例えば、トイレトレーニング等でも、なかなかトイレに行きたい感覚がつかめないこともありますね。
虫歯の穴が大きくなって、そこに食べカスが入って、初めて痛みを感じることもあるのです。
つまり、痛みがない=虫歯がないは、必ずしも当てはまらないので注意が必要です。
2)虫歯だけど白い
大人の虫歯は黒くなりますが、乳歯は白いまま、中で虫歯になっていることが特徴です。
実は、白い虫歯は進行が早く、あっという間に悪化します。
中には、進行がゆっくりとしている黒い虫歯もありますが、乳歯はやわらかいので、白いまま虫歯になるケースがほとんどです。
他の症状とも合わせて、よく子供の行動を観察しましょう。
3)歯茎と歯の境目が痛い
子供に歯磨きしてあげている際に、歯と歯茎の間に歯ブラシをおくと痛がる場合は、虫歯になっている可能性があります。
虫歯になっている時は、歯茎は帯状になり、歯が白く濁って見えます。
4)食べ方がいつもと違う
虫歯が初期段階であれば、幼児は痛みを感じません。
しかし、進行していくと、食べる際になんとなく違和感を感じるようになります。
噛んでいる側を変えたり、食事を拒否したりする際は、虫歯の可能性もあります。
子供のボディランゲージに注目しましょう。
[quads id=2]
早期発見のために、虫歯になりやすい場所をチェック
虫歯を見分けるには、虫歯になりやすい場所を特によくチェックしておくことも大切なことです。
汚れが残りやすい場所はある程度決まっていますよ。
○奥歯の歯間
大人だけでなく、子供も虫歯ができやすい場所は、奥歯の歯間です。
歯ブラシをきちんとしたつもりでも、歯間にたまった食べ物のカスなどが残っていることがあるのです。
デンタルフロスなどを使って、きれいにしてあげたいですね。
○奥歯の溝
大人でも同じですが、奥歯は歯間だけでなく、溝にも虫歯菌が繁殖しやすいです。
歯磨きをしているつもりでも、しっかりと奥まで届いていないことが多いので、正しい歯磨きをしてあげたいですね。
○上あごの前歯の歯間
上あごの前歯の歯間も、虫歯になりやすい箇所です。
特に、哺乳瓶でミルクやジュースなどをまだ与えられている幼児は、この場所が虫歯になりやすくなります。
○歯と歯茎の間
歯と歯茎の間も、細かく手を動かして、丁寧に磨いていないと虫歯になりやすい場所です。
子どもの虫歯!7つの原因と対策!

子供がなぜ虫歯になるのかを知ることで、虫歯を予防することができます。
歯を観察することで、見分ける方法だけでなく、普段の生活習慣もチェックしましょう。
そうすることで、そもそも虫歯になりにくい口内環境を整えてあげることができますよ。
1)甘いもの→虫歯
子供の味覚の変化も、成長段階では欠かせない特徴です。
赤ちゃんのうちは、ミルクだけだったのが、それから少しずつ食事をするように進んで行きます。
そのうち、おやつ等の甘いもの味覚も感知して行くと食べる機会が増え、甘いものが食べたいという欲求が出てきます。
その時は、注意が必要ですね。
甘いものを口に入れる頻度が高いと、虫歯も出来やすくなってしまいます。
2)遺伝的に歯が弱い
歯も身体の一部ですので、毎日、歯の手入れを欠かさない、定期的に歯医者で検診を受けるなどをしていても、遺伝で虫歯になりやすいのです。
ただ、生活習慣を見直すことで虫歯を作りにくい口内環境を作ってあげることは可能です。
正しいデンタルケアを小さい時から教えてあげるようにしましょう。
3)歯の磨き方が足りない
歯の磨き方が足りないと、奥歯や歯間に歯垢が残ってしまい、虫歯の原因となります。
歯ブラシだけでは、どうしても歯間に汚れが残ってしまいます。
特に寝る前に歯磨きの後にフロスをしないと、虫歯の原因になってしまうのです。
実は、歯ブラシで磨いたところで、60%程度しか汚れを落とせていなません。
小さな歯の間を磨くためには、デンタルフロスを使って丁寧に汚れを落としたいですね。
フロスを使用することで、80%の汚れを落とすことができます。
4)夜寝る前の歯磨きは特にしっかりと
虫歯菌は、夜寝ている時に一番アクティブになります。
また、寝ている時は唾液の分泌量が少なくなり、口内が乾燥してしまうので虫歯菌が増える環境になります。
唾液の分泌量(成人)
- 安静時 0.2~0.5 ml/分
- 睡眠時 0.1 ml/分以下
口に食べものが入ってこないため、刺激が少ないんですね。
さらに鼻が詰まっていて口呼吸をしている時は、いっそう乾燥するため虫歯になりやすくなります。
夜寝る前の歯磨きは、特に念入りに行いましょう。
[quads id=6]
5)歯磨き粉の量は多めで使う
歯そのものを強くすることも大事です。
最近ではフッ素入りの歯磨き粉が多く売られていますよね。
フッ素は虫歯菌の進行を抑え、口の中に長くとどめることで歯を強くします。
歯全体に行き渡るように多めに使って、ゆっくりと磨きましょうね。
何度もゆすぎ過ぎるとフッ素が取れてしまいますので、ゆすぐのは1~2回くらいにしておきましょう。
6)食べものの内容も考える
糖分をよく取っている子供の歯は溶けやすく、すぐに虫歯になってしまいます。
糖分が多く含まれているおやつや飲み物を、好きなだけ与えたら子供が困ることになりますよ。
虫歯になりにくい食べ物を選ぶことも大事ですね。
また、食事やおやつの時間をしっかりと決めておくようにしましょう。
少量のおやつをダラダラと続けて食べさせるよりも、決められた時間にまとめておやつを食べるほうが、虫歯の進行を抑えられます。
注意したいのはやはり、甘いもの。
「糖」は虫歯菌も大好きです。甘いものを食べさせるならキシリトールがいいですね。
食後にキシリトールのラムネを舐めるようにすれば、唾液も出て虫歯の進行を抑える効果が期待できます。
ちなみに、唾液には、酸性寄りの口の中を中性に戻す作用があります。
7)定期的に歯の検査を行う
日頃からどんなに歯のケアをやっていても、定期的に歯科検診に行くことをオススメします。
特に子供の場合、歯間が虫歯になっているのに気がつかないケースが非常に多いためです。
定期的に歯科検診に通っていると、虫歯の早期発見ができ、大きな虫歯になる前に対処することができます。
[quads id=3]
虫歯菌が嫌がる口内環境とは

虫歯になるメカニズムは、まず口の中の虫歯菌が歯に残った食べ物のカス(歯垢)を分解します。
その時に虫歯菌が出す「酸」が歯を溶かしているのです。
虫歯菌が好む口内環境だと虫歯は早く進んでしまいますし、虫歯菌が嫌がる環境を作ると虫歯の進行は抑えることができます。
・唾液を出すこと
・食事の時間を空けること
・フッ素入りの歯磨き粉を使う
これらの対策が、虫歯菌が嫌がる環境を作るポイントです。
口の中は中性を保つこと
通常は、口の中は弱アルカリ性から中性で保たれています。
しかし、炭水化物や糖分を摂ると口の中が酸性になり、石灰が溶けていきます。
つまり、虫歯が進行しやすい状態になるのです。
逆に、口の中が酸性でない時間には、歯の再石灰化がおこなわれ、少々の傷はふさがっていくのです。
ということは、口の中を中性にする時間を確保することが非常に大事になるわけです。
ですから、
- 食事の間隔を空ける
- 食べても酸性にならない食べ物をおやつに出す
などの工夫をしましょう。
しっかりと食事の間隔を空けたとしても、ジュースを飲んだら糖分を含んでいるので、口の中が虫歯になりやすい酸性の状態になってしまいますよ。
糖分を摂らない時間を3時間はしっかり空けることを心がけたいですね。
まとめ
子供の虫歯の見分け方は、大人とちょっと違うので、親がしっかりと観察してあげたいですね。
虫歯の発見が遅れてしまうと、急に歯が痛みだして、子供が一晩中泣くこともあります。
そうなってしまうと、子供だけでなく、親もつらい思いをしてしまいます。
・子供の虫歯の見分け方を知って、早期発見を心がけること
・日々の歯のケアを真剣に考えること
この2点を、パパとママで協力して気をつけてあげたいですね。
小さい子供のころから、正しいデンタルケア習慣を身につけると、一生虫歯のできにくい歯になりますよ。
虫歯予防に効果がある食べ物ってなに?
→虫歯予防に効果のある食べ物!幼児の歯を丈夫にするコツとは?
虫歯を見分ける前に、虫歯を予防するのが一番ですよね。歯の健康に役立つ習慣を身につけたいですね!
[quads id=5]
[quads id=6]




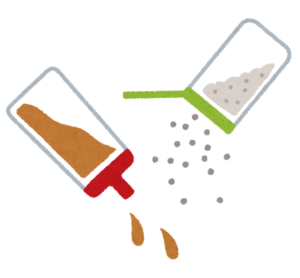
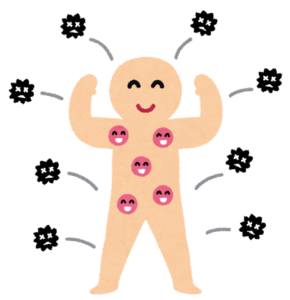





コメント