セミが鳴くと夏を感じますよね。
毎日、セミの鳴き声を聞いていると、
- 一体どうしてあんな大きな鳴き声が出るのか
- セミは何のために鳴いているのか
不思議ですよね。
また、セミは明るい時間にだけ鳴くと思っていたのに、最近は夜も鳴き声を聞くことがありませんか?
考えてみると、セミの鳴き声には色々な疑問がわいてきます。
今回は、セミが鳴く仕組みや、鳴き声の謎についてお伝えします。
[quads id=1]
セミが鳴く仕組みは2つ

セミは、鳴く仕組みは2つあります。
◯羽を使って音を出す
一つ目の仕組みは、他の昆虫がするように羽を使って音を出す方法です。
鈴虫などは、羽どうしをこすり合わせる摩擦で音を出しますが、セミは羽をお腹にこすり付けることで音を出します。
◯お腹全体で音を大きくしている
2つ目は、セミが大きな鳴き声が出せる仕組みになります。
セミの体の中には、お腹側に音を出す器官である発音膜とそれを動かす発音筋があります。
発音筋は発音膜を細かく動かすことで音を出しますが、それだけではあの大音量は出せません。
セミのお腹は大きな空洞になっていて、共鳴室と呼ばれる部分があります。
発音膜で発生した音が、共鳴室の空気を震わせてさらに大きな鳴き声にしています。
[quads id=2]
セミはオスしか鳴かない

◯オスだけ、鳴く器官が発達している
オスのセミの成虫は、発音膜、発音筋、共鳴室の大きな声で鳴く器官が発達していますが、メスは発達していません。
メスのお腹の中は、大きな卵巣があります。
つまり、セミはオスしか鳴かない、鳴くことができないのです。
◯求愛のために鳴く
なぜオスだけが鳴くのでしょう。
それは、求愛のためです。
他のセミより大きな鳴き声で鳴くことで、自分の存在をアピールし、自分に合ったメスを見つけ子孫を残すために鳴いています。
さらに、メスが鳴かないのも子孫を残すためだと考えられています。
大きな鳴き声を出せば、存在をアピールすることができます。
しかし、裏を返せば、外敵に見つかりやすいということです。
子供を産まなければならないメスは、そのリスクを背負わないために鳴かないのです。
セミが鳴く条件とは!気温が関係ある?

日本ではセミは夏しか鳴きませんよね。
セミは暑い時、気温が25℃前後でたくさん鳴く傾向があり、気温の影響を受けます。
セミの種類によっても影響を受けやすい気温が違っているので、1日を通して気温が変化すると、セミの鳴き声は違ってきます。
例えば、ヒグラシは気温が低いと鳴き始めるので、涼しい朝方や夕方に鳴きます。
また、明るさにも影響を受けます。
日本では、夜中ではなく、朝から夕方にかけて鳴くことが多いです。
[quads id=3]
最近の異変!夜の時間にセミが鳴いている!?
都会に多いのですが、夜中にセミの鳴き声が聞いたことがありませんか。
この理由は、主に2つ、先にお伝えした、セミが鳴く2つの条件「気温」と「明るさ」です。
最近は、夜になっても気温が下がらず、熱帯夜が続いています。
特に都会では、ヒートアイランド現象が起こり、湿度も温度も高いまま夜でもセミが鳴く気温ままです。
また、都心は、街灯やネオンが夜遅くまでたくさんついているため明るいですよね。
そうすると、セミは今が夜だと分からず、昼と勘違いして鳴き続けます。
この現象は、15年ほど前から見られるようになり、小学校の教科書にのるほど注目されています。
◯実はセミは夜行性
セミが夜中鳴いていると、生態系はどうなるのかと少し気になります。
でも、実はセミは、形態学上はカメムシ目で、カメムシの子孫です。
カメムシは夜行性のため、セミも、本来は、夜行性で夜鳴く性質がありました。
小さいセミが昼間鳴くと、外敵の鳥に襲われやすいですが、夜だと見つかる危険も少ないですよね。
セミが多く生息するタイでは、夜鳴くのが常識なんですよ。
しかし、海を渡り移動する過程で、熱帯で生活していたセミが、寒冷地に対応する進化をとげ、昼型に変化したと考えられています。
[quads id=4]
まとめ
セミが大きな声で鳴くのには、色々な仕組みや意味があるんですね。
時々、セミの抜け殻を見ると、どこかで頑張って鳴いているんだなという気分になります。
鳴き声をうるさいなと感じることがありますが、セミの生きている証拠なんだと思うと応援したくもなります。
今年は、いつぐらいまでセミが鳴くのか、天気にも注目していきたいです。
[quads id=5]
[quads id=6]

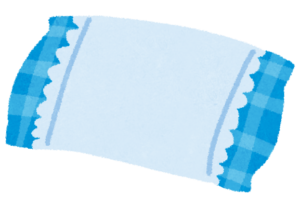







コメント