2月下旬となると、増えてくるのが大学や高校合格の知らせです。受験を終え、頑張った孫に、親戚の子に合格祝いを考える時期ですね。
ここでは合格祝いなどで使える、2月下旬に使う時候の挨拶を例文付きで紹介します。
また、合格祝い以外にも使える、季節の表現もあるので参考にしてみてください。
[quads id=1]
2月下旬は20日前後から
2月20日前後から月末までを、一般的に下旬とします。でも、手紙においては厳密な区切りはありませんので、目安として考える程度でOKです。
また2月19日が「雨水」という二十四節気のひとつにあたります。19日以降は水がぬるくなって春の訪れが近いという目安の日にちになるので覚えておきましょう。
2月下旬の時候の挨拶の使い方
2月下旬は地域や年度によって寒暖の差があります。身の周りの季節感に合った言葉を選びたいですね。
暖かさを感じてきたら
「雨水」「向春」「三寒四温」「早春」「解氷」「梅花」
まだまだ寒いと感じるときは
「春寒」「寒風」「残寒」「余寒」などがよく使われます。
合格祝いを贈りたい時の例文
子どもの受験を支えたご両親に、お祝いのメッセージを送る時はこんな感じでどうでしょう。
両親宛への手紙
「三寒四温の候、この度は○○君(ちゃん)が志望校に合格したとのこと、お慶び申し上げます」
ではじめ、
「朝晩はいまだ残寒を感じさせます、ご家族皆様お風邪など召しませぬようお気を付け下さい。」
で結びます。
第一志望以外の合格の場合は、ねぎらいの言葉を加えるといいですね。
「寒風なお去りがたき折、変りなくご健勝のことと存じます。この度は○○君(ちゃん)の受験を無事に終えられたとのこと、ほっと一息つけますね。」
ではじめ、
「余寒の折、くれぐれもご自愛ください」
で結びます。
子ども本人に宛てる手紙
大人からの手紙のマナーとして挨拶をいれて書けば、子ども自身も大人気分を味わえますね。
「梅花のほころびをみつけ、やっと春の足音が近づいてまいりました。志望校合格の知らせを受け、喜びにあふれていることでしょう。」
ではじめ、
「残りの中学生活を満喫し、良き春を迎えられますようお祈りしています」
で結びます。
合格祝い以外にも時候の挨拶はそのまま使うことができます。季節感にマッチした挨拶を使うようにしましょう。
[quads id=2]
合格祝いをもらったお礼にも!
お祝いのお礼では、本文も時候の挨拶と文体を合わせて書くように心がけると、手紙が引き締まります。
「受験シーズンも終わり、春が近づいてまいりました。この度は○○にお祝いを頂戴し、誠にありがとうございます。」
ではじめ、
「向春の折、お互い良き春が迎えられることをお祈りいたします」
で結びます。
春は始まりの季節でもありますから、新たなスタートについて触れてみるのもおすすめです。
[quads id=3]
2月下旬は春を意識したい時期
2月下旬は冬の終わりが見え始め、春を意識した言葉も多く使えます。梅の花や、水溜りの氷など、手紙を書く前に一度外に出て季節を体感するのもいいですね。
おめでたい手紙にはまだ寒い季節ながらも、春を思わせる手紙で華を添えましょう。
2月中旬を表現したい場合
まだ寒い日が続く場合は、2月中旬の時候の挨拶がふさわしい場合もありますね。
→2月中旬の時候の挨拶で使える言葉は?季節感を意識しよう!
3月上旬を表現したい場合
地域によっては、2月下旬でも3月のような春の陽気が感じられる日もあるでしょう。
そんな3月上旬の季節感を表現したい時は、こちらを参考にしてくださいね。
→時候の挨拶で3月上旬に使える例文!季節を感じる言葉とは?
3月も上旬になると花もつぼみを付け始め、本格的な春はもう間近ですから、なんだか気分もウキウキしてきますね^^
[quads id=5]
[quads id=6]

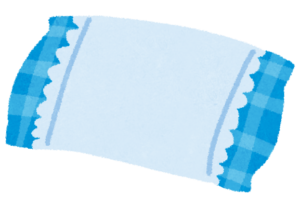







コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 2月下旬の時候の挨拶はこちらにまとめています。→時候の挨拶で2月下旬に使える言葉!合格祝いの例文などに便利! […]
[…] →時候の挨拶で2月下旬に使える言葉!季節を感じる例文も! […]