溶連菌は秋~春先にかけて流行しますが、夏に感染することもあります。
子供がいる方には割となじみがある病気なので、知っているという方が多いかもしれませんね。
実は、この溶連菌は子供だけでなく大人にも感染の可能性があります。
そして、一度だけという病気ではなく、再発することもありますので、症状や原因を正しく知っておくことが大切です。
[quads id=1]
溶連菌が大人に感染する感染経路

溶連菌感染者の多くは4歳~15歳くらいまでの子供ですが、大人にも感染します。
感染経路はこの2つです。
- 飛沫感染(咳やくしゃみ)
- 経口感染(菌に触れた手を口に入れるなど)
保育園・幼稚園・小学校に通う子供が感染してきて、家庭内で家族に感染することが多いです。子供が溶連菌に感染した場合は、子供と同じ食器を使う事は避けましょう。
また、同じタオルを使わないように気をつけたり、普段よりも手洗いうがいに気をつけたいですね。
大人に感染するのはどんな時?

健康な大人ならば免疫力があるため、感染したとしても発症しないまま自然治癒してしまうことが多いです。
ただ、風邪や疲労などで免疫が落ちている時は要注意です。
また、妊婦の場合も免疫が低下しているので、家族で感染が確認されたらマスクでの予防を徹底しましょう。
ストレスが溜まっていたり、食生活が乱れたりすることで、免疫力は落ちてしまいますので、普段からの生活を見直すことが大切です。
[quads id=2]
溶連菌感染症の基本的な症状
- のどの痛み、腫れ
- 発熱(38度以上)
- 嘔吐
- かゆみを伴う発疹
- イチゴ舌(舌に苺のようなブツブツができる)
正式名称はA群β溶血性連鎖球菌といい、赤血球を壊してしまう細菌です。
特に喉の腫れは特徴的で真っ赤に腫れてしまいます。
皮膚の薄い子供の場合はほっぺが赤くなることも多いです。
大人が発症すると高熱が続くことがあるようです。
溶連菌感染症は合併症が怖い

発熱や咳、喉痛みが特徴の溶連菌感染症は、抗生物質をきちんと飲めば、治ることがほとんどです。
ですが、
「薬をすべて飲みきってください」
「2週間後に完治したか検査をします」
と医師から言われることもあります。
これは、菌を確実に消えたかどうかを確認して、合併症を防ぎたいからです。
溶連菌感染症は合併症を引き起こす危険性が高く、中には死に到るケースもあります。
◯劇症型レンサ球菌感染症(劇症型溶連菌感染症)
溶連菌感染症の合併症の中には、あっという間に命を落としてしまう、「人食いバクテリア」と呼ばれる合併症があります。
それが、劇症型レンサ球菌感染症です。
怪我をしたところや分娩中に皮膚や筋肉に感染すると、あっという間に傷口が広がり、皮膚が死んでいきます。
進行が早いため、素早い手術で壊死した組織を取り除き、抗生剤を投与しなければなりません。
数十時間で30%ほどの人が死亡する、とても危険な病気です。
◯急性糸球体腎炎
急性糸球体腎炎は溶連菌感染症を発症してから1~2週間後に血尿や蛋白がでる腎臓の病気です。
治療すれば治る病気で、症状が軽い場合は自然に治ることもあります。
しかし、重症化すると入院が必要なケースもあります。
溶連菌感染症が完治したか尿検査を受け、早期発見をすることがとても大切です。
[quads id=3]
◯血管性紫斑病
血管性紫斑病は、溶連菌に限らず、色々な細菌やウイルス感染によって起こる血管の炎症です。
「アレルギー性紫斑病」「アナフィラクトイド紫斑病」「シェーンライン・ヘノッホ紫斑病」と言われることもあり、子供が発症しやすい病気です。
主な症状
- 紫斑…足や腕などにかゆみがある蕁麻疹のようなものができ、赤紫色のアザ(紫斑)ができる。
- 関節炎…足や手の関節に痛みや腫れがでる。両方の足や手にできることが多く、歩けないほどの痛みがでる場合も。
- 腹痛…激しい腹痛は50%以上の人に現れる。同時に、血便、嘔吐の症状がでることも。
- 腎炎…紫斑が出でから3~数か月後に血尿や蛋白尿が見られる。自然に治ることほとんどだが、まれに腎不全の原因になることもある。1年後に発症することも、紫斑が出たときは定期的な検査が必要。
これらの症状を治す専用の薬はなく、数週間、安静にしておくことで治療します。
痛みがある時は、痛み止めやステロイド剤を使うこともあります。
◯リウマチ熱
リウマチ熱を発症すると、まず発熱が起こり、次に体のだるさ、疲れやすい、関節痛が現れます。
中枢神経の異常を起こし、脳の機能が侵されることがあるので運動機能障害があらわれることがあります。
この病気の怖いところは、弁膜症という後遺症を残す危険性が高いことです。
弁膜症は心臓の弁の病気で、心不全の原因になったり、突然死の原因になるここともあります。
リウマチ熱は再発しやすく、再発することに、弁膜症のリスクも上がります。
再発を防ぐために、5年以上抗生剤を飲む必要があります。
ちなみに関節の変形や痛みが起こる、関節リウマチとは別物です。
◯中耳炎
特に子供に多い合併症です。
子供は、耳管が短く角度が水平なため、ウイルス感染で炎症が起こると詰まりやすく、膿がすぐに溜まってしまいます。
抗生剤を飲むことで治ることが多いですが、治らない場合は鼓膜を切って膿を出すこともあります。
◯扁桃炎、咽頭炎
溶連菌感染症の合併症の中で、発症することがもっとも多い病気です。
喉の強い痛みのために、食べ物などの飲み込みができなくなります。
咽頭炎だけの場合は熱は出ませんが、扁桃炎を発症すると40度近い熱が出ます。
抗生剤を飲む治療が中心で、点滴を打つこともあります。
◯副鼻腔炎
頬や額、眉間の部分に副鼻腔がありますが、溶連菌感染することで副鼻腔に膿が溜まることがあります。
頭痛や蓄膿のような症状がでます。
抗生剤を飲むことで治りますが、体質により再発を繰り返したり、慢性化したりしてしまうこともあります。
◯「伝染性膿痂疹(とびひ)」や「丹毒(たんどく)」などの皮膚への感染
溶連菌が皮膚に感染すると、感染した深さによって、次のように症名や症状が変わります。
- 伝染性膿痂疹…表皮に感染、皮膚にかさぶたや膿がでる炎症が起こり、次々と広がっていく
- 丹毒…真皮に感染、皮膚に熱を持った炎症が起こり、痛みや発熱がある
- 蜂窩織炎(ほうかしきえん)…皮下組織に感染、皮下脂肪に炎症が起き、老人や糖尿病患者に発症しやすい
皮膚への感染も、抗生物質や点滴で治ります。
◯猩紅熱
猩紅熱を発症すると、寒気、発熱、喉の痛みがでます。
最初は熱が出て、その後赤い発疹が起こるケースが一般的です。
額と頬が赤くなり、口の周りが青白く見え、舌は白苔がたくさん現れます。
白苔がはがれると、苺舌と呼ばれる、舌が真っ赤になります。
抗菌薬が効果的で、他の合併症を予防できます。
◯リンパ節炎
リンパ節にウイルスが感染し、痛みや腫れがでます。
首やわき部分に腫れが起こるケースが多いです。
[quads id=4]
どうして合併症が起こるの?
溶連菌感染症を発症すると、抗生剤を飲むことがほとんどです。
それなのに、どうして合併症が起こってしまうのでしょうか。
◯薬を飲みきっていない
最も考えられる理由が、薬をすべて飲みきっていないので、ウイルスがすべて死滅していないことです。
抗生剤はとても効き目が強いため、1日で症状が治まってしまうことは珍しくありません。
症状が治まったため、治ったと勘違いして薬を飲むのをやめてしまうと、ウイルスはすべて死滅せず体内に残ってしまいます。
一見すると、体調は回復したように見えても、免疫力は低下したまま。
残ったウイルスが増殖し、合併症が起こってしまいます。
抗生剤は、一定期間飲み続けてこそ、本当の効果を発揮します。
薬はすべて飲むことで、治るように計算して処方されているので、すべて飲みきるようにします。
子供が薬を嫌がる姿はかわいそうで、飲ませるのは一苦労ですよね。
でも、合併症を起こさないためにも、すべて飲ませるようにしてください。
◯処方された薬が溶連菌の種類と違っていた
溶連菌には種類がいくつかあるので、出された薬が溶連菌に適していないと、効果が少ないケースもあります。
最近は、今までの抗生剤では、効果が少ない溶連菌も存在します。
症状に応じて抗生剤の種類も変わってくるので、2~3日たっても効果がない場合は再度診察を受けてください。
[quads id=4]
溶連菌を治療する方法
子どもが集団感染をするイメージが強い溶連菌ですが、疲れがたまっていたり、子どもから移されたり、大人も感染してしまうことがあります。
「同じ溶連菌なら治療の方法は同じよね?」と考えて、大人の薬を半量にして子どもに飲ませた、なんて経験ありませんか?
これはとっても危険なケースのようです。
子どもと大人では、体の大きさや免疫力が違うため、処方される種類や量など、それぞれに適した治療方法が必要です。
◯溶連菌の治療は抗生物質が中心
大人も子どもも、溶連菌を治療する方法は基本的には同じで、抗生物質が使うのが一般的です。
抗生物質の種類は、
- ペニシリン系
- マクロライド系
- セフェム系
の3つが良く使われます。
◯抗生物質のアレルギーに注意
抗生物質は即効性あり効果が高いので、とても溶連菌の治療に有効な薬です。
でも、注意しなければならないのが、抗生物質への副作用とアレルギー反応です。
下痢や血便などの副作用、蕁麻疹などのアレルギー反応が出るケースがあります。
呼吸困難などのアナフィラキシーショックがでたときには非常に危険です。
これらの症状が出たときには、すぐに薬の使用を中止し、医師の診察を受けてください。
子どもはアレルギーに弱く、どんなアレルギーをもっているか分からないことも多いので、抗生剤を使った時の反応には、より一層の注意が必要です。
◯状況によって薬を変えることも必要
また、アレルギー反応だけでなく、抗生物質の治療を受けていても、効果が現れないことがあります。
2~3日経過しても薬の治療をしても効果がないなら、溶連菌と抗生物質が合っていない可能性があります。
効果がない薬を飲み続けていると、溶連菌が治らないだけでなく、合併症を引き起こすケースもあります。
早めに、もう一度、医師の診察を受けてください。
溶連菌の合併症は非常に危険なものが多いため、治療中、急な異変がないかなど、経過に注意してください。
[quads id=4]
◯大人の解熱鎮痛剤
溶連菌の治療で、大人と子どもで処方される薬の種類が全く違うのが、解熱鎮痛剤です。
大人によく使われる解熱鎮痛剤は、「ロキソニン」「ポンタール」などの非ステロイド性の薬です。
薬局でも購入できるので、手軽に使用することができます。
手軽に使用できるのですが、
- 胃炎、胃潰瘍などの胃腸障害
- アスピリン喘息で息が苦しくなる
- むくみ
- 湿疹などの皮膚障害
- 強烈な眠気、だるさ
などの副作用を起こすこともあります。
副作用が強い時は、使用をすぐに止め、医師の相談を受けておきます。
今後の薬の処方にも、細心の注意を払わなければならないので、どの薬で副作用が出たかをきちんと覚えておいてください。
◯子どもの解熱鎮痛剤
子どもには副作用が少なく安全性の高い、「カロナール」や「アンヒバ」などのアセトアミノフェンがよく処方されます。
副作用が起きることは少ないのですが、短い期間に続けて使うと、腹痛や下痢、皮膚障害がでる場合があります。
下痢ほどひどくなくても、便が柔らかくなることがよくあります。
また、子どもに解熱鎮痛剤を使用するとき、ぜったいに大人に処方する非ステロイド性の鎮痛剤を使ってはいけません。
非ステロイド性の鎮痛剤を子どもに使用した時の副作用は恐ろしいです。
肝機能障害、意識障害、最悪の場合、命を落としてしまった事例があります。
量は関係ありません、半量、4分の1でもダメです。
◯すぐに解熱鎮痛剤を使わない
解熱鎮痛剤は、溶連菌を治療するというより、38度以上の高熱による脳の障害を防ぐために使います。
熱が出るのは、溶連菌と体が戦っている証拠です。
熱が出たからといって、すぐに解熱鎮痛剤を使ってしまうと回復を遅くします。
特に子どもに解熱鎮痛剤を使う時は特に注意が必要です。
間違った使用法をすると、体温が下がりすぎる危険があります。
◯大人と子どもでは症状の現れ方も違う
大人は、免疫力・体力がついているので、溶連菌に感染しても症状が軽く、無自覚なことも多いです。
のどの痛みが、少しある程度で「風邪を引いたかな」程度で、自然治癒することも珍しくありません。
しかし、無自覚でも感染していることに変わりなく、周囲に移す可能性は否定できません。
知らない間に、大人が子どもに移していて、子どもだけがつらく苦しむ…ということも。
溶連菌に感染しているかどうかは自己判断ができませんが、それだけに日ごろの、手洗い、うがいで予防することが大切です。
[quads id=4]
大人が仕事に復帰するまでの目安
溶連菌は人に移してしまう可能性があるので、できれば仕事を休んだほうがよいでしょう。
溶連菌に感染すると
- 38度以上の発熱
- 喉、リンパ線が腫れる
- 手足に赤い発疹
- 下痢、腹痛
- 嘔吐
- 頭痛
などの症状あり、特に喉の痛みが出ることが多いです。
大人は症状が出なかったり、出てたとしても軽いケースもあります。
周囲の人がみんな元気で健康なら感染する確率も低いですが、会社の人の健康状態なんて、把握できませんよね。
医師に相談しても、休むように言われることがほとんどです。
ちなみに、子供の場合は「医師の診断が必要で、登校は避ける」病気とされて、免疫力の低い人にはうつってしまいます。
◯仕事の種類よっては必ず休まないといけない
保育士や幼稚園の先生、教師、介護士など集団生活の中で仕事をしている人は、感染させるリスクが高くなるため、仕事は休むように指示がでます。
特に、介護士は、免疫力落ちている高齢者と接することが多いため、特に注意が必要です。
◯2~3日は休まなければならない
溶連菌は完治するまで、2週間~1か月ほどかかりますが、その間ずっと休まなくてはいけないということはありません。
症状が軽い場合は、抗生物質を飲み、1日たって症状が軽減していればその後2~3日で仕事へ復帰できるケースがほとんど。
周囲に感染させる確率もグッと低くなります。
薬を飲んでいる2日間は休み、3日目に診察を受けて許可が出れば会社にいけるパターンが多いです。
◯再発に気を付ける
仕事に復帰しても完治しているわけではないので、できるだけ無理をせず、再検査で完治したことを確認します。
大人は、症状が治まると処方された薬をすべて飲まなかったり、忙しさから完治していないのに無理をすることが多いものです。
そのため、大人の溶連菌は再発しやすく、中耳炎、気管支炎、副鼻腔炎などの合併症を引き起こす傾向があります。
処方された薬をすべて飲みきり、1か月後は完治したか医師による診断を受けておくのが安心です。
◯仕事に復帰してからも注意が必要
抗生物質を飲んでから、症状が落ち着けば、感染させるリスクも低くなり仕事にも復帰できます。
ですが、先にもお伝えしましたが、完治しているわけではありません。
溶連菌は抗生物質で治すことはできますが、感染の予防を止める薬はないため、まだまだ注意が必要です。
復帰してから気を付けるポイントとしては、
- マスクをして飛沫感染を防ぐ
- 同じ食器、タオルを使わない
- 手洗い、うがいをする
などに注意して下さい。
復帰してからは、無理をしないことはもちろん、周囲に移さない配慮が肝心ですね。
[quads id=4]
まとめ
大人の場合は、自己判断で薬の服用をやめてしまうと、再発や合併症の発症につながるケースがあります。
症状が出る時は、免疫力が低下しているときですから、自然治癒するから大丈夫だ、と油断しないようにしてくださいね。
2週間近く薬を飲み続けるのはつい億劫になってしまいますが、症状が出たのであれば後々のためにも溶連菌の薬はしっかりと飲み切りましょう。
子供が感染してきたらマスクやうがい、手洗い、そしてバランスのとれた食事と睡眠で免疫をつけることも大切ですよ。
こんな感染症にも注意!
→おたふく風邪は初期症状が出る前からヤバい?大人も気を付けよう!
家庭内で移してしまう感染症は、ちょっとの知識があれば予防できることも多いですよ。感染経路や予防対策は必見ですね。
[quads id=5]
[quads id=6]


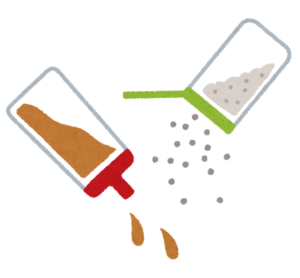
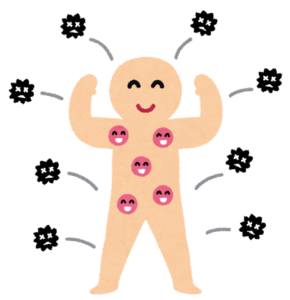





コメント