比較的に飼育が簡単と言われるイモリ。
人気が高まっているとは言え、まだまだ、飼育する人も少ないので、どうすればいいか悩みますよね。
イモリの飼育で最も気を配るってほしいことは、気温の管理です。
イモリは暑さに弱いので、冷暖房が完備の、人間と同じ環境だと死んでしまうのです。
今回はイモリを飼育する時に知っておくべきこととして、
- イモリに最適な気温とは?
- イモリのエサには何を上げるべきか?
- 飼育する時の3つの注意点について
をご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
[quads id=1]
イモリの飼育に最適な気温

自然の中で生きているイモリは、人間が冷たいという水温でも生活していますよね。
イモリはある程度の低温でもエサを食べ、排泄ができるなど生きていくことができます。
適温は15〜20度と言われていて、低温に強い性質があります。
反対に高温には弱く、気温30度を超えると確実に生きられず、死んでしまいます。
20度前後であれば、何とか生きられるのですが、25〜26度はイモリにとってはやや暑い、辛い気温になります。
◯イモリは寒さには強いが暑さには弱い
例えば、夏場の明け方の、25〜27度を私たちは涼しいと感じますよね。
でも、イモリにとっては暑い温度になんですよ。
それだけ、暑さに弱いのです。
夏の室温が27度ぐらいの設定の場合は、飼育ケースの中や側に、凍ったペットボトルをいれてケース内の温度を下げてあげてくださいね。
◯10度以下では活動が鈍る
低温に強いと言っても、外の水が凍ってしまうほどの気温では生きていけません。
10度以下になると活動が鈍り、冬眠を始める温度に近づいていくため、エサもあまり食べなくなります。
さらに5度以下になると、イモリの適温よりも寒くなってしまうため、弱っていきます。
[quads id=2]
飼育のポイント!エサや寿命は?

温度以外で気になることと言えば、まずエサですよね。
イモリは基本的になんでも食べます。
イモリは、自然界では
- コオロギなどの虫
- イトミミズ
- 赤虫など
を食べています。
◯家で飼育する時に食べさせるエサ
人が飼育するときは、生き餌を実際にとってくることもできますが、ペットショップでも赤虫やイトミミズなどが売られています。
また他の生き物用のエサ、そしてお肉を食べます。
どのようなエサを用意すればいいのか、下記のとおりまとめました。
- ウーパールーパーのエサ
- 金魚のエサ
- かめのエサ
- 魚肉ソーセージ
- 鳥のささ身
- レバー
- シラス
魚肉ソーセージなどは塩分が多いので、少なめにあげるようにします。
◯水道水は与えない

エサをあげると同時に水もあげましょう。
金魚などを飼ったことがある人は、良くわかると思うのですが、水中で生活する生き物は水道水に弱いです。
殺菌のために、水道水中に含まれる塩素は、人にとってはほぼ無害でも、生き物にとって有害になります。
ペットボトルなどに、水道水を入れ、キャップをせずに1日置けば塩素(カルキ)が抜けていきます。
浄水器のミズを使ってもいいです。
水を沸騰させる方法もありますが、水中の酸素も抜けてしまうので、おすすめできません。
◯イモリは長生き
イモリは意外と長生きです。
大事に育てると20年ほど生きることができます。
アカハライモリでは、長くて30年ほど生きるケースもあります。
長生きなので、気温管理などに気を配り、できるだけ長生きさせてくださいね。
[quads id=3]
イモリの冬の越し方

自然のイモリは10度以下の気温になると活動が鈍り、冬眠を始めます。
飼育しているイモリも冬は、冬眠をすることも多いです。
イモリを飼育ケースの中で冬眠させるためには、冬眠に適した環境を作る必要があります。
また、冬眠を始めると餌を食べないので、餓死しないように冬眠のエサやりもポイントです。
◯気温は10度以下を保つ
気温が15度程度になると、イモリは冬眠から目覚めてしまいます。
冬の間(少なくても2〜3か月)は、十分に冬眠させて、自然に目覚めさせてあげたいですよね。
しっかり冬眠すると、繁殖もしやすく長生きもします。
室温をきちんと5〜10度に保つか、屋外の安全な場所に移しておきます。
◯適度な水分と隠れる場所をつくる
イモリが冬眠するときにはたくさんの水は必要ありません。
園芸用の水苔などにたっぷり水を含ませて、飼育ケースに入れます。
水分が乾ききってしまう前に、スプレーなどで、湿らせます。
そして、石や枯れ枝、枯葉、苔などで冬眠中に隠れる場所を作ります。
◯冬眠前のエサやり
冬眠中に餓死しないように、日ごろからエサをきちんと与えておくこともポイントです。
冬眠する前だからと言って、無理にエサを与えると肥満してしまうこともあるので、その必要はありません。
毎日、きちんろとエサを与えていれば十分です。
冬眠中はそのままにせず、お腹空いたり、喉が渇いたりすると起きる時もあるので、毎日観察することを忘れないようにします。
まだ、個体が小さかったり、痩せている場合は、あえて冬眠させる必要はありません。
室温は15度以上にして冬を越させます。
◯初めての飼育の場合は、冬眠させない方法もある
初めてイモリを飼育する場合は、エサやりや水やりのタイミングが難しく、上手に冬眠させられないこともあります。
上手く冬眠できないと、イモリは死んでしまう可能性がとっても高いんです。
イモリの成長のためには冬眠をさせるほうがいいのですが、冬眠をしないと死んでしまうわけではないので、絶対に、させるものではありません。
あえて冬眠させて、弱らせてしまうより、しばらく飼育して、お世話に慣れてから冬眠させるのが安心ですね。
[quads id=4]
イモリを飼育する時に気を付けるべき3つの注意点

イモリは飼いやすい生き物ですが、飼育する時にはやはり注意点があります。
イモリを飼育する時には、これからご説明する3点を守ってくださいね。
1)イモリは脱走をする
イモリが死んでしまう原因は、餓死のほかに、飼育ケースの蓋からの脱走があります。
脱走してすぐ見付けることができたり、脱走した場所に、生きていく環境があればよいですが、そのままにしておくと干からびてしまいます。
お世話の時に、蓋を閉め忘れ、蓋がないケースで飼育してしまう人もいます。
必ず、蓋がある飼育ケースで育て、蓋を確実に締めるようにします。
脱走すると、水がある場所に向かう傾向があるので、もし、ケースの中にいないことに気が付いたら、水気がある場所を主に探すといいですよ。
2)イモリの病気に気を付ける
イモリも環境が整っていないと病気をします。
よくある病気は「モルチペスト」という、体に白い斑点がでる病気や皮膚がもやもやする、水カビによる病気です。
あまりにもひどい場合は、薬で洗うようにします。
また、水替えを忘れないことも、病気を防ぐ方法です。
脱皮が上手くいかないこともあるので、皮が残っているときは優しく取り除いてあげます。
また、病気ではありませんが、イモリは共食いをするケースがあります。
イモリの体調があまりに違いすぎる時は、同じ飼育ケースに入れないようにしてください。
3)イモリの毒に注意

イモリには皮膚の下から毒を出す毒腺があります。
可愛いからと必要以上に触るのはおすすめできません。
毒が付く可能性は高いですし、人間の体温でイモリが弱る危険性もあります。
イモリは人間に触られることに慣れないと、ストレスになります。
毒が付いたとしても、毒性はそれほど高くありませんが、イモリを触った後は、その手で目や口を触らないようにします。
お世話の後は、石鹸で手をきれいに洗い、消毒用アルコールで除菌します。
イモリだけに限らず、生き物を飼う上での、大切なポイントの一つです。
[quads id=4]
まとめ
飼育が簡単で道具がそれほど必要ないと言われるイモリも、気温やエサ、環境作りなど、気を配るべきことは結構ありますね。
難しいことはたくさんありませんが、気温管理には特に気を配ることが大切です。
エアコンがあるので、室温の調節は簡単そうですが、暑い夏の外出中など、うっかり気温が高くならないように注意が必要です。
イモリは長生きの生き物です。
大切に育てて、寿命いっぱいに飼育してあげてくださいね。
[quads id=5]
[quads id=6]

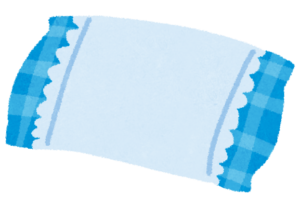







コメント