4月中旬と言えば新年度がスタートして、新しい環境に慣れ始めたころです。
入学式も終わり、中旬からは平常通りの授業が始まります。
それに伴ってお母さんの中には役員に選出されて挨拶の手紙を用意することがありますよね。
町内会などの公式な回覧文でも、文書を書くことの多くなる時期です。
そんな時に文頭に時候の挨拶を使ってスマートな挨拶文を書きたいですね。
ここでは4月中旬に使える時候の挨拶を、例文付きで紹介します。友人あての季節の手紙など色々な場面に応用できるので参考にしてみてください。
[quads id=1]
4月中旬の時候の挨拶のコツ

4月中旬になると、桜が満開から一気に散り始める春真っ盛りのころですね。
ニュースでも桜の話題が多く、街を歩く人の装いも春らしい明るい色が増えてくる季節です。
春の暖かさを表す「春陽」「仲春」「春粧」という言葉や「軽暖」「陽春」などは4月を通して使いやすい言葉です。
4月中旬は10日~20日が目安
なお、二十四節気では、4月20日ごろに穀雨(こくう)という、春の雨の降る季節をさす言葉があり、その前までが中旬になります。
また地域によっては、まだまだ桜という言葉を使いたい季節でもあります。
まだ咲いている場合なら「桜花」、既に散り始めているところでは「桜端」など、身近な様子を表すのがポイントです。
[quads id=2]
町内会、保護者会のお知らせに使える例文
書き出しの例文
大勢の人が見る文書の場合は書き出しもふさわしい言葉を選びたいですね。
町内会のお知らせの書き出しなら、
「花の盛りも過ぎ、吹く風もやわらかな季節となりました。町内会の皆様におかれましては健やかにお過ごしのことと存じます。」
「花見の季節も終わり新緑が鮮やかに芽吹いてまいりました」
保護者会やクラス役員の挨拶には、入学式などの様子を加えるのも、素敵な挨拶になりますね。
「うららかな好季節を迎えました。先日の入学式では我が子の成長を感じ、皆様も感慨深くご覧になったことでしょう」
「心地よい春風の季節となりましたね」
きちっとした目上の方への手紙なら、
という書き出しなどはしっかりした印象を与えてくれます。
「~の候」や「~のみぎり」などを使うと、簡単に引き締まった文書となりますよ。
結びの例文
町内会や保護者会などの文書では、総会などの出席を求めるものも多いですよね。
そんな時は、結びに時候の挨拶を使わずに、「万障お繰り合わせのうえご参加くださいますようお願い致します」などで締めくくる場合も多いです。
友人や親しい間柄への手紙で使える例文
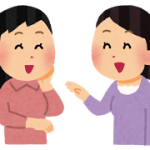
書き出しの例文
友人向けにはくだけた言い回しにして、時候の挨拶にアレンジを加えると親しみやすい言葉に早変わりします。
例えば4月が旬の食材を使ったり、庭先の様子を入れてみると、
「スーパーにたけのこが売られているのを見つけ、おいしい春を実感しております」
「桜の季節が足早にすぎ、我が家の庭ではつつじのつぼみが膨らみ始めました」
このように身近なことで季節を感じた瞬間を言葉にして添えてあげるだけで、おしゃれに見えますね。
結びの例文
友人へや親しい親戚へ宛ての手紙では
「新年度を迎えお忙しいとは存じますが、風邪など引かないようご自愛ください」
「春本番、うららかな気候をお互い思う存分満喫しましょうね」
などと相手へ語り掛けるような言葉で結ぶのもいいですね。
[quads id=3]
まとめ
4月中旬につかう時候の挨拶としては、大勢に向けた文書では「~の候」などの表現がふさわしいですね。
文書を出す相手によっては堅苦しくならないように、身近な光景などを時候の挨拶に加えて少しくだけた調子にアレンジするといいです。
時候の挨拶とは、自分の感じた季節感を伝えるものです。身の回りのできごとを自分の言葉で表現してみると楽しく手紙を書けますよ。
旬の食べ物を話題にだすのも簡単に季節を感じることができます。
まずは、基本の「春陽」「仲春」「春粧」などの言葉をおさえつつ、例文を参考に、自分なりの季節を感じる言葉を探してみましょう。
年や地域によってちがいますので、前後の季節の言葉も確認しておいてくださいね。
4月上旬の時候の挨拶
→時候の挨拶で4月上旬に使う言葉は?入学のお祝いの季節です!
4月下旬の時候の挨拶
年や地域によって同じ時期でも気温が違うことがありますので、ルールに縛られることなく、その時の季節を感じる言葉を使えば大丈夫ですよ。
[quads id=5]
[quads id=6]

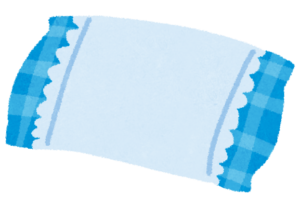







コメント
コメント一覧 (1件)
[…] →時候の挨拶を4月中旬に使おう!町内会でも使える季節の言葉は? […]