夏休みになると、悩んでしまうのが自由研究ですが、できれば手軽に済ませたいですね。
そんな時は、身近にある卵で、おもしろい実験をしてみてはいかがですか?
「夏休みがもう終わりそう!」
「時間をかけて実験の自由研究なんてできない!!」
と焦らなくても大丈夫なように、簡単にできる実験を集めました。
自由研究にぴったりな、卵を使った実験について、ご紹介していきます。
[quads id=1]
自由研究におすすめ!スケルトン卵を使った2つの実験
卵が透明なゴムボールのようになってしまうスケルトン卵。
こんな状態になります。
◯スケルトン卵を作る実験
お酢が卵の殻のカルシウムを解かす性質を使った実験で、3日間で終了します。
材料
- 水で良く洗った卵
- お酢
- 卵が入る大きさの瓶(卵1個につき200mlのお酢が必要なのでそれが入る大きさのもの)
方法
1)瓶の中に卵を入れ、卵が全部つかるほどのお酢を入れる
2)卵から泡が出てくるのを確認したら、キッチンペーパーなどで蓋をする
(ほこりやゴミが入らないようにするためです、二酸化炭素が発生するので、密閉してはいけません。)
3)2日目になったら、殻がどれぐらい溶けているか確認、もう1日置く
あまり溶けていなかったら、かき混ぜるか、お酢を交換する
4)殻が溶けて、薄皮だけになっていたら完成
少し残っているときは、水で優しく洗ってきれいにする
これで完成です。
薄皮はカルシウムではないので、溶けずに残り、ゴムボールのようになります。。
また、実験に使ったお酢は、料理には使えないので捨ててください。
完成したスケルトン卵も食べても命に問題はありませんが、食べるためのものではありません。
[quads id=2]
◯スケルトン卵で浸透圧の実験

このスケルトン卵で、さらに展開した実験ができます。
お酢でスケルトン卵を作ると、よく見ると、元の大きさよりもやや大きくなっています。
これは、浸透圧の関係で、卵の中に水分が移動したためです。
この卵をさらにほかの液体に入れることで、種類による浸透圧の違いを調べることができます。
実験にかかる日数は2日です。
材料
- スケルトン卵(液体の数だけ)
- 水、しょうゆ、減塩しょうゆ、砂糖水など
- 卵が入る大きさの瓶
- 量り
方法
1)量りなどで大きさを量り、手触り、弾力を調べたり、写真をとる
2)漬ける液体を同じ量だけ準備して、瓶の中に卵と一緒に入れる
3)1日、冷蔵庫で保管する
4)1日たったら、水できれいに洗い、水気を優しくとり大きさなどを調べる
ご紹介した液体以外にも、ジュースやお味噌汁、麺つゆなども面白いと思います。
スケルトン卵だけだと、同じ実験の自由研究がある可能性もあります。
少し付けくわえるだけですが、もう少し踏み込んだ実験になりますね。
[quads id=3]
本当に時間がない時にオススメの3つの卵実験
夏休みもギリギリになってしまって自由研究の時間が取れない時は、こちらの短時間でできる実験にチャレンジしてみてください。
◯卵で虫歯予防のフッ素の効果を実験する

歯と同じようなカルシウムでできている卵の殻を使って、フッ素に虫歯予防の効果があるかを確かめる実験です。
実験時間は約30分でできます。
歯磨きが嫌いな、お子さんにもおすすめですよ。
材料
- フッ素配合の歯磨き粉
- 卵
- 酢(食べ物の酸の代わり)
- 瓶
- 油性マジック
- 歯ブラシ
- カレースプーン
方法
1)卵の殻に、線を引き、フッ素を塗る部分と塗らない部分がわかるようにする(フッ素を塗る部分には「あり」塗らない部分は「なし」と書く)
2)卵の殻の「あり」の部分に、歯磨きを塗り3分置いた後、軽く流す
3)瓶の中に水を入れ、スプーン1杯の酢を入れて混ぜ、卵を全部沈ませる
4)卵の殻の様子を見て、小さな泡が出始めるまで、酢を足していく
5)5~7杯ほど入れると泡が出てくる
6)フッ素を塗ったほうは、あまり泡が出てこないことを確認して終了
小さな泡は、カルシウムが溶け出しているためにできるものです。
この実験では、まず、泡ができることで、食べ物の残りかす(酸)が歯を解かすことを確認します。
そして、フッ素を塗った部分は泡が少ないことで、カルシウム(歯)が溶けないことも確認するのが目的です。
◯卵を水に浮かす実験

これは、食塩水の密度を使った実験で、アルキメデスの原理を調べる実験です。
水の密度(1g/cm3)が卵の密度(1.09g/cm3)を超え、卵が浮くまで食塩を足していき、加えた食塩の量を調べます。
1日あれば終了します。
材料
- 卵
- 計量カップ(500ml)
- 食塩200g
- スプーン
- 量り
方法
1)計量カップに水を400ml入れ、卵を沈める
2)卵が沈んだことを確認
3)食塩を量りながら加えていき、よく混ぜて、卵の様子を観察
4)卵が浮くまで、食塩を量りながら加えていく
5)卵が浮いたら、合計で何グラム入れたか確認して終了
1日で終わるので、本当に時間がないときはおすすめです。
[quads id=6]
◯黄身返し卵を作る実験

黄身返し卵とは、遠心力を利用して、黄味と白身を逆さまにした、外側が黄色い卵のことです。
江戸時代のレシピ本に載っていたという面白い料理です。
作り方が難しく、昔は、上手に黄味と白身が逆さまになりませんでしたが、現在では、作り方が改良されて成功率は上がっています。
これを、どのように実験するかですが、黄身返し卵を作る時に、卵を何回、回転させれば成功するかを見ていきます。
材料
- 卵
- ストッキング 片足
- セロハンテープ
- 針金(お菓子やパンの袋を閉じるものが便利)一本
- 懐中電灯 一本
- 画鋲 一個
- クリップ
方法
1)卵の頭に画鋲で穴を開け、伸ばしたクリップを入れて、黄身を崩すようにかき混ぜる
2)卵が割れないように、セロテープを巻き付ける
3)ストッキングの中心部分に一か所結び目を作り、卵を入れる
4)反対側は、針金で留めて卵が移動しないようにする
5)卵が入ったストッキングをぐるぐる回転させ、両端を引っ張って高速回転をかける
6)懐中電灯を当て、光を透かして黒くなっていたら、反転した証拠になる
7)茹でて、真ん中を切って、成功しているか確認
実験では、手順5の回転数を数えて、手順7で成功していたかを確認するデータをまとめます。
卵の殻を使って絵を描く

出典:http://asobimakuri.jugem.jp/?eid=144
実験からは少し離れますが、学年が低いなら、卵の殻を使って絵を描く自由研究もおすすめです。
卵の殻を乾かし(薄皮もはがす)、色を塗り、もう一度乾かしてから、細かく砕きます。
下絵の上に、ボンドを使いながら、殻を貼っていきます。
3原色の赤、青、黄色だけを使ってできた色を紹介し、卵の殻に色を付けていくと実験性を出すことができます。
まとめ

身近な卵で、短い時間で色々な自由研究ができますね。
今回ご紹介した実験は、危険な薬品を使うことはありませんが、瓶、お酢の取り扱いに注意し、換気も十分にしてください。
実験の自由研究では、研究したことを分かりやすく、まとめるのもとても大切です。
写真などを使って、実験したことがきちんと伝わるようにまとめてくださいね。
◯他の自由研究ネタを探している方はこちらも
中学生向け
小学生向け
困ったときのヒントにぜひご活用ください。
悩む前にまずやってみると、面白くなっていきますよ。
[quads id=5]
[quads id=6]

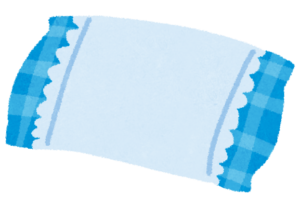







コメント