生後100日祝いとして行われるお食い初めですが、本来どのような意味があるのか、分かりやすく説明できますか?
せっかくお食い初めを予定しているのでしたら、意味や由来を知っておくほうがよいです。
同じ赤ちゃんのお祝いでも、意味を理解しておくと、より深く願いを込めることができますからね。
お祝いのメニューについても紹介していますので、家族みんなで赤ちゃんを囲んで、ワイワイ楽しく、お食い初めのお祝いをしてあげてくださいね。
[quads id=1]
100日祝いにお食い初めを行う意味

お食い初めとは、生後100日目を迎える赤ちゃんのお祝いの儀式です。
母乳やミルク以外の初めての食べ物を御膳で用意し、歯が生え始めるまですくすく成長したことを喜びます。
そして、「一生食べ物に困りませんように」「健康で丈夫に育ちますように」との願いを込めてお祝いします。
また、お食い初めという名前こそついていますが、実際に赤ちゃんに食べ物を食べさせるのではなく、食べる真似をさせる儀式となります。
◯100日にこだわる必要はある?
地域によっては110日目や120日目で100日祝いをする風習がありますが、一般的には100日目です。
しかし、家族が揃ってお祝いする方が喜びも大きいですから、100日目きっちりにこだわらなくても大丈夫です。
家族が揃いやすい吉日で、赤ちゃんの100日祝いをしましょう!
◯儀式はまず形を守ることから!
男の子ならおじいちゃんの左膝に、女の子ならおばあちゃんの右膝に座らせてお食い初めを始めます。
正式には、お食い初めの席で1番長寿の人がお箸を持って行います。
食べさせる順番は、ご飯→汁物→ご飯→魚→ご飯の順番に、3回食べさせる真似をします。
また、多少アレンジしてもよいでしょう。たとえば、年長者だけでなく家族全員で交代で食べさせるのも記念になっていいですね。
[quads id=2]
お食い初めの由来
お食い初めの由来は、平安時代にさかのぼると言われています。
その頃は、生後100日祝いではなく、生後50日目にあたる頃、重湯の中にお餅を入れ、そのお餅を赤ちゃんの口に少しだけ含ませる儀式がありました。
それを「五十日(いのか)の祝い」と呼び、50日目に食べるお餅を五十日餅(いのかもち)と呼んでいました。
その後、五十日の祝いが「百日」になり、鎌倉時代にはお餅が魚に代わり「真魚始め」と呼ばれるようになりました。
いろんな呼び名があり、室町時代には初めて100日祝いの「お食い初め」と呼ばれ始めました。
○100日祝いの呼び名の種類
・箸初め
・箸揃え
・真魚始め(まなはじめ)
・百日(ももか)
地域によっては、今でも「お箸初め」と呼んだりもしますが、一般的には「お食い初め」として定着し、現代へと脈々と受け継がれています。
[quads id=3]
まとめ
生後100日祝いとして行われるお食い初めは、家族のよき思い出になります。
赤ちゃんがすくすくと育ち、家族で行ったイベントのことを理解できる年になったら昔話に花が咲きますよ。
子供は自分が赤ちゃんだったころの話を聞くのが好きですから、記念写真を見せながら「この時はこれを食べたのよ」「石を口に当てるときょとんとしてたっけ」など、お話してあげたいですね。
その時は、お食い初めの意味をしっかりと伝えることで、家族の深い愛情も一緒に感じられると思いますよ。
メニューの意味も知っておこう!
お食い初めに準備するお祝いのメニューにも、それぞれ意味が込められています。昔ながら定番メニューと、今風の人気お祝いメニューを紹介しています。
[quads id=5]
[quads id=6]

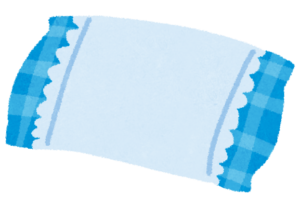







コメント
コメント一覧 (4件)
[…] →100日祝いのお食い初めはいつから行われている!?意味と由来を調べてみた! […]
[…] →100日祝いのお食い初め!意味と由来とは? […]
[…] →100日祝いのお食い初めを説明できる?意味と由来を知っておきたい! […]
[…] →100日祝いのお食い初めとは!意味と由来まとめ! […]